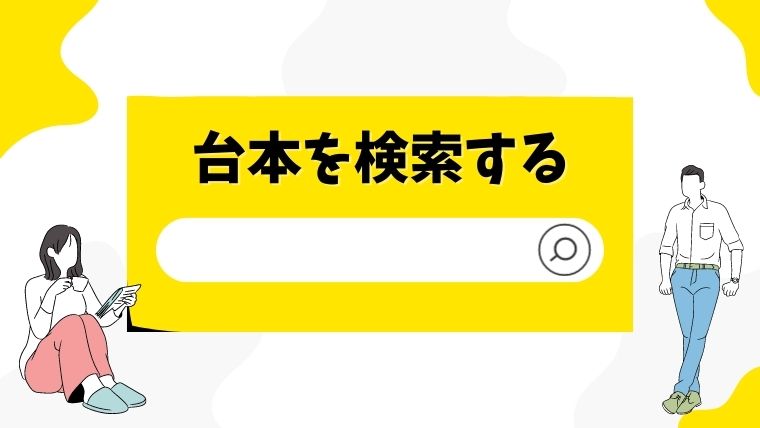●使用料:無料
●利用報告:商用のみ要(非商用は任意)
●クレジット表記:必須
ー表記内容ー
| 台本名 | 当ページのタイトル |
| 作者名 | 紺乃未色(こんのみいろ) |
| サイト名 | フリー台本サイト「キャラコエ」 |
| 台本URL | 当ページのURL
※リンク付け(URLをクリックすると、当ページに飛ぶように設定すること)必須 |
上記4点を必ず表記していただきますよう、お願いいたします。
利用のルールについては、利用規約をご覧くださいませ。
概要
| カテゴリ | 朗読(一人) |
|---|---|
| ジャンル | 現実世界 |
| 時間(目安) | 10分~15分 |
| あらすじ | 黒い服を着た少女がインターフォンを鳴らしている。 怖い、と思うよりもさきに、血の気が引いた。 とある会話を思い出したからだ。 |
| 注意 | このストーリーはフィクションです。実在する人物や団体、出来事などとは一切関係がありません。 |
その他、朗読におすすめの台本は、以下のページにまとめています。

フリー台本『ねえ、忘れてるの?』
1
ピンポーン。
ピンポーン。
インターフォンの音がやけに大きく聞こえる。
リビングのソファの上で、俺はなんだかとてもイヤな予感がした。
だって、音が2回鳴ったのだ。
1回鳴るのは、マンションの共同玄関《きょうどうげんかん》から呼び出されたとき。
そして、2回鳴るのは……。
まさに、部屋の前のインターフォンのボタンをプッシュされたとき!
つまり、そいつは、すぐそこにいる。
誰だ!!??
おそるおそる、モニターを見てみると、そこには真っ黒な服を着た女の子の姿があった。
大きなマスクをしていて表情がまったく読めない。
……血の気が引いて「終わった」と思った。
つい、先日の会話がフラッシュバックする。
2
その日の学校帰り、俺は仲の良いクラスメイト二人と都市伝説《としでんせつ》の話で盛り上がっていた。
口裂《くちさ》け女だとか、トイレの花子さんだとか、人面犬《じんめんけん》だとか、古くからあるおなじみのストーリーに「そうだったっけ?」「こうじゃない?」などと、つっかかりながら、ファーストフード店でチーズバーガーに食らいつく。
なんてことない、俺たちくらいの高校生によく見られる光景だ。
たまに、オカルトちっくな話になるのもあるあるだと思う。
「あ、じゃあさ! 令和の都市伝説《としでんせつ》! 『忘れた約束』って知ってるか?」
突然、そんなことを言いだしたのは、ルキトだった。
「なにそれ?」
タクマはストローでがりがりと氷をかき混ぜながら聞いた。
たしかに、俺も気になる。
「怖がるなよ?」
ルキトが声を潜《ひそ》めて言った。
「まさかあ」
タクマが笑う。
「トキはどうだ? トイレに行けなくなっても、責任はとらんぞ」
ルキトがからかうように言った。
「平気だ」
俺は、ぴしゃりと言ってのけた。
「ならいい。あのな、話はこうだ。ある日、突然、黒い服を着た少女が家にやってくるんだ。ピンポーンってな」
あれ、思いのほか、怖いかもしれない。
そう感じたものの、いまさら引き下がることはできない。
俺にだって、プライドがあるのだ!
「それで?」
平然《へいぜん》を装い、続きを促《うなが》す。
「インターフォン越しに「はい」って出ると、その少女が言うんだ「あの日の約束、もう忘れた?」ってな。それで、ここでの正解は「覚えてる」だ。そしたら、「じゃあ、ドアを開けて。渡したいものがあるの」と話が流れる」
「開けるのか?」
タクマが尋ねる。
「そう。ちゃんと、少女が渡したいものを受け取るのが正解。そしたら、その子は立ち去って行く」
「ふうん。それで、なかに何が入ってるんだ?」
俺が尋ねると、ルキトはにやりと笑った。
「焦《あせ》るな。焦るな。なかにはな、紙切れがある」
「紙切れ?」
「そうだ。そこに住所が書かれているらしい。「ここに来て」とのメッセージ付きでな」
「まさか、それ行くんじゃないだろうな?」
「そのまさか! 行くのが正しい」
ルキトが言った。
「待て待て待て。俺はとっさに話を止めた。さっきから、正解、正解って言ってるけど、それ、不正解だったら、どうなるんだ?」
「聞く?」
ルキトが真剣《しんけん》な顔をして言った。
「聞く!」
俺はやけになって言葉を返した。
「話によると、不正解になった人は、人知れず消えてしまうらしい。それで、世間《せけん》が忘れた頃に、ひっそりと、遺体《いたい》が出てくるんだと」
背筋が冷たくなる。
「う……。それは……」
俺が言葉に詰まっていると、隣でタクマが「それは怖い」と言った。
おんなじ気持ちだ。
「まあ、都市伝説だけどな」
ルキトはなんでもないことのように言った。
「それで、家に行ったら? どうなるんだ?」
俺が尋ねると、ルキトは少し首を傾げてから口を開いた。
「ん? とくになにもない。ただ、何度も言うけど、この|都市伝説《としでんせつ》のポイントは、とにかく従うことなんだ。そうすれば、何も怖くない」
いや、十分怖いぞ!
俺はそう突っ込みたい気持ちを、メロンソーダーで|喉《のど》の奥へと流し込んだ。
そして今にいたるわけだ。
3
恐怖しかない。
ただ、あの都市伝説《としでんせつ》が本当なら、ルキトの話を聞いておいてよかった。
俺は、おそるおそる、インターフォンの通話ボタンを押した。
「はい」
たった二文字の言葉が震える。
「……あの日の約束、もう忘れた?」
きた!
俺はパニックになりながらも、正解を伝えるべく、口を開いた。
「いいや。覚えてるよ」
「……じゃあ、ドアを開けて。渡したいものがあるの」
一瞬《いっしゅん》、どうしようかと考えた。
いや、違う。迷っている場合じゃない。
都市伝説に従《したが》わなくては、消されてしまうのだから。
「わかった」
どうして、こんなときに限って、両親は不在《ふざい》なんだ!
大きく深呼吸し、思い切ってドアを開けると、そこにはやっぱり黒ずくめの少女がいた。
「はい。これ」
少女は小さな箱をぐいっと押し付けると、背中を向けて、静かに立ち去って行く。
かと思うと、ぴたりと動きが止まった。
なんだ?
少女はくるりと顔だけをこちらへ向けた。
瞬間、ばちりと目が合う。
「ひいっ!」
なさけない声がでる。
そんな様子を、少女はじっと眺めている。
俺は逃げるように、部屋へと飛び込んだ。
カギをかけることも忘れない。
荒い呼吸を繰り返しながら、震える指先で箱を開けようと試みる。
あー、いやだ、いやだ。もう、いやだ。
そんな、幼《おさな》い言葉ばかりが、頭に浮かんでは消えていく。
ええっと、ええっと……。
たしか、この中に紙切れが入ってるんだったよな?
ルキトの話を思い返す。
すぐに、この先の展開を思い出してぞっとした。
「え、俺……ほんとに、行くのか?」
箱の中には、話の通り、マンションらしき場所の住所が記された紙があった。
「まじか……」
このまま、少女も箱も、放っておいたらどうなるだろう。
ダメだ。
酷《ひど》い目にあうかもしれない。
俺に残されている選択肢《せんたくし》はただひとつだけ。
この場所へ行くしかないのだ。
とてつもなく嫌だけど!
いや、待て! なにも、一人で行けというルールはない。……はずだ。
俺はスマホをたぐりよせると、ルキトに電話をした。
……出ない。
それなら、とタクマに連絡する。
……電源すら入っていない。
どうしよう。
二人とコンタクトがとれてから、一緒に行きたい。
でも、早く行動しないと、《《謎のなにか》》がしびれを切らしてしまうかもしれない。
頭をぐるぐると回転させるものの、良い案はちっとも思い浮かばなかった。
「仕方ない」
俺は、こぶしをぎゅっと握って立ち上がった。
4
紙切れに書いてあるマンションは、いわゆるレンタルスペースだった。
建物《たてもの》自体には怪しいところはない。
自由に出入りできるエントランスを抜けて、指定の部屋の前に立つ。
あたりには、誰ひとりいなかった。
せめて、人通りが激しければ、安心できたのに……。
ああ、ぐずぐず言っていても、仕方がない。
俺は、自分に「大丈夫!」と言い聞かせながら、インターフォンを押した。
応答《おうとう》はない。
「帰ってもいいだろうか」
小さく呟くと、パタパタと扉の向こうで足音がした。
それも、一人じゃない。
俺はとっさに、身構《みがま》えた。
バタン、とやけに大きな音を立てて扉が開く。
思わずぎゅっと目を瞑《つむ》る。
……そのまま、数秒が経過《けいか》した。
人の気配はある。
だが、音がない。
おそるおそる視界を広げようと試みるが、それは叶わなかった。
5
パン! という破裂音《はれつおん》が響き渡り、目を閉じたまま、大きく一歩後ずさる。
「おめでとー!!!」
「え?」
まぬけな声が漏《も》れる。
今度こそ、目をぱっちりと開くと、そこには見知った顔が二つあった。
「あーー、もう、なに?」
俺はその場にへなへなとしゃがみこんだ。
「うわあ。お兄ちゃん、ちょっとやりすぎなんじゃないの?」
そう言った少女は、俺の家に来た、あの黒ずくめの子だ。
「お兄ちゃん?」
「ああ。こいつ、俺の妹」
ルキトがさらりと言った。
「はじめましてー」
少女がほほ笑む。
怖さなんて微塵《みじん》も感じさせない、可愛らしい女の子だ。
「そんなことよりー。トキってば、まだ、状況飲み込めてなくない?」
頭上でタクマの声がした。
「うん。え、なに? これ?」
俺が言うと、ルキトとタクマは顔を見合わせた。
「だーかーらー。今日、誕生日だろ?」
二人の声が重なる。
「あ、うん」
忘れていたわけじゃない。
ただ、インターフォンが鳴ってから、それどころじゃなくなってしまっただけだ。
「つまり、サプライズってわけ」
ルキトが言った。
「え、都市伝説は?」
「こいつの作り話。でも、なかなかリアリティあったよな」
タクマが答える。
「な……なんだあ」
俺はそこでやっと、自分の足で立ち上がることができた。
「まあ、入れよ。おいしいもんいっぱい揃《そろ》えたからさ。食え、食え」
テーブルの上には、ピザやらスナックやらが並んでいて、俺は盛大《せいだい》にもてなされた。
うん。とても、気分が良い。
さっきまでの緊張感《きんちょうかん》の反動か、まるっこいチョコレートがそこらへんに転がるだけで、楽しい気分になる。
「……そういやさ、トキ。お前、約束忘れてるのか?」
ふいに、ルキトがまじめな顔をして、そんなことを言うものだから、背筋が騒《さわ》いだ。
「え?」
なんだ、なんだ? まだ何かあるのか?
もう、かんべんしてほしい。
「あー、違う、違う。怖い話じゃないって」
俺の顔があまりにも引きつっていたのか、ルキトは片手をぶんぶんと振りながら宥《なだ》めるように言った。
「なに?」
「あー、やっぱり忘れてる」
タクマがけらけら笑った。
「ほら、去年のトキの誕生日、俺たち、頑張ってサプライズしようとしたのにさ、とちゅうで気づいちまっただろ?」
「ああ、うん」
そうだ。
あまりにもバレバレだったから、「もうわかってるから、普通に準備してくれて大丈夫だぞ」なんて伝えてみたところ、「そういうときは、知らないふりをしろ!」と、こてんぱに怒られたのだ。
俺もなんだかイラっときて、まさかのケンカに発展するしまつ。
タクマは一人おろおろしてたっけ。
「俺、トキと言い争いながらさ、「来年こそはあっと言わせてやるからな!」とかなんとか口にしてたんだよな。今でこそ笑えるが、そのときは、サプライズ失敗したのがよっぽど悔しかったからさ」
ルキトは、そう言ってコーラを一気飲みした。
「ああ! たしか、そんなやりとりした気がする」
俺が言った。
「それで、その言葉に、お前、なんて返したか覚えてるか?」
俺は、一年前の記憶を引っ張り出そうと、うんうん唸《うな》る。
「あ……」
「思い出した?」
タクマがにんまりとした笑みを浮かべた。
たしか、俺はこんなことを言ったのだった。
「ふん! 来年こそはバレずにサプライズ? それ、今言ってる時点でアウトだろ! やれるもんなら、やってみろ。 一年後の約束だからな! 絶対覚えてろよ」
……そうだった。
あの日の約束は、まぎれもなく、俺がけしかけたものだったのだ。
「う……くそう!」
なんとなく居心地が悪くなり、俺は目の前にピザに大きくかぶりついた。
完