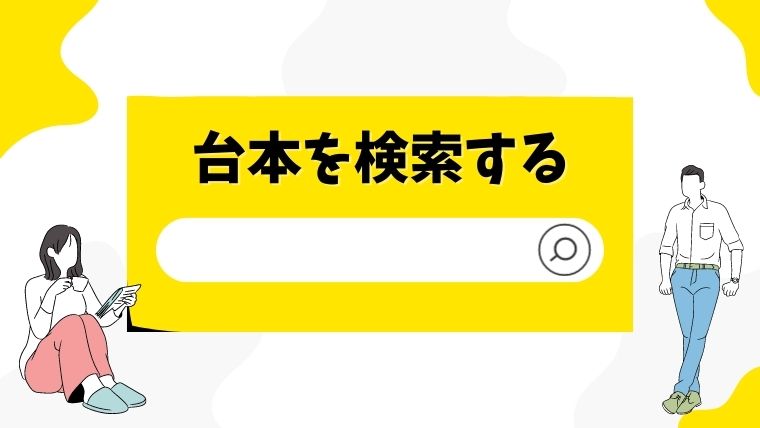●使用料:無料
●利用報告:商用のみ要(非商用は任意)
●クレジット表記:必須
ー表記内容ー
| 台本名 | 当ページのタイトル |
| 作者名 | 紺乃未色(こんのみいろ) |
| サイト名 | フリー台本サイト「キャラコエ」 |
| 台本URL | 当ページのURL
※リンク付け(URLをクリックすると、当ページに飛ぶように設定すること)必須 |
上記4点を必ず表記していただきますよう、お願いいたします。
利用のルールについては、利用規約をご覧くださいませ。
ずっと温めていた短編小説です。
フリー台本として当サイトに載せようか、ずっと迷っていたのですが、思い切って公開!
みなさまの、声の活動のお役に立てましたら嬉しいです。
※基本的にロボット視点。⑥⑨⑩のみ第三者視点です。
(視点切り替えがあるので、場面が変わったことを聞き手に伝えるのが難しいかもしれません。
間で表現するか、トーンを変えるか、、、朗読してくださる方の表現にお任せします)
概要
| カテゴリ | 朗読(一人) |
|---|---|
| ジャンル | SF・ファンタジー |
| 時間(目安) | 45分~60分 |
| あらすじ | 「僕は昔、ネコガタのロボットだったらしい」 人工人間のなかに埋め込まれたパーツ。それは、遠い昔の映像を記憶していた。 |
| 注意 | このストーリーはフィクションです。実在する人物や団体、出来事などとは一切関係がありません。 |
その他、朗読におすすめの台本は、以下のページにまとめています。

フリー台本『追憶のメモリーパーツ』
1
最近、よく夢を見る。
巨大《きょだい》な鉄のタケノコみたいにぐんぐん伸びる建物《たてもの》を、ただ眺《なが》めている夢だ。
僕はネコガタのロボットで、小枝《こえだ》のように細く、温かな腕に抱き抱えられている。
「六百三十四メートルになるらしいよ」
少女が言った。
僕はこの声が好きだ。
聞いていると、まるで、直射日光《ちょくしゃにっこう》の当たらない風通《かぜとお》しの良い場所でまどろんでいるような気分になる。
本当はいつまでも、ずっと、耳を澄《す》ましていたいけれど、そうはいかない。
どこからかピアノの音が流れてくるからだ。
「あ、帰らなきゃ。カラスが鳴くから、帰らなきゃ」
少女は歌うように言葉を紡《つむ》ぐ。
僕はボディを「ギギッ」ときしませた。
本当は「うん」と返事をしたかったのだけれど、それは叶《かな》わなかった。
2
僕のカラダにつまっているのは、ぬくもりある血《ち》や、ドクドク動くシンゾウなんかじゃない。
ただの無機質《むきしつ》な部品だけだ。
だから、人間のように夢を見るなんてこと、あるわけがないのだ。
そう自分に言い聞かせながら、見慣れた道を歩いていると、突然、激しい怒鳴《どな》り声と、ゴンッというドラム缶を殴《なぐ》るような音が聞こえてきた。
「もう、帰ってこなくていいからな!」
男の低い声だ。
僕は我《われ》に返った。
すぐに、そばをずんぐりむっくりとした男性が通り過ぎていく。
アルコール(たぶん、ウイスキーだ)の残《のこ》り香《が》が【不快《ふかい》】だと思った。
なにごとだろうと考え、まがり角《かど》を左に進むと、僕と同種《どうしゅ》の人工人間《じんこうにんげん》が灰色のコンクリートに両手をついてうずくまっていた。
「立てる?」
僕は手を伸ばした。
「ありがとう」
彼女の顔はいびつに歪《ゆが》んでいる。
いや、正確にはへこんでいた。
「大丈夫?」
「ええ。殴《なぐ》られるのはこれで六十三回目。早く部品を交換しないと、明日の仕事に支障《ししょう》が出てしまうわ」
その口ぶりは、まるで「トイレットペーパーの|芯《しん》をとりかえなくてはいけない」といった感じだった。
「それよりも、君はもっと休んだ方が良い気がする」
僕が言うと、彼女は首をかしげた。
「何を言っているの? 休みなんて必要ないわ。だって、ロボットだもの。あなただってそうでしょう?」
彼女の言うことはもっともだった。
「……君のことが心配なんだ」
「ありがとう。だけど、問題ないから大丈夫よ。私は働かなくてはならないの。もっとたくさん」
僕は「そう」と短く返す。
もう、なにも言わないことにした。
ただ、「彼女を形成《けいせい》するパーツが、これ以上、悲鳴《ひめい》を上げることがなければいい」とひっそり思った。
3
女性型人工人間の背中を見送ったあと、僕は鉛《なまり》をひきずるような重さを感じながら、目的地へと向かっていた。
体がとてつもなくだるい。
すべてを投げ出したくなってしまう。
油が足りなくて上手く動けないときの感じ……。
いや、違う。
似てはいるけれど、しっくりとこない。
僕は、不調の原因を探ろうと、ノウミソの中枢《ちゅうすう》をフル稼働《かどう》させた。
「わからない」
結局《けっきょく》、良い回答はちっとも思いつかなかった。
「おいおい。シオンじゃねえか。こーんなところで油売ってるなら、もっと稼《かせ》いでこいっつーの」
「あらあら? お仕事は?」
正直、今、一番会いたくない人たちだ。
僕の主でもある水沢隆介《りゅうすけ》と水沢里奈《りな》は、両手に高級ブランドのロゴが大きく描かれた紙袋を握っている。
つりあがった四つの目が僕を睨《にら》みつけていた。
「あ、はい。これからホームセンターへ」
僕が答えると、隆介《りゅうすけ》はあからさまに眉間《みけん》のシワを深めた。
「お前、まだあんな時給安いところで品出しのバイトでもしてんのか?」
「あなた、無駄《むだ》にルックスは良いんだから、もっとほかにもあるでしょう?」
隆介《りゅうすけ》と里奈《りな》は順番に言った。
「えっと……。そういう仕事は、今探しているところで」
僕は切れの悪い言葉を返す。
「まあ、いいさ。たくさん働いてがっぽり金を持って帰ってこいよ。それが、お前の役割なんだからな」
「そうよ。期待してるわ」
二人はケラケラ、クスクスと笑いながらその場を去っていく。
空はほんのりと赤く染まり、一匹のカラスが遠くを飛んでいる。
どこからか、あの音が流れてきた。
僕は小さく口ずさんだ。
夢の中で何度か聞いたことがある。
残念ながら、歌詞の一部分《いちぶぶん》しかわからないけれど、僕はずっと遠い昔から、この曲を知っているような気がしている。
ただの思い込みかもしれない。
でも、このメロディを聞いていると、あるはずのないココロが、ほんのりと温かくなるような感覚に包まれるんだ。
そのことだけはゆるぎない事実《じじつ》だった。
「ああ、帰りたい」
僕は知らぬうちにそう口にしていた。
もちろん、あの主人たちが待つ家にではない。
一体、どこに帰りたいのか、それは自分でもわからなかった。
4
「よう。シオン、元気か?」
騒《さわ》がしい音が鳴り響く工場内《こうじょうない》。
人間用の休憩時間《きゅうけいじかん》に大声でそう言ったのは、工場長の源次郎《げんじろう》さんだ。
「はい。おかげさまで」
年齢は四十八歳と聞いたことがある。
妻と息子の三人家族で、今は|単身赴任《たんしんふにん》をしているらしい。
源次郎《げんじろう》さんは、白い歯を見せながら、「おう。それはよかった」と言ってげらげら笑った。
半袖《はんそで》の作業着《さぎょうぎ》から伸びる腕《うで》には浮き出た血管。
ついさっきまで、ロボットにはできない、なにかしらの力仕事をしていたことを物語っている。
「今日も午後から別の仕事か?」
僕は「はい」と答える。
「そうか。がんばれよ」
源次郎《げんじろう》さんは、僕の世界のなかでは、あまり人間らしくない部類《ぶるい》に入る。
まったく異なる雰囲気ではあるけれど、夢で見る少女に近いような……。
そんなことを考えていると、ふと、あのメロディが蘇《よみがえ》ってきた。
「おい。シオン? どうした?」
源次郎《げんじろう》さんが顔の前でごつごつとした手を振った。
「源次郎《げんじろう》さん「夕焼け色に染《そ》まる空、カラス鳴いたら、帰り路《じ》へ」って曲を知っていますか?」
「ん? あの夕方に流れてくるやつだな。たしか『夕《ゆう》べに染《そ》まる空』って曲名だったと思うぞ」
僕は「夕《ゆう》べに染《そ》まる空」と繰り返す。
脳裏《のうり》にちらついたのは夢でみた光景だ。
「ああ。その曲がどうかしたのか?」
「僕、この曲をずっと前に聞いたことがあるんです」
「そりゃあな。毎日、毎日、鳴ってるからな」
「えっと……。もっと、もっと、昔から知っているような気がするんです」
源次郎《げんじろう》さんは、片手を顎《あご》に添《そ》えて視線を床に落とした。
「……」
源次郎《げんじろう》さんは何も言わない。
機械《きかい》が動く規則正《きそくただ》しい音がやけに大きく感じられた。
なにか言葉を発した方が良いのだろうか、と考える。
「そういやな……」
先に沈黙《ちんもく》を破《やぶ》ったのは源次郎《げんじろう》さんだ。
「部品《ぶひん》が記憶《きおく》を覚えていることがあるそうだ」
僕が「部品が記憶を?」と復唱すると、源次郎《げんじろう》さんは「ああ」と頷いた。
「もっと、詳しく知りたいです」
「元々、ロボットや機械には心ってもんはない。そういう風に作られているからな。まあ、その方が人間に都合《つごう》がいいからってのもあるんだろうが……。
だけどな、何度もリサイクルされた部品《ぶひん》の欠片《かけら》が、まれに感情を抱《いだ》くことがあるそうだ」
「感情……」
僕はそっと自身のカラダに触れた。
人間であればシンゾウがあるところだ。
「どういうわけか、喜怒哀楽《きどあいらく》を覚えちまうらしい。そんでもって記憶もまた然《しか》り。たまに前世《ぜんせ》のことを覚えている人間がいるだろう。それと同じ感じだ」
源次郎《げんじろう》さんはそう言った。
僕の脳内《のうない》に知らぬ街の映像が浮かんでくる。
「このタワーができあがったら、一緒に見にこようね」
大好きな声で少女が言った。
彼女の足元では、ひまわりがゆったりと花びらを広げている。
これまでの夢では見ることがなかったシーンだ。
ネコガタロボットの僕は「ニャ」とマニュアル通りの音を発して、目をちかちかと光らせる。
本当は「もちろん」と言いたかったけど、やっぱり無理だった。
「おーい。シオン、戻ってこい」
源次郎《げんじろう》さんが僕の肩を叩く。
「あっ。すみません」
「いや、いいけどよ。大丈夫か?」
源次郎《げんじろう》さんの真っ黒な瞳がこちらへと向けられている。
「はい。何かを思い出したような気がしました」
「ひょっとして、生まれる前の記憶《きおく》、か?」
「おそらく。きっと昔の話です」
「……そうか」
源次郎《げんじろう》さん、と僕は名を呼んだ。
「ん? なんだ?」
「あなたの他にも素敵な人間がいるのかもしれません」
僕はそう言ってから、笑顔を作ってみせた。
「なっ。俺はな、そんなんじゃねえよ」
源次郎《げんじろう》さんの頬《ほお》が赤く変化した。
その色は僕に夕暮れの空を連想《れんそう》させる。
「なに、笑ってやがんだ? 変な奴《やつ》」
「いや、なにも。……源次郎さん」
「ん?」
源次郎《げんじろう》さんが首を傾げる。
「また、会えるでしょうか?」
「……ああ。姿かたちは変わっているかもしれんが、きっと会えるさ」
彼は僕が何を言いたいのか、悟《さと》ってくれたのかもしれない。
「少しだけ、生かされるのが楽しくなりました」
源次郎《げんじろう》さんは目尻を下げた。
それから、なにも言わずに大きく頷いた。
「今はまだ鉄の塊《かたまり》だが、こいつらも大切に扱ってやらねえとな」
彼はレーンの上を流れている部品をそっと手に取った。
5
「あ! 居た。源次郎《げんじろう》さん」
若手作業員《わかてさぎょういん》の声が響き渡る。
マシンの重大なオイル漏《も》れが発覚《はっかく》したときみたいな慌《あわ》ただしさだ。
彼も源次郎《げんじろう》さんと同じく人間労働者の一人。
現代においては、数少ない類《たぐい》である。
「どうした?」
源次郎《げんじろう》さんが尋ねる。
「その……。ユキが仕事辞《や》めたいって」
「なんだと? 昨日までは仕事に対してかなり前向きだったぞ」
ユキは僕と同期《どうき》の人工人間《じんこうにんげん》だ。
ほぼ同じタイミングに製造《せいぞう》された。
精密《せいみつ》な計算を得意とする彼女は、この工場になくてはならない大切な存在だ。
「なんでも、家族から他の仕事を勧《すす》められてるみたいで……」
「なぜだ?」
「最近、宇宙旅行が流行ってるでしょう。それに参加したいらしくて、お金が必要なんだそうです」
先日、主人と交わしたやりとりを思い出す。どの家も似たような状況らしい。
「はあ? ロボットを極限《きょくげん》まで働かせてその金で宇宙に遊びに行くだあ? ふざけんな」
その声があまりにも響いたからだろう。
まわりの視線が一気に源次郎《げんじろう》さんへと集まった。
「落ち着いて下さい!」
若手作業員《わかてさぎょういん》が言った。
「これが落ち着いてなんかいられるか! 胸糞悪《むなくそわる》い」
「気持ちはわかります。ただ、あなたは必要以上にロボットへ感情移入《かんじょういにゅう》する傾向があります。立場をわきまえてください。工場長、皆が見ていますから」
「……ああ、すまない。ついカッとした」
源次郎《げんじろう》はそう言って、荒《あら》い呼吸を繰《く》り返す。
「どうしましょうか?」
「あとで直接話してみる。まあ、家族の問題だからな。俺が止めることはできないだろうが」
源次郎《げんじろう》さんは鋭《するど》い視線でどこかを睨《にら》みつけていた。
6(第三者視点)
「やーい、変人」
子供の頃、源次郎《げんじろう》はよく消しゴムのカスを投げつけられていた。
ときには紙飛行機《かみひこうき》やどんぐり、小石のときもある。
ときおり、源次郎《げんじろう》は彼らを思いっきり睨んだものの、当時、体が小さいせいもあってか、相手はまったく怯《おび》えた様子を見せなかった。
「お前んとこのロボ、ポンコツだから働くことができないんだろ」
「名前がさ、ポンってところがまたウケるよな!」
「ていうか、父ちゃんも母ちゃんも働いてるなんて、家族全員、頭がおかしいんじゃないの」
「うわあ。変人がうつるから近づくなよ」
源次郎《げんじろう》へ飛んでくるのはモノだけじゃない。
頭のてっぺんから足先にまで、言葉という名の鋭《するど》い刃《やいば》が刺さっていく。
自分では抜き方がわからないものだから、刃は老廃物《ろうはいぶつ》となり、みるみるうちに源次郎《げんじろう》の体内に溜《た》まっていった。
「そのうち、お腹がぱんぱんになって、口からナイフが飛び出してしまいそう」
源次郎《げんじろう》は冗談なんかではなく、真剣《しんけん》にそう思っていた。
そもそもの話、ポンは働くために源次郎《げんじろう》の家へ来たわけではなかった。
「外遊びが好きだなんて変わってる」
そんな、意味のわからない理由でハブられて、友達がいない源次郎《げんじろう》のために、両親が手配《てはい》してくれたのだ。
しかし、源次郎《げんじろう》はポンに興味を持たなかった。
一人で虫を追いかけ、一人で空き地に秘密基地《ひみつきち》を作り、一人で図鑑《ずかん》を眺めた。
結局、ポンは家事をこなしながら、源次郎《げんじろう》の両親をサポートする日々を送ることになったのだ。
ある日のことだった。
「おかえりなさい」と声を掛けてくるポンを、源次郎《げんじろう》は無視して睨《にら》みつけた。
「お前のせいだ! いつも、苛《いじ》められるのは」
ポンはその場で静止した。
源次郎《げんじろう》はダメだとわかっていながらも、自身を抑えることができなかった。
「お前なんて……。お前なんて、家にこなければよかった」
ポンは言葉を返さない。
その様子に腹が立ち、源次郎《げんじろう》は彼の首あたりへめがけて、思いっきり拳《こぶし》を突き付けた。
「グウ……」
ポンは|唸《うな》り声を発した後「シューン」と言った。
コンピューターが起動終了《きどうしゅうりょう》する時の音だ。
それから、まったく「動《どう》」を感じさせなくなってしまった。
まるで、生物が「死」を迎えた瞬間《しゅんかん》みたいに。
このときの光景は、トラウマとなり源次郎《げんじろう》の脳裏《のうり》にこびりついている。
その|証拠《しょうこ》に、源次郎《げんじろう》はいまだにコンピューターのシャットダウン音を好きになれない。
「お前が悪い!」
源次郎《げんじろう》はポンを殴《なぐ》った後、叫びながら部屋へと飛び込んだ。
うっかり人を殺してしまった罪人《ざいにん》のように、ベッドの上で毛布《もうふ》を|被《かぶ》り目を瞑《つむ》る。
気が付くと、源次郎《げんじろう》は夢を見ていた。
源次郎《げんじろう》が捕まえた自慢《じまん》のカブトムシにゼリーを与えているポン。
眠っている源次郎《げんじろう》にブランケットを掛けるポン。
親とケンカしている|源次郎《げんじろう》を見守っているポン。
ああ、いつもかたわらには彼がいたんだ。
「源次郎《げんじろう》、起きなさい」
父の声に意識が戻る。
源次郎《げんじろう》の視界に入ってきたのは、両親の姿。
そして、いつもと変わらないポンの茶色い瞳《ひとみ》だった。
「もう、こんなこと、二度とするんじゃないよ。あとで、ちゃんと理由を話してもらうからな」
父が言った。
「え、ポン? どうして? 壊したのに」
源次郎《げんじろう》が尋ねると、父は大きくため息を吐いた。
「まったく……。プログラムの一部が破損《はそん》していて、直すのに手間取《てまど》ったぞ」
ポン、と弱弱《よわよわ》しい口調《くちょう》で名を呼ぶと、彼は一言「はい」と答える。
源次郎《げんじろう》はポンの腹の部分に抱きついた。
それから何度も「ごめん」を繰り返した。
「問題ございません」
ポンはいつもと同じように淡々《たんたん》と言った。
7(ロボット視点に戻る)
僕は体内《たいない》の部品が足りない感覚《かんかく》に苛《さいな》まれている。
ぽっかりと大きな空洞《くうどう》ができてしまったみたいだ。
とうとう、ユキの姿を見なくなってから三日が過ぎた。
もう、戻ってはこないだろう。
「おい、シオン」
背後から源次郎《げんじろう》さんの声がした。
僕は振り返る。
「もし……。もしもの話だ。お前が人間どもをどうにかしてやりたいって思ったら、俺に協力させてくれ」
「……どうしたんですか? 突然《とつぜん》」
「急なことじゃねえ。ずっと考えてたさ。もっと……ロボットと人間が協力して一緒に過ごせる世の中にするには、どうすれば良いんだろうってな」
僕はじっと彼を見た。
「ようやく、目が覚めた。無理だ。今の人間はもう、心が腐《くさ》っちまってる。たとえ、相棒《あいぼう》を失《うしな》ったとしても、なんとも思いはしないだろうな。どっちが人工的《じんこうてき》なんだって話だ」
彼の|額《ひたい》には大粒の汗が滲《にじ》んでいた。
「源次郎《げんじろう》さん……。これ、使ってください」
僕は彼に白いタオルを手渡した。
「ああ。ありがとうな」
「僕は……。僕たちは、人に危害《きがい》を加《くわ》えることはできません」
「そうだったな。まあ、だからこそ力になりたいわけだが……」
すべてのロボットは、絶対的《ぜったいてき》な主《あるじ》である人間に|逆《さか》らうことができないようにプログラミングされている。
「あなたに危険な目にあってほしくない。だから、言葉だけで嬉しいんです」
それは僕の本意であった。
「その言葉に救われるよ。……シオン、また明日な。これ、洗って返すからな」
彼はタオルを空中でばさばさ振りながら言った。
8
源次郎《げんじろう》さんと別れた後、僕は小汚《こぎたな》い男が女性型の人工人間《じんこうにんげん》に暴力を奮《ふる》っている場面を目撃《もくげき》した。
鉄骨《てっこつ》を叩くような乾《かわ》いた音が、路地裏《ろじうら》の風を震わせている。
「止めて下さい!」
体が勝手に動いた。
「ああ? お前、誰だよ」
アルコールの匂いがする。
僕は体内に広がる黒いモヤの正体《しょうたい》が理解できた。
これは【怒り】だ。
「なぜ、殴《なぐ》る?」
僕は淡々《たんたん》と言った。
「ああ? こいつの稼《かせ》ぎが少ないからに決まってるだろう」
男は吐《は》き捨てるように口にする。
あるはずのないハラワタが、ふつふつと煮《に》えくり返る気がした。
「……どうして、お前ら人間が遊ぶために、働かなくてはならないんだ」
中年の男は「はあ?」と素《す》っ頓狂《とんきょう》な声を上げた後、くっくっと喉《のど》を鳴らした。
「なにがおかしい?」
僕は男を睨《にら》みつけた。
「はっ。おかしいったらありゃしないさ。仕事がなければお前らなんて存在《そんざい》する意味すらねえからな。そもそも生まれてないって話だ。それが、「どうして働かなくてはならないんだ?」って? 違うぞ、違う。俺らはお前らに働かせてやってんだ」
男がぐいっと顔を近づけてきて、目をくわっと開いた。
理解したか? そう尋《たず》ねるように。
気付いたときには、僕の十本《じゅっぽん》の指が男の首を掴《つか》んでいた。
ガラン、とまぬけな音が鳴った。
男が手にしていた酒の瓶《びん》がコンクリートに当たった音だ。
「はっ。てめえ、なにしやがる」
男は苦しそうではあるが、どこか余裕《よゆう》さえ感じられる表情をしていた。
「僕は……。働くために生まれた。わかってる、そんなことは」
首を掴む手にぐっと力を込める。
男に主人の姿が重なった。
彼らのために働いて、稼《かせ》いで、一体自分はなにをしているのだろうか。
そんな疑問に蓋《ふた》をして、やり過ごそうとしていた。
「うっ。い、いの、か?」
男は顔に冷や汗を滲《にじ》ませつつもにやりと笑った。
「だめよ! そんなことしたらあなたが……。お願いだから止めて!」
女性型の人工人間《じんこうにんげん》が叫ぶように言った。
きんきんとした声が脳に響く。
だけれど、僕は止まらなかった。
十本の指がさらに男の喉元《のどもと》に食い込む。
「うっ」
男が呻《うめ》いた。
『自動爆破装置起動《じどうばくはそうちきどう》。自動爆破装置起動。
内部爆破《ないぶばくは》、三十秒前。ただちに三メートル以上離れて下さい』
僕の体内から機械的《きかいてき》なアナウンスが流れる。
それから、すぐにカラダがまったく動かなくなった。
「だから言ってやったのに。どうだ、気分は?」
男は勝ち誇《ほこ》ったように目を細めた。
僕の手から抜け出して、首をゆっくりと左右に傾ける。
彼の骨がばきばきと鳴った。
『内部爆破《ないぶばくは》、二十五秒前。内部爆破《ないぶばくは》、二十秒前。ただちに三メートル以上離れて下さい』
「ふん。もう会話もできないか。ほら、行くぞ」
男は女性型人工人間《じんこうにんげん》の腕を掴み、引きずるようにして去って行った。
僕は十本の指を宙《ちゅう》に掲《かか》げたまま、前方《ぜんぽう》を見つめることしかできない。
「もしも、お前がさ、人間どもをどうにかしてやりたいって思ったら、俺に協力させてくれ」
源次郎《げんじろう》の言葉が蘇《よみがえ》る。
【人に危害《きがい》を与える場合は内部爆破《ないぶばくは》する】
そんな原則《げんそく》に縛《しば》られることのない彼に頼《たよ》るべきだったのだろうか。
「ゲン、ジ、ロウさん」
僕はとぎれとぎれに彼の名を呼んでいた。
視界《しかい》いっぱいに広がるのは、赤色に滲《にじ》む空と十本の無機質《むきしつ》な指。
遠くの方には鳥《とり》の|影《かげ》がふたつ見えた。
どこからか、あのメロディが流れてくる。
「ユウヤケイロニ、ソマルソラ、カラス、ナイタラ、カエリジエ……」
僕は動力《どうりょく》を振り絞《しぼ》って、懐《なつ》かしいフレーズを紡《つむ》いだ。
『内部爆破《ないぶばくは》、十秒前。九、八、七……』
多分……僕は、この光景を知っている。
中途半端《ちゅうとはんぱ》に浮いた十本の指も、体内《たいない》から発せられるアナウンスも、全部、全部、覚えている。
きっと、この瞬間《しゅんかん》を、何度も、何度も、経験している。
……ああ、彼女に会いたい。
次こそは必ず……。
いつか、彼女の元で過ごしたい。
ある日の源次郎《げんじろう》さんの言葉が頭に浮かんだ。
「部品が記憶《きおく》を覚えていることがあるそうだ」
もしも本当ならば……。どうか……。
僕は、全身のパーツが熱くなるほどに、強く願った。
『爆破《ばくは》』
シャットアウトする直前に聞こえたのは、「ぼふん」という爆発《ばくはつ》にしてはやけに地味《じみ》な音だった。
9(第三者視点)
男は「無菌《むきん》」という言葉が恐《おそ》ろしいほどに似合う、白い空間でぼうっと天井を眺《なが》めていた。
「お体拭きますねー」
三十代半《なか》ばの看護師《かんごし》が声を掛けると、小さく頷《うなず》いて反応を返す。
先程から、その繰り返した。
彼女のかたわらでは、介護用《かいごよう》ロボットが男の体を支えている。
「今日はね、空が綺麗なんですよ。びっくりするくらいにオレンジ色なんです」
看護師は朗《ほが》らかな口調《くちょう》で言った。
男の視線が窓の方へと移動する。
「私、夕焼けを見ると、なぜだか頭の中にスカイツリーが思い浮かぶんですよ」
介護用《かいごよう》ロボットが動きを止めて、看護師を見た。
「多分、小さい頃の記憶だと思うんです。まだ、建設途中《けんせつとちゅう》だったときによく見てたんですよね」
男は一言も言葉を返さない。
看護師はそんな彼を気にすることなく一方的《いっぽうてき》に話を続ける。
「それから、音楽も流れてくるんです。あ、知ってますか? 『夕《ゆう》べに染《そ》まる空』っていうんですけど」
男は掠《かす》れた声で「ああ」と言った。
「昔は切ない曲だって思ってたんです。なんだか、一日が永遠《えいえん》に終わってしまうみたいで。だけど、大人になってから二番を知ったんです。……ねえ、あなた、歌詞知ってる?」
介護用《かいごよう》ロボットは少しの間の後、口を開いた。
「二番。いいえ。わかりません」
「二番は『空が藍色《あいいろ》に変わったら、星屑《ほしくず》が風に揺れて、もうすぐ朝がくる』みたいな感じなんですよ」
そこまで言うと、彼女は「ふふっ」と笑った。
そして、言葉を続ける。
「一日はまだ終わってなかったんです。夜には夜の世界があって、それから、また朝が来るんです……。そうやって、ずーっと毎日が続いてるんだって知ったときに、私、ほっとしたんですよね」
男はゆっくりと頷《うなず》いた。
「一度、友人にこの話をしたことがあるんですけど、笑われちゃいました」
看護師は屈《かが》み込み、男と視線を合わせた。
「あなたも笑って呆《あき》れますか? 源次郎《げんじろう》さん」
男が「いいや」と言葉を発すると、看護師はにっこりと笑った。
「あっ」
介護用《かいごよう》ロボットが声を上げた。
どこからともなく『夕《ゆう》べに染《そ》まる空』のメロディが流れてきたからだ。
「夕焼け色に 染《そ》まる空 カラス鳴いたら 帰り路《じ》へ
沈《しず》む太陽 ゆるやかに 微笑《ほほえ》み さよなら 告げている
たそがれ どきに 背を向けて 小路《こみち》 鳴らして 家につく」
看護師は囁《ささや》くように歌詞を口ずさむ。
男はそっと目を閉じて彼女の歌声に集中した。
メロディが二番に差し掛かる。
「あ、おじいちゃん!」
病室の入り口で甲高《かんだか》い子どもの声がした。
そこにいたのは二人の大人と一人の子ども。
そして、一体の人工人間《じんこうにんげん》だった。
「父さん、調子《ちょうし》はどう?」
息子らしき人物に声を掛けられた源次郎《げんじろう》は、「いい」と短く口にした。
近くにいた少年は、ぱっと顔を綻《ほころ》ばせた。
「よかった! あのね、新しい家族が増《ふ》えたんだよ。今、名前を考えてるところなの。ほら、僕のおじいちゃんだよ」
少年はそう言って、人工人間《じんこうにんげん》の方へと視線をやった。
「源次郎《げんじろう》さんですね。はじめまして」
人工人間《じんこうにんげん》が挨拶《あいさつ》をする。
その瞬間、源次郎《げんじろう》の目から水滴《すいてき》が溢れ出した。
「父さん? どこか具合が悪いのか?」
源次郎《げんじろう》は首を振った。
「おじいちゃん。どうしたのー?」
少年は棚《たな》に掛けられていた白いタオルを手に取り、源次郎《げんじろう》の目元を拭《ぬぐ》おうとしている。
その布は何年も使われていたらしく、ボロボロにほつれていた。
「……ポン」
源次郎《げんじろう》が呟く。
少年は「え?」と言って、きょとんと首を傾げた。
「ポン」
先程よりもはっきりとした声で源次郎《げんじろう》が言った。
人工人間《じんこうにんげん》の目が少しだけ見開く。
「あ。もしかして名前のこと? うん。いいね。ポンにするよ。よかったね。名前が決まって」
少年はマイペースに言葉を紡《つむ》ぐ。
「はい。素敵です。源次郎《げんじろう》さん、ありがとうございます」
ポンと名付けられた人工人間《じんこうにんげん》は淡々《たんたん》と言った。
「気に入ったー?」
「はい。……なんだか、とても懐《なつか》かしい響きがします」
ポンはそう言うと、茶色い瞳で源次郎を見つめた。
10(第三者視点)
数日後、介護《かいご》ロボットはふいに看護師《かんごし》へと声を掛けた。
「源次郎《げんじろう》さん、素敵な方でしたね」
いつも、私語《しご》を慎《つつし》んでいる彼にしては珍《めずら》しい行動だった。
「ええ。そうね、なんだか大きな山みたいな方だったわ。近くにいると、見守られてるような感じがしたもの」
看護師が言った。
「僕、源次郎《げんじろう》さんとのお別れは、なぜか【切ない】が激しくて戸惑《とまど》ってます」
「ええ。気持ちはわかるわ。……あら? あなた、泣いてるの?」
介護用ロボットははっとした表情になる。
「いいえ。……オイルが漏《も》れたんですね。処理《しょり》してきます」
「あら、大変。今はどこも落ち着いているから、ゆっくりで大丈夫よ」
「ありがとうございます」
彼はそう言って、くるりと女性に背を向けた。
看護師の女性は少し首を|傾《かし》げたあと、小さく口を開いた。
「ねえ……」
介護ロボットが振り向いて「なんでしょうか?」と尋ねる。
「へんなこと言うようで悪いんだけど……。源次郎《げんじろう》さんのこと思い出したら、久しぶりにスカイツリーが見たくなっちゃった。
……もし、よかったら、帰りに付き合ってくれないかしら?」
介護用ロボットは看護師を見つめた。
その目元はテカテカに塗《ぬ》れたままだ。
「はい。もちろんです」
彼の返答は「ギギッ」でも「ニャ」でもない。
夕日に染《そ》まるひまわりのような、温かく慈愛《じあい》に満ちた声音《こわいろ》だった。
完
資料:小説に登場する歌詞
夕べに染まる空 作詞:紺乃未色
1.
夕焼け色に 染まる空
カラス鳴いたら 帰り路へ
沈む太陽 ゆるやかに
微笑み さよなら 告げている
たそがれ どきに 背を向けて
小路(こみち) 鳴らして 家につく
2.
夕焼け空が 藍色に
いちばん星が ごあいさつ
星屑揺らす 空の風
輝く 三日月 にこやかに
もうすぐ 明日(あす)が やってくる
今は しばらく 夜の闇