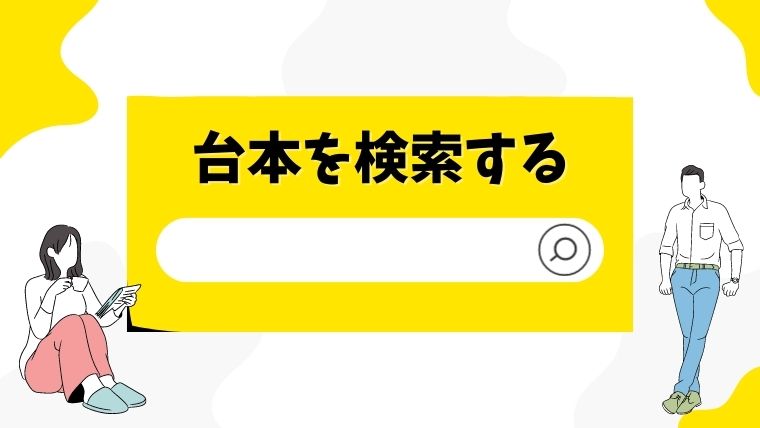●使用料:無料
●利用報告:商用のみ要(非商用は任意)
●クレジット表記:必須
ー表記内容ー
| 台本名 | 当ページのタイトル |
| 作者名 | 紺乃未色(こんのみいろ) |
| サイト名 | フリー台本サイト「キャラコエ」 |
| 台本URL | 当ページのURL
※リンク付け(URLをクリックすると、当ページに飛ぶように設定すること)必須 |
上記4点を必ず表記していただきますよう、お願いいたします。
利用のルールについては、利用規約をご覧くださいませ。
概要
| カテゴリ | 朗読(一人) |
|---|---|
| ジャンル | 現実世界 |
| 時間(目安) | 10分~15分 |
| あらすじ | 新しいアルバイトスタッフとしてやってきた佐々木トモカ。 彼女によると、僕とは遠い昔に会ったことがあるらしい |
| 注意 | このストーリーはフィクションです。実在する人物や団体、出来事などとは一切関係がありません。 |
その他、朗読におすすめの台本は、以下のページにまとめています。

フリー台本『戯れの運命』
その人は、ファミリーレストランの新人アルバイト「佐々木トモカ」として僕の前にあらわれた。
「楓真(ふうま)くん、また会えたね」
そう声をかけてきたのは、休憩時間中、スタッフルームのイスに座っていたときのことだった。
「え?」
「ふふ」
彼女は真正面から、僕の目をじっとみて、ほほ笑んでいる。
「えっと……」
その甘ったるい笑顔に耐え切れず、視線を逸らす。
壁にかけられたカレンダーのなかでは、クマのキャラクターが笑っている。
「あんた、佐々木トモカのことが好きなのか?」
そう、からかわれたような気がした。
違う。ちょっとだけ、可愛いかもって思っただけだ。
「えっと……。ごめん。わかんないけど、ひょっとして同じ大学?」
そうだったらいいな。
たぶん、心のどこかで願っていた。
「ううん」
佐々木トモカは首を振る。
僕はがっかりした。
「じゃあ、どこで?」
「……あのとき、私はイギリスのお屋敷に住んでいて、楓真(ふうま)くんはそこの庭師をしていたの」
彼女の言葉を聞いたとたん、僕の頭のなかには、いくつもの薔薇の花びらが舞い散った……。
なんてことがあるわけもなく、ただぽかんと口をあけることしかできない。
「ねえ、聞いてる?」
「あ、うん。あのさ、それっていつの話?」
「ええっと、二百年くらい前だと思うわ」
「まだ、生まれてないよ」
「そりゃそうよ。ああ、そのあと、何度か会ったこともあるのよ。……聞きたい?」
「うん」
「あるときはねえ、私はホトトギス、楓真(ふうま)くんは橘(たちばな)の花だったわ。せっかく会えたっていうのに、あなたったら、うんともすんともいわないし、あげくのはてにどこかに吹き飛ばされてしまうし、さんざんだったわ」
佐々木トモカは、口を尖(とが)らせた。
「それは、ごめん」
まったく心当たりもないことを、僕は謝る。
「あ! それから、楓真(ふうま)くんが黄金のススキだったこともあるわ。夕陽を背景にして、風にゆらゆら揺れている姿がとても美しかったの」
佐々木トモカはうっとりとした口調で言った。
「そのとき、佐々木さんは?」
「私は赤とんぼ。ちょうど、今くらいの季節だったわ。お友達と一緒に草原を飛んでいたら、偶然あなたのことを見つけたの」
「それで、どうなったの?」
「声をかけようとしたら、すぐにヤギに食べられてしまったわ」
「ヤギに……。そう」
僕はとうとうなんと返していいのかわからなくなった。
「わかったでしょう? ずっとすれ違っていたの。でも、やっと会えた。お互い大学生で、おんなじアルバイト先。わたし、とっても嬉しいの」
佐々木トモカは、そう言って笑うと、自然な流れで小さな鞄(かばん)をたぐりよせた。
僕もつられるように、リュックサックのジッパーをあけ、そのなかに手を突っ込む。
二人は同時にスマートフォンをひっぱりだし、そうなるのが当然とでもいうかのように、連絡先を交換した。
佐々木トモカはメッセージをくれるだけでなく、ことあるごとに、話しかけてきた。
休憩中はもちろんのこと、お客さんが少ないちょっとした時間帯や、バイト終わりのタイミングなんかも。
悪い気はしなかった。
その……。わりとタイプだから。
でも、話の内容は、相変わらずぶっとんでいる。
バイト仲間たちからは、憐(あわ)れむような目で見られるしまつだ。
「佐々木さん、新人のわりに仕事はできるけどさ、なんか、頭のネジ外れてるよなあ。昔は、イギリスに住んでたんだってよ」
「ああ、俺も聞いた。楓真(ふうま)とはそのときに出会ったって話だろ? それで、今の世界でも再会できたって。本当なのか?」
みんなの視線がこちらに集合する。
「えっと、わかんない」
僕がおずおずと答えると、どっと笑い声が響く。
「そりゃそうだろ。でも、気をつけろよ。ずっとあんな話聞かされてたら、そのうち洗脳されるかもしれん」
「たしかに! 佐々木さん、楓真(ふうま)くんのこと好きなのかしら?」
「さあ? べつに興味ないし、害はないけどお、あたしはあんまり関わりたくはないかも」
彼らは口々にそんなことを言っていて、僕は「そりゃそうなるよな」とそのときは思っていたんだ。
それなのに、バイトからの帰り道、彼らの言葉を思い出すと、呼吸が荒くなり、歩くスピードがどんどん早くなった。
夕暮れのコンクリートを乱暴に踏みしめ、人混みにもかまうことなく、ずんずん進む。
周囲の笑い声や話し声がうっとうしくてたまらない。
それが、ふつふつと湧(わ)いてくる腹立たしさのせいだと気づいたとき、僕の足はぴたりと止まった。
「なんだ、腹立たしいって?」
一人、立ち止まり、呟(つぶや)く。
これじゃまるで、佐々木トモカのことを好きみたいじゃないか。
少し、休憩しよう。
ほてった体と頭を休ませなくては。
ちょうど目の前には、バーガーショップがあった。
窓ガラスに貼られた巨大ポスターのなかでは、目玉焼きとチーズをサンドしたバーガーが、どどんと存在感を放っている。
その背景には、うっすら光る満月と黄金の|絨毯《じゅうたん》があった。
「ススキ……」
僕は、そのポスターに吸い寄せられるようにして、店内へと足を踏み入れた。
さっさと注文を済ませて、トレイを持ち、一番奥の席へと向かう。
人は少ない。
これなら、四人掛けのソファ席を使っても文句はいわれないだろう。
腰を下ろすと、それまで感じなかった足の重みが伝わってくる。
「はあ」
バーガーが包まれている紙をたらたらとめくりながら、僕はため息を吐いた。
「佐々木トモカ」
小さく名を呼ぶと、胸の奥がざわめいた。
僕の魂(たましい)のなか、どこかにある引き出しが、カタカタと動いているみたいだ。
過去の記憶が、ここから出せと騒いでいるような気がした。
本当に、忘れてしまっているだけなのだろうか。
佐々木トモカのいうように、僕は、あるときは庭師で、あるときは橘(たちばな)の花で、あるときはススキだったのかもしれない。
それで、やっと今、大学生として彼女とまた会えたのだとしたら……。
なんて、ロマンチックな主人公なんだろう。
僕は、バーガーを両手で掴んだまま、そんなことを思った。
明日は佐々木トモカと休憩時間がかぶっていたはずだ。
もしも、タイミングがあえば、伝えてみようか。
僕も、ずっと君のことを探していたのかもって。
どんな顔をするだろう。
笑ってくれるだろうか。
「それでえ、どういう状況なわけ?」
突然、聞こえてきた甲高(かんだか)い声に、我に返る。
「そうそう! あたしたち、気になってたんだから!」
どうやら、同世代くらいの女性たちが、近くの席に座ったらしい。
さっきまでの静けさが一瞬でどこかへ吹き飛んで行く。
げんなりしたのは一瞬だった。
「ああ! 楓真(ふうま)くんのことね」
そのうちの一人が佐々木トモカだったからだ。
ふいに名が出てきたものだから、思わず身を小さくさせる。
彼女たちは、おそらく四人だ。
斜め後ろのソファ席にいるらしい。
「そう! アルバイト先の楓真(ふうま)くん。トモカの運命の人」
女性Aが言った。
僕は照れくさくなって、ひっそりと頬をかく。
「ふふふ。十三番目のね」
女性Bが付け加える。
「え?」と声を出したくなるのを堪える。
十三という妙な数字がひっかかる。
「もう! 今回は本物なんだから!」
佐々木トモカが声を上げる。
「またまたあ。いっつもおんなじこと言ってるわよ」
「トモカが惚れっぽいのは相変わらずね」
女性AとBが順番にそう言った。
「だーかーらー。楓真(ふうま)くんは間違いないんだから」
「はいはい。それで、どんな感じよ?」
女性Cが尋ねる。
「時間の問題だと思うわ。もう少しで付き合えるかも。なんてったって、過去のことを伝えているとき、彼、どこか懐かしそうな表情をしていたもの」
佐々木トモカの口調からは、自信がうかがえる。
「まったく、それ、ほとんどの男子が信じてしまうんだから、笑えないわよね」
「ほんっと。はたから見たら、ありえないって思うんだけど」
女性ABCがケラケラと笑った。
「そんな言い方ひどいわ! あのね! 私はウソをついているんじゃないんだから! 本当に過去に会ったことあるって思うのよ」
佐々木トモカが抗議する。
「はいはい。あとから、勘違いでしたーってパターンも多いけどね」
女性Bがなだめる。
「もう! そういうときもあるってだけよ」
彼女たちがあーだこーだと言葉を交(か)わしているあいだ、僕は茫然(ぼうぜん)と、トレイの一点を見つめていた。
この数分のあいだに、なにが起こったのか、イマイチ飲み込めていない。
「あのう」
男性の声がした。
ちらっと様子を見てみると、バーガー店のスタッフが佐々木トモカのいるテーブルのところに立っていた。
「あら? たしか、あなたは……」
女性Aの声がする。
「トモカさん! 僕、ぜんぶ思い出しました! それで、お付き合いを……」
彼が言葉を言い切る前に、佐々木トモカはこう言い放った。
「ああ、それね。ごめんなさい。どうやら、私の勘違(かんちが)いだったみたい。忘れてくれるかしら」
「え?」
男性スタッフは、佐々木トモカの言葉を受け入れられないようだった。
「可哀想(かわいそう)だけど、あなたは十二番目なの」
女性Cが声をかける。
「違うわよ。十一番目だったと思うわ」
「そうそう」
女性AとBが付け加える。
「まあ、今となっては、どっちでもおんなじだけどね」
佐々木トモカがとどめを刺した。
「そんな……」
男性は力が抜けたようにそう言ったかと思うと、すぐに、僕の席のすぐ横を通り、どこかへと去って行く。
彼のふらふらとした足取りと、小さな肩がすべてを物語っている。
「残念ながら、次は貴方(あなた)ですよ」と言っているようにも思えた。
僕は、彼が去って行った方向をしばらく見つめたあと、ゆっくりと姿勢を正し、手元のバーガーへと視線を落とした。
それから、なにごともなかったかのようにかぶりつく。
少し冷めているけど、やっぱりうまい!
でも……。
今年はじめて食べた期間限定のバーガーは、去年のそれよりもずいぶんとしょっぱく感じられた。