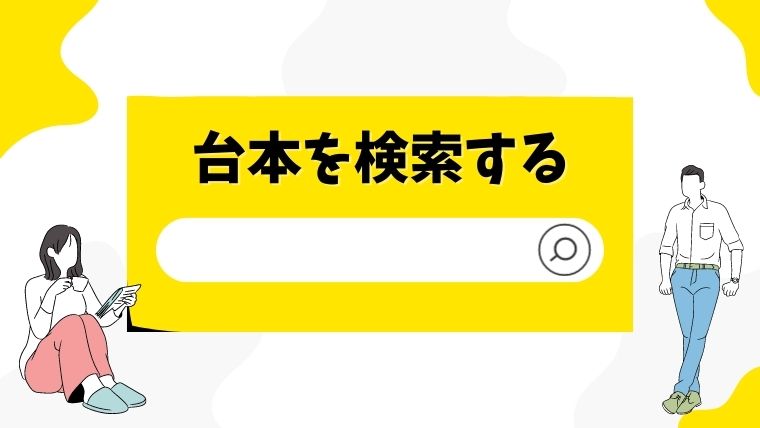●使用料:無料
●利用報告:商用のみ要(非商用は任意)
●クレジット表記:必須
ー表記内容ー
| 台本名 | 当ページのタイトル |
| 作者名 | 紺乃未色(こんのみいろ) |
| サイト名 | フリー台本サイト「キャラコエ」 |
| 台本URL | 当ページのURL
※リンク付け(URLをクリックすると、当ページに飛ぶように設定すること)必須 |
上記4点を必ず表記していただきますよう、お願いいたします。
利用のルールについては、利用規約をご覧くださいませ。
概要
| カテゴリ | 朗読(一人) |
|---|---|
| ジャンル | 現代ファンタジー・ホラー |
| 時間(目安) | 30~40分 |
| あらすじ | 主人公の家の庭には、不可思議な石像がある。 |
| 注意 | このストーリーはフィクションです。実在する人物や団体、出来事などとは一切関係がありません。 |
その他、朗読におすすめの台本は、以下のページにまとめています。

フリー台本『石像のはなし』
1
僕の家にはこじんまりとした裏庭がある。
春と秋には、壁に沿うように咲いたバラたちが、庭のまんなかにドンと立つ人型の石像に向かって、めいいっぱいに花びらをひろげる。
耳を澄ますと、ねえ! あたし、きれいでしょう? ねえ! なんとか言いなさいよ、なんて声が聞こえてきそうにも思える。香水を纏った貴族のように、香りをふりまくのも忘れない。
一方、縦五十センチ、横に十センチほどの石像はかたぶつだ。彼女たちの声を無視するように、ただ立っている。少しでも笑ったら、内側からパリンと割れて死ぬのか? と聞きたくなるような表情で、じっとこちらを向いている。
まるで、僕のことしか見えていないみたい。
「こいつがいるかぎり、大丈夫だ」
僕は石像を見つめ返し、キリキリと痛む胃を押さえ、呟いた。
2
「これはね、身代わりの石像といわれているんだよ」
祖母がそう言ったのは、僕がまだ、小学校六年生の頃だ。
朝からしとしとと雨が降り、天気予報士の言葉をかりるなら、すっきりとしない天気だった。
太陽が分厚い雲の裏に隠れているせいか、日差しの気配はみじんも感じられない。古びた畳の匂いがする居間は、やけに薄暗く、むしむしとしていて、とにかく居心地が悪かったのを覚えている。
そんなとき、町はずれにある古びた骨董屋から、祖母宛に怪しげな石像が届いたのだ。
「こんちは! お荷物ですよ!」
天気に似つかわしくない、元気いっぱいの声だと思った。
「あらあら。待っていたのよ。悪いけど、そのまま、裏庭に運んでくれるかしら?」
「もちろんっす」
配送業者は二人掛かりで重たそうなそれを運び、その背後では母がいったい何事かと、いつものエプロン姿でうろたえていた。
「ありがとうねえ。あ、ハンコね。ハンコ、ハンコ」
「ちょっと! お義母さん」
「そんなに声を尖らせて、どうしたの?」
祖母は慣れた手つきで玄関に置いてある眼鏡を手にとった。伝票にハンコを押し、顔から少し遠ざけて押し具合を確認したのち、それを配送業者へと渡す。鼻歌まで歌いながら。
配送業者の二人組は、我が家に漂う不穏な空気から逃げるようにして、そそくさと帰って行った。
「お義母さん! なんですか、これは。へんな儀式でもするおつもりですか?」
あのときの母の言葉には、きっとありったけの嫌味が込められていた。ところが、祖母がおこなったのは、まさに儀式じみたものだったのだ。
「まあまあ。見ていなさい。マサトくん、こっちにきて手のひらをおだし」
祖母は庭から手招きした。
「え?」
僕は一歩、後ろに下がりそうになるも、祖母のやけににこにことした笑顔に暗示でもかけられたのか、体が勝手に動き、気が付くと指示の通りにサンダルを履いて裏庭へと下り、右手を差し出していた。
思えば、昔から、祖母には逆らえなかったっけ。
「お義母さん、なにするんです?」
母の声がした。
「大丈夫さ」
祖母がそう言ってからは、一瞬だった。
彼女はどこかに隠し持っていた針の先で、僕の親指の柔らかな腹を突いた。濃厚なイチゴジャムのような赤がぷつりと滲む。六十五歳をとうに過ぎているとは思えないほど、俊敏な動きだったものだから、悲鳴を上げる暇すらなかった。
「ちょっと! お義母さん?」
僕の代わりに声を出したのは、母だった。
その声に続くように、僕は叫ぶ。
「痛い! おばあちゃん。やめて!」
「落ち着きなさいな」
祖母はそう言うと、血の滲んだ僕の指を掴み、石像の顔の方へとひっぱった。
ちょうど、そいつの唇があるところだ。
僕はパニック状態になりながらも、それが、やけにひんやりしていることをありありと感じとった。まったく意味のわからない状況のなかで、その冷たさだけはたしかだった。
「お義母さん。いったい、なにをしているんです? おふざけなら、よしてください」
母の叫びに近い声が、あたりに響く。
「さっきも言った通り、これは『身代わりの石像』さ。今のはちょっとした下準備だよ」
祖母は、母の金切り声や僕の悲鳴に怯むことなく、淡々と答える。
「み、身代わり?」
僕は、震える声で、その怪しげな言葉を繰り返した。
「そうさ。これからは、マサトの病やケガを代わってくれる」
祖母は満足げにうなずく。
「なんです、それは。ばかばかしい」
一方の母は、呆れたように吐き捨てた。
祖母は昔から、突拍子もない行動をとるわりに、言葉が足らず、誤解を招くことがあった。
突然、大声で呪文らしき言葉を唱えながら、タンスのなかの服を大量にゴミ袋に突っ込みだしたり(あとから知ったところ、見たことのない虫がいたらしい。祖母は大の虫嫌いだ)、家のまわりを、歌いながらスキップしたり(ただの運動だったらしい。歌っていたのは、そのとき楽しかったから)、するものだから、近所の人たちからは変人として扱われていた。
なにを言っても聞き入れようとしない性格だからか、母もそこで諦めたように、ため息を吐く。
「私にはわかるんだよ。この石像の持つチカラはね、とてつもなく大きい」
「その、チカラが本当にあるとしてですよ、安全なモノなんですか? 正直、さっきの儀式といい、気味が悪いですよ」
母が言った。
「そんなのはね、なんでも使いようだ。安心して利用できるモノなんて、どこにもない。……マサト」
「な、なに」
祖母にまっすぐみつめられると、僕は固まってしまう。彼女の目は、祖父がよくやっていた囲碁の石みたいに黒くて丸い。それは、蛍光灯の明かりを弾いて人工的に光るんだ。僕はどうしてか、そこを見ずにはいられない。
「いいかい、よくお聞き」
「う、うん」
「さっきも言った通り、この『身代わり』の石像のチカラははかりしれない。だから……大切にするんだよ」
まだ小学生だった僕は、祖母の言葉を素直に受け止め、定期的にその石像の手入れをした。ホースの水をかけながらタワシでごしごしと洗い、細かいところは使い古した歯ブラシで擦って、汚れを落とした。
そうこうしているうちに、だんだんと愛着がわいてくる。タワシを使い丁寧にブラッシングをし、歯ブラシで優しく毛づくろいをしてあげているような錯覚さえあった。まるで、裏庭でペットでも飼っているような気分だ。
もちろん、石像は話すこともなければ、食べることもない。鳴くこともなければ、歩くこともないのだけれど。
三ヶ月ほど経った頃には、石像の掃除はすっかり僕の習慣となった。
最初は、ぶつぶつと文句を言っていた母も「そういや、イギリスのローズガーデンにも、石像ってあるものね。むしろおしゃれでいいじゃない」と、考え直したようだった。
僕は母のこういう、最終的にはポジティブな方向に意識を向けるところが、凄いと思う。
そうでなければ、祖母とはきっと暮らせない。
3
最初の異変に気が付いたのは、高校生のときだった。
珍しく、学校に遅刻しそうだった僕は、自転車をかっとばしていた。いつもなら、右左右の順に視線をやってから渡る信号のない交差点にさしかかる。
「やばい、やばい」
僕は焦りから、右の方向だけに顔を向けると、おろしたてのスニーカーの裏でペダルをおもいっきり踏みつけた。
本当にすぐだった。僕は体の左側に衝撃を感じ、宙へと投げ出された。青い空に浮かぶ巨大な雲や、規則正しく並ぶ車の列、あんぐりと口をあけてこちらを見ている人々が、スローモーションとなって視界に映る。音はない。視覚以外の感覚はどれも、どこかにすっ飛んでいったみたいだった。
そのうち、重たいリュックがコンクリートに落ちるような音がして、意識がふつりと途切れた。
「軽傷だったのよ! 本当によかった。本当に……」
僕がベッドの上で目を覚ますと、母は父に肩を支えられるようにして、ぼろぼろと涙をこぼしていた。
「へえ。そうなんだ」
どうやら、ぶつかったのはトラックだったようで、こんなのは奇跡的だと、医者からも言われたらしい。僕は、どこか他人事のように、ふうんと思った。だって、大きな事故にしては、手も足も、もちろん頭も、ぜんぜんいつも通りだったから。
消毒液の匂いをべったりとはりつけた病室の壁やら天井やらをなにげなく見渡す。さっさと帰れ。そのベッドはあんたのものじゃない。そう、あしらわれているような気すらした。
「もう、退院できる?」
「え? ああ。うん、聞いてみるわ」
母はあっけにとられたのか、涙をひっこめて、そう言った。
「なんだこれ」
退院後、石像の前で首をかしげる。
そいつの左腕のところが、黒く変色していたからだ。いきなりこんなことってあるのだろうか。そう思い、父に聞いてみるも、サビだろうと流されてしまう。僕はどこか腑に落ちない気持ちを抱えつつも、手入れを続けることにした。
突然、あたりが暗くなる。黒煙のような色をした雲が、どこからか流れてきたらしい。これは、雨が降るぞ。そう思ったときだった。
ぽつり、と空から水滴が落ちてきて、僕の指を濡らした。その冷たい感触がいつかの儀式を思い出させる。
「もしかして……」
じっと石像に視線をやるものの、そいつはいつも通り人体模型のように、ただまっすぐに立ち、僕を見ているだけだった。
4
やはり、と確信を持ったのは、大学生のときだった。
僕はそのとき、ラインカーでテニスコートの白線を引いていた。
まっすぐに線を描くのは意外と難しい。顔を伏せ、じっと集中し、白線を描いていたのがダメだった。
グラウンドの中央から、それは飛んできた。まずい、野球部のボールだ、と理解し、両手を上げようとするものの、猛スピードで向かってくるボールを受け止められるはずがなかった。
僕はいつかと同じように、意識を失い、二日間眠り続けた。
退院後、裏庭に出るなり、僕は震え、両手をクロスするようにして自身の肩を抱きしめた。首から腕にかけてうっすらと生えている産毛たちが、興奮したように立ち上がる。
「黒くなってる!」
一方、僕はというと、軽傷だった。当たりどころがよくなかったらしく、このときも医者から驚かれた。
「すごい! すごいぞ」
僕は片手で石像の頬を撫で、叫んだ。
このときから、僕は無敵になった。なにがあってもケガをしない、強者だ。きっと、病気もしないし、死にもしない。
なぜなら、この石像があるから!!!
この事実は自信という名の栄養素となり、筋肉やら骨やら血管やらのすみずみにまで満ち溢れた。なんだってできる。バンジージャンプだって、無茶なアルバイトのシフトだって、暴飲暴食だって、アルコールの一気飲みだって怖くない。
僕は刺激的なことを、思いつくかぎりなんでもやった。
そんなむちゃくちゃな生活が続き、やがて社会人になった。
「あそこ、受かったのか? やるな!」
「マサトくん、あの部品メーカーに就職決まったの? 凄いじゃない」
「おい、聞いたぞ。」
僕は地元では有名なとある部品メーカーに入社し、まわりからもちやほやされて、鼻高々だった。
「マサト、頑張ったのね。でも、無理しちゃだめよ」
「ああ、とくにお前は、すぐにむちゃくちゃなことをするからな。仕事ではほどほどにしておいた方がいいぞ」
母も父もまんざらでもなさそうで、頬がゆるっゆるに緩んでいたのを覚えている。彼らとも、あとどのくらい一緒にいられるのかわからない。
ちょっとした親孝行になっていたら嬉しい、だなんてらしくもないことを考えたりもした。
仕事は楽ではなかったものの、やりがいがあった。やればやるだけ、数字に反映される営業職は、無茶が許された僕の身体にぴったりだとすら思っていた。
とはいえ、土日は書類を片付けるために出勤していたものだから、実質、休みはほぼなく、さすがにふらふらになりながら、帰宅することもあった。
いつからか、眉間の赤いニキビは治らなくなり、お腹や背中にはかゆみのある発疹がいくつもできていた。
「マサト、さすがに一度、病院に行ってきたら?」
母にそう言われた回数も、もう数えきれない。
「大丈夫だって」
「でも……」
「母さんも知ってるだろ! 俺の身体が強いこと。ちょっとやそっとのことじゃ、倒れたりしないんだ」
「そうだけど……」
僕は、母さんの視線から逃れるように、裏庭へと続くガラス戸をあけた。
滑りが悪いのか、キーキーと黒板をひっかいたようなイヤな音が、耳にツンと響いた。
古びたサンダルに足を突っ込み、石像の前へと進む。どこからか、秋の冷たい風がやってきた。干からびた枯葉を捨てるように裏庭へと落とし、ついでといわんばかりに、僕の全身から容赦なく熱を奪い去っていく。
ふいに、胃が痛み、背が丸まった。
「う……」
思わず声が漏れる。
「大丈夫だ、大丈夫」
ふうふうと息を吐きながら、問題ないと自分に言い聞かせる。
だって、僕には、身代わりがいる。
僕はヘソの上をさすりながら、まっすぐに石像の顔を見つめた。
「ふう」
小さく深呼吸をすると、胃の痛みが心なしかマシになったような気がする。今日は早く寝よう。こういうときは、睡眠をとるのが一番だ。きっと、明日になれば、楽になっているはずだ。
5
その日の寝つきは、最悪なものだった。
大粒の雨が裏庭へと降り注ぎ、石像の上から下までに、歪んだ水玉模様がぶつぶつと滲んでいく。あっというまに石像は雨水に覆いつくされ、墨汁のような色へと変わってしまった。
それは、不吉さを感じさせる光景だった。
空ではゴロゴロと雲が唸っている。
ピカッと鋭い光の線が弾け、次の瞬間、石像は窓ガラスが割れるような音を立てて、真っ二つに……。
「いやだ!!!」
目覚めたときには朝だった。
雨上がりの湿った土の匂いとむせかえるような甘いバラの香りがする。
「え? なに」
僕の視界は、いつもの天井ではなく、よく知るはずの居間を映している。そこから動くことができない。
おかしい! おかしい! おかしい! パニック状態になるものの、あたりには誰もおらず、助けを求めることもできない。
「あら? マサト。今日は早いのねえ」
台所の方から、母の声がした。
「僕はここだ! ここにいる!」
そう伝えたいのに、声にならない。
「うん、たまにはね。朝ご飯は?」
聞こえてきたのは、正真正銘、僕の声だった。いったい誰だ! 僕のふりをしているのは!
「あら? 珍しい。朝ご飯、ちゃんと食べるのね」
母は感心したように言った。待ってくれ。そんな、わけのわからない奴に騙されるな!
「もちろん。体は資本だからね」
「よかったわ。最近、調子悪そうだったから、心配してたのよ。ちょっと待っててちょうだい。ついでだから、すぐに準備するわ」
「はーい」
僕の偽物は、まるで昔からそうしてきたかのように、元気よく返事をした。
台所の窓を閉める気配がして、すぐに靴下が畳に擦れる音がした。その足音はだんだんとこちらへと近づいてくる。
ガラス戸越しにひとりの男と目があった。どこからどう見ても、僕そのものだ。
「ふふ」
そいつは笑いながらサンダルを履き、裏庭に下りてくると、首を回し、手首を回し、足首を回した。一方の僕は、体全体がカチカチに固まり動けない。
「人間の体って、想像よりもうんと柔らかいんだね」
そいつは、内緒話をするように、小声でささやきかけてくる。
それから両手を空に向かって上げると、心地よさそうに伸びをしてみせた。
信じたくはないが……。きっと、こいつの正体は石像だ。
なんという最悪な事態だ。もしも人間の体だったのなら、全身の力が抜けて、地面にへたりこんでいたに違いない。幸か不幸か、いや不幸なことに、今の僕は、ただ立っていることしかできない。
こいつはなにをする気だ? 最初から、身代わるふりをして、体をのっとる隙をうかがっていたのか? 聞きたいことは山ほどあった。
「ああ。そこ、ちょっとだけ、窮屈でしょう?」
悪びれるそぶりもなく、そいつは言った。ちょっとどころの話じゃない。金縛りにでもあったかのように、ぴくりとも動かないんだから!
「でも、体はずいぶんと楽でしょう?」
その言葉には頷かざるをえない。
たしかに、胃の痛みは感じないし、発疹特有のうっとうしいかゆみもない。ついでに、肩こりや腰痛も消えている。
「大変だったんだよ? いつもの方法では対処できないくらいにキミの体、弱っていたようだったから。……でもね、ボクのパワーは偉大なんだ。キミが知っているようにね。だから、こうやって、まるごと身代わりになることができたんだよ。ふふ。大丈夫。仕事も任せて。うまくやるからさ」
僕の偽物はにっこりと笑った。
悪意のない笑みがかえって怖いと感じた。こいつはおそらく、善意でやってるんだ。左腕や頭のケガを代わってくれたように、弱った体ごと、身代わってくれたんだ。
……たぶんだけど。
「この体があれば、いろんなことができるね。楽しみだなあ。ほら、ここから居間のテレビが見えるでしょ? ボク、ヒマだったからよく見てたんだよね。高いところからジャンプスーツひとつで飛び下りたり、急な崖を登ってみたり、スポーツカーのレースに参加してみたり……。そういうの、楽しそうだなあってずっと思ってたんだ」
やめてくれ! 僕の体でそんな危険なこと、するんじゃない!
「あ、でもまずは、健康体に戻さないとね。今のこの体、けっこう辛いから。キミ、よく耐えてたよね」
「マサト! 庭にいるの?」
母の声だ。
「じゃあ、行ってくるね。あ、ここ、網戸にしておくよ。ガラス戸、閉めちゃったら寂しいでしょう?」
僕の身代わりは、妙な気遣いをしてくるりと背を向けた。待ってくれ! 僕はどうなる? また、もとに戻してくれるのか? 叫びはちっとも声にならない。どうしてこんなことに……。
僕は、祖母のいいつけを守り、石像を大切にしていた。
「石像を大切に……」
叫びどころか、呟きすら音にならない。
「……あ」
祖母の言葉を思い出し、はっとした。
「この『身代わりの石像のチカラは計り知れない。だから、大切にするんだよ』」
そうか……。
そうか、大切にすべきは、石像じゃなかったんだ……。
僕はようやくそのことに気づき、心の中でがっくりとうなだれる。言葉足らずな祖母の真意を理解するものの、ときはすでに遅すぎる。
やるせなさに、意味をなさない言葉を思いっきり叫びたいけれど、それは叶わない。
「痛いっ」
網戸越しに悲鳴が聞こえた。
「あら? 足の指をぶつけたの?」
母が尋ねる。
「いった。小指、痛いって」
「そりゃ痛いわよ。ひょっとして折れたんじゃないの?」
ときを同じくして、足元の一部がじんと熱をもった。
あ、黒くなった。見ることはできないけれど、僕にはわかる。
「くそう。こんな棚なんかに……」
身代わりは悔しそうに呟く。
「病院に行っておいた方がいいわよ」
母がそう口にするも、身代わりはそれには答えずに、だんまりを貫いた。
「マサト?」
「治った」
「え? もう?」
「うん」
「あ、あらそう。まあ、あなた、昔からそういうところあるものね」
母はけろっとしてそう返す。
「ふふ。なるほど。これは便利だ」
「ええ? 便利?」
母が尋ねる。
「なんでもない。わあ! おいしそう。僕、ずっと食べてみたかったんだ」
「なあに? 変な子ねえ」
変なんじゃない。そもそも僕じゃないんだ!
そうせいいっぱい伝えながら、最悪の事態を想像する。あいつはきっと、健康的な生活を意識してくれるだろう。だが、ケガはどうだ? 人間の体に慣れていないはずだから、きっと今みたいになにかしら頻繁にやらかす可能性がある。それで、危ない遊びでもされたら……。
ぞっとした。
もしも、僕が石像になったまま、あいつが体を痛めて、そのせいで、どんどん石像の色が黒くなったら、どうなるんだろう。
あの夢のように、いつか割れてしまったら……。
いやだ! いやだ! いやだ!
誰でもいい。助けてくれ。
自由に動ける体を手に入れた石像は、視界のなかで、楽しそうに手足を動かしている。
顔なんてにっこにこだ。……新たな人生を手に入れたことを喜んでいるみたいだ。
どうか、どうか、どうか。健康体に戻ったら、さっさと体を返してくれますように。
僕は、痛みもかゆみもない体で、そう願うことしかできなかった。