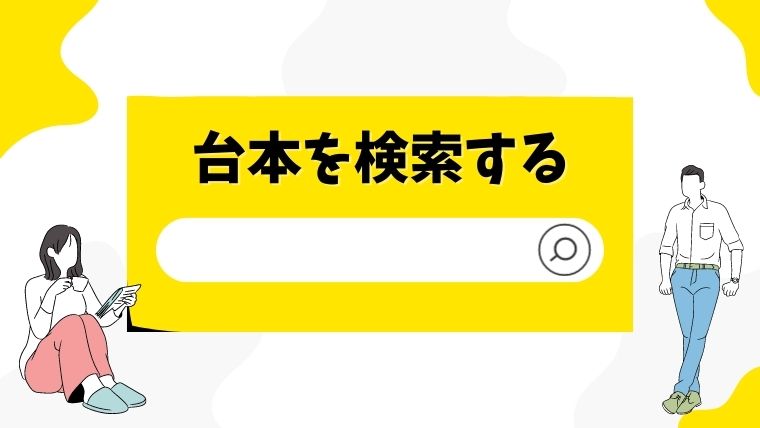●使用料:無料
●利用報告:商用のみ要(非商用は任意)
●クレジット表記:必須
ー表記内容ー
| 台本名 | 当ページのタイトル |
| 作者名 | 紺乃未色(こんのみいろ) |
| サイト名 | フリー台本サイト「キャラコエ」 |
| 台本URL | 当ページのURL
※リンク付け(URLをクリックすると、当ページに飛ぶように設定すること)必須 |
上記4点を必ず表記していただきますよう、お願いいたします。
利用のルールについては、利用規約をご覧くださいませ。
概要
| カテゴリ | 朗読(一人) |
|---|---|
| ジャンル | 現実世界・SF |
| 時間(目安) | 6~10分 |
| あらすじ | 今夜、九時。終末を迎える。 とある夫婦の小さな物語。 |
| 注意 | このストーリーはフィクションです。実在する人物や団体、出来事などとは一切関係がありません。 |
その他、朗読におすすめの台本は、以下のページにまとめています。

フリー台本『終末の魚たち』
1
どうやら、世界が終わるらしい。
そんなニュースが世間を騒がせてから、半年あまり。
ついにその日がきたというのに、町はいつもと変わらない。
空には雲一つない、いたって普通の土曜日だ。
どういうつもりなのか、配達員はポストに朝刊《ちょうかん》を届け、隣の鈴木さんは鉢植えに水をやっていた。
しいて変化を挙げるなら、数ヶ月前まではチラシでぎっちり膨らんでいた新聞紙が、ほっそりとしたことだろうか。
なるほど、これは妙に現実を知らしめてくる。
タイムリミットは今夜九時。残されているのは、十一時間あまり。
結婚して十年になる妻は、いつものようになにもいわずに外出したばかり。
めっきり少なくなった会話から知ったことは、最近、中学校時代の友人とよく顔を合わせているということだ。
ひょっとして、浮気だろうか?
ここにきて、疑いもしなかった考えがよぎった。
まあ、今となっては、どちらでもいいことか。
僕は、ソファから立ち上がり、水槽《すいそう》の前へと移動した。
「君たちも、気の毒だったね」
このタイミングに生きていたばっかりに、抗いようのない大きな流れに生を閉ざされてしまう。
慈《いつく》しみが伝わったのか、四匹の金魚がガラスの傍によってきた。
自慢じゃないが、彼らは僕に懐いている。こちらをじっと見てきたり、エサの時間じゃなくても、近づいてきたりする。
可愛いものだ。
思えば、金魚たちとの付き合いも、もう、十一年になる。飼ってから知ったことだが、わりと長生きなのだ。
彼らとは、妻がまだ恋人だった頃に近所の夏祭りで出会った。
今より体が一回り小さかったときは、僕が水槽に近づいても知らんぷりしていたっけ。
ところが、年数を重ねるうちに、どんどん信頼関係が生まれていった。少なくとも僕はそう思っている。
「でもなあ」
それも全部、意味のないこと。
ふいに虚無感《きょむかん》を覚え、テレビをつけた。
電源はオン。真っ黒な画面。ぼやけた僕の輪郭《りんかく》が映っている。
ぽちぽちと義務的にチャンネルを操作すると、ひとつだけニュースを報道している番組があった。
いやというほど聞いた単語が、繰り返されている。
地球、隕石、壊滅的、避けようがない、それから今日の日付。
「いっそのこと」
町がパニックとなり、ぎゃあぎゃあ騒がしければよかったのに。
そうすれば、わけもわからないまま終末を迎えられたはずだ。
少しの希望を持ち、窓を開けると、秋の風がひゅるると入り込んでくる。
僕の期待を裏切るように、街はどこまでも静かだった。
2
妻が帰宅したのは、夕方の六時。
僕が両親との電話を終え、金魚にエサをやりながら「最後の晩餐《ばんさん》だね」と、笑えない冗談を言っていたときだった。
そりゃあ驚いた。
てっきり、もう帰ってこないと思っていたから。
「ただいま」
「……おかえり」
「はい、これ」
妻は、茶色い包みを差し出した。ふわりと香ばしく、甘い匂いがした。
どこかで嗅いだことのあるような……。
僕は、袋を受け取ると、片手を突っ込み、中のものを引っ張り出した。
「タイ焼き!」
思わず声を上げる。
「そう、覚えてる? 南公園の隣のところ」
「ああ、学生時代によく君と食べてた」
もう十五年以上も前の話だ。
大学帰りにデートするとき、よくそこでタイ焼きを買って、いろんなことを話した。
どうでもいいような、ささいなことばかりだったけど、僕はけっこうその時間を気に入っていたんだ。
「ふと、思い出してね。さっき友達と別れたあと、行ってみたの。そしたらさ、まだやっててびっくり」
妻はそう言いながら、イスに腰掛け、テーブルに頬杖《ほおづえ》をついた。
珍しく、会話を続けてくれる気でいるようだ。
「へえ。あのメガネかけた女の人だった?」
そこは女性の店主が切り盛りしていた。
当時、五十代くらい。
人付き合いを好まなさそうなタイプだったこともあってか、周りの大人は、変わり者の独身者だと噂していたっけ。
「そう! おんなじ人だった。ずいぶんとおばあちゃんになってたけど。しかも、私のこと、覚えててくれたのよ。あなたのこともね」
妻は、興奮したように言った。
「凄いね。たしかに、通いつめてはいたけど、記憶に残ってるもんなんだね」
「まさかって感じだった。それで私ね、これで最後だからって思って伝えたの。あのときは彼と恋人だったけど、今は夫婦ですって」
「そしたらなんて?」
相手の反応が気にならないといったら嘘になる。
「こっちが拍子《ひょうし》抜けするくらい喜んでくれて。その人、なんて言ったと思う?」
「わからないよ。なに?」
「《《今日》》、お店開けてて、本当によかったって。そのことが聞けて嬉しいって。私、あの人の笑ったところ、初めて見たかも」
きょう、という言葉の重みがのしかかる。
「……そっか」
タイ焼き屋の店主は、懐かしい客にいったい何を思ったのだろう。
「私、最初は意味がわからなかったの。久しぶりの再会って言っても、お互いに名前も知らないのよ? カップルの客が時を経て夫婦になっていたからって、そこまで喜ぶかなあって」
「うん」
「だけど、ちょっと今、わかったような気がする。あ、でも、どうだろう。違っているかも」
彼女は、水槽をぼんやり眺めながら言った。
そこでは、四匹の金魚たちが十年前とおんなじように思いのままに泳ぎ、エサを突いている。
「ええ? どっち?」
僕は笑った。
「たぶん、それを理解するには、私はまだ若すぎるのよ」
「もう、三十代なのに?」
「まだ三十代よ」
妻は不服そうに言った。
「そうだね、まだ三十代」
ここで機嫌を損ねるなんて野暮なことをしてはダメだ、と僕はうなずく。
3
「いただきます」
妻は会話をやめて、ぱくりとタイ焼きにかぶりつく。
「いまだに、君はしっぽからなんだね」
僕は頭の方から頬張った。
もぐもぐと、タイ焼きを堪能する。まだ、温かい。
「変わらないね」
「うん。この味だよ。やっぱり美味しいや」
僕はそう言って、お茶を淹れるために立ち上がった。学生のときはコーラばかりだったけれど、今は緑茶が恋しいんだ。
妻は無言でタイ焼きを食べ続けている。沈黙。それが心地良かった。
リビングに漂うのは、水槽のエアーポンプから聞こえるブクブクという音だけだ。
「ねえ、あの子たちさあ、自分の身に起こること、なーんにも知らずにごはん食べてるのよねー。いつもと変わらず」
僕がお茶をのせたトレーをテーブルに置くと、妻が言った。
「そうだね。まあ、僕たちも似たような感じだけど」
僕はイスに座り直す。
「そう? 私たちは、前もって情報を知ってるじゃない」
「そうはいってもさ、最期のときに、何が起こってどうなるかなんてわからないし」
「まあ、そうね」
妻がうなずく。
「夜ごはん、どうする? 簡単なものなら作るけど」
僕は暗い雰囲気にならないようにと、話題を変えた。
「うーん。あ、せっかくなら、冷蔵庫のなかのもの、一緒に全部使い切りましょうよ。なんでもありの料理をするの。どう?」
妻がいらずらっこのように笑う。
大学時代の面影がちらつく。思えば、久しぶりに見た笑顔だった。
「それはいいね」
僕は答えながら、ふと、胸のなかに懐かしさと温かさがこみあげてくるのを感じた。
ありきたりな言葉であらわすなら、これが幸せなのかもしれない。
すっかり、忘れていたけれど。
「決まりね! すぐにでもとりかかりましょう。なんてったって時間がないんだから」
妻が冗談じみた口調で言った。
「その通りだ」
どうか、彼女もおなじ気持ちでいてくれますように、とひっそり願う。
終末まであと少し。
僕は最期の瞬間まで、かつてはありふれた、小さくも愛おしい時を過ごそうと思う。
そこにいる金魚たちみたいに。
終