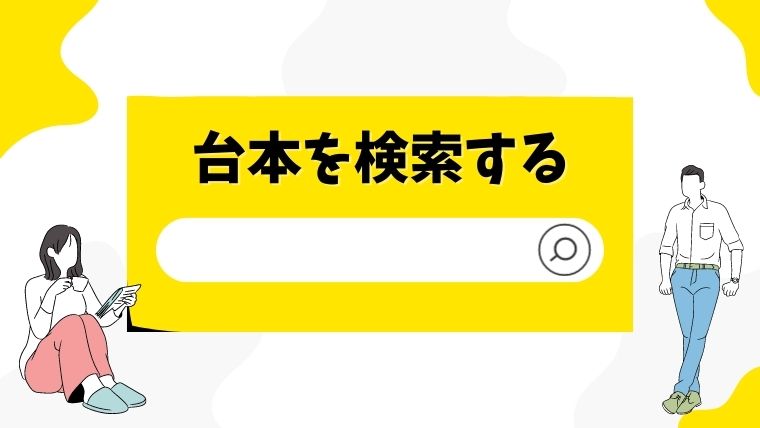●使用料:無料
●利用報告:商用のみ要(非商用は任意)
●クレジット表記:必須
ー表記内容ー
| 台本名 | 当ページのタイトル |
| 作者名 | 紺乃未色(こんのみいろ) |
| サイト名 | フリー台本サイト「キャラコエ」 |
| 台本URL | 当ページのURL
※リンク付け(URLをクリックすると、当ページに飛ぶように設定すること)必須 |
上記4点を必ず表記していただきますよう、お願いいたします。
利用のルールについては、利用規約をご覧くださいませ。
概要
| カテゴリ | 朗読(一人) |
|---|---|
| ジャンル | 現実世界 |
| 時間(目安) | 15~20分 |
| あらすじ | 主人公は、行きつけのバーでひとめぼれした宮口に近づこうと、彼が勤務するビルの清掃員に転職する。 |
| 注意 | このストーリーはフィクションです。実在する人物や団体、出来事などとは一切関係がありません。 |
その他、朗読におすすめの台本は、以下のページにまとめています。

フリー台本『追いかける女、その先に』
1
その人と出会ったのは、いきつけのバー「rye field《ライフィールド》」だった。
常連さんたちは、みんな、そのお店のことをライって呼んでいる。
こじんまりとしたところだけど、マスターの人柄がいいからか、自然と人が集まってくる。そんなバー。
たまに、顔に深い傷がある人だとか、顔を半分以上隠した怪しい人だとかもやってくるけれど、彼らが何者なのか、わたしは知らない。
いちいち聞くのも野暮《やぼ》ってもんだ。
それで、その人、宮口《みやぐち》さんはとある金曜日の夜に、わたしの二つ隣の席に座った
手足がすらりとしていて、モデルのようないでたちだった。
たぶん、30代半ばくらい。
きりっとした目はりりしくて、それでいて表情はやわらかい。
生地《きじ》のしっかりしたスーツからは、初夏を思わせるような香りが漂っている。
なんて素敵な人なんだろうと思った。
きっと、運命の王子様だ!
いわゆるひとめぼれってやつ。
わたしはめったに酔うことなんてないんだけれど、そのときは、アルコールが猛《もう》スピードで全身を駆け巡ったのか、頭がくらくらした。
マスターと交わしている会話によると、近くにある大手のメーカー会社で働いているらしい。
やっぱり仕事もできる人なんだ。
この人と結婚したら、今の生活を抜け出して、幸せになれるんじゃないかしら。
わたしは、うっとりとして、心のなかで大きくうなずいた。
それからひっそりと計画を立てる。
「それじゃ、マスター、そろそろ行くよ」
男性が言った。
「はい。いつも、ありがとうございます」
「あ! 次はしばらく、来れないかも」
「そうですか。お体に気を付けて」
マスターと少しだけ言葉を交わして、彼は立ち上がった。
ドアからぶらさがっているベルがカランと鳴った。
軽やかなその音は、わたしにとってはゴングの音だ。
彼を追うようにしていきおいよく立ち上がると、マスターが小さく笑った。
「あ、あの、お会計……」
ちょっぴり恥ずかしい。
「ええ、ええ。わかってますとも」
マスターはゆっくりとした口調で言った。
2
わたしはスーパーのレジ打ちのアルバイトを辞めた。
突然のことだったから、店長には怒られたけれど、気にしてなんかいられない。
「君、まだ入ったばかりじゃないか」
そんなこともいわれたけど、べつにこの仕事に憧れていたわけじゃない。
あれ? どうして応募したんだっけ?
まあいいか。
きっと、忘れてしまうくらいどうでもいいことだったんだ。
今日から職場は、彼のいるビルの清掃員《せいそういん》だ。
まずは、宮口《みやぐち》さんのそばに潜入しようと思い、仕事を探すとすぐに見つかった。
これから、彼の部署や役職を探っていけばいい。
運の良いことに、同僚《どうりょう》はウワサ好きの人ばかり。
これならすぐに情報を掴めそうだ。
わたしは、デッキブラシをぎゅっと握った。
「あなた、新人にしては手際《てぎわ》がいいじゃない。経験者?」
先輩が大きな声で尋ねてくる。
「あ、ありがとうございます。はい、過去に5回くらい、清掃員の仕事をしたことがあって……」
「5回も?! なるほどね。だからこんなに仕事ができるわけね。期待しているわ。わからないことがあったら、なんでも聞いて」
彼女は、がはがはと声を上げて、わたしの肩を叩いた。
コミュニケーションが苦手でも、それなりの経験やスキルがあれば関係性はなんとかなるもんだ。これは最近、学んだこと。
わたしはゆっくりとその職場に馴染んでいった。
3
あれから、バー「rye field《ライフィールド》」に顔を出してはいるものの、宮口《みやぐち》さんとは会えていない。
もしもばったり出くわしたのなら、同じビルで働いているのだと話しかけられるのに……。
現実は甘くはないようだ。
それならば、やはり次の手を打つしかない。
集めた情報によると、彼は3Fフロアにある経理部で働いているらしい。
わたしもすでに簿記《ぼき》を猛勉強中だ。
採用試験を受けて、合格したら、じょじょに距離を詰めていこう。
未経験だと年齢制限があるけれど、そんなものはでっちあげればいい。
きっと、わたしのことだから、
入社するまではスムーズに進められるはず。
ただ、、、こんなことをして、本当に宮口《みやぐち》さんと仲良くなれるのだろうか。
ずっと見ないふりをしていたことがぼんやりと浮かんでくる。
「少し、お疲れですか?」
はっとして、顔をあげると、マスターがにこやかに笑っていた。
「あ、はい」
店内には、もの悲しげなクラシック音楽が流れている。
このせいだ!
想像がネガティブになってしまったのは。
「お仕事、大変ですか? ええっと、今はスーパーでしたか?」
マスターが尋ねる。
「いいえ。清掃員の仕事をしているんです」
「ほう。本当になんでもできるんですね。今回は、体力勝負ですか。あなたなら、なんなくこなせそうですが……」
マスターは、片目をつむってチャーミングなしぐさをして見せた。
「ふふ。たしかに動くのは嫌いじゃないんで、仕事は合っているんです。
ただ、わたし、肌が弱いので、手が荒れるのが辛いですね」
両手を広げて、手の甲を眺める。
そこは、全体的に赤くなり、皮がむけていた。
慣れてはいるけれど、あらためて見ると、痛々しい。
その状態が、自分の姿をあらわしているような気がして、喉《のど》の下がつきりと痛んだ。
「ああ、水を使いますからね。それは、痛みますね」
マスターの声は優しかった。
店内には、誰もいない。
それがいけなかったんだ。
わたしの目からは雫《しずく》がぽたぽたと落っこちて、テーブルを汚していた。
「おやおや」
マスターは、無駄のない動きでティッシュペーパーの箱を差し出してくれる。
ありがとうございます、も言えずに、わたしはただただ泣き続けた。
「……わたしは、幸せになりたいだけなんです」
そう言って、またわんわん泣いた。
それもただ、王子様を待っているだけじゃなくて、ちゃんと自分で捕まえにいこうとしているのに……。
うまくいった試しがない。
そんなことを、声にならない声で、マスターに訴え続けた。
思えば、彼には、これまでにもいろいろと愚痴《ぐち》をもらしていたっけ。
追いかけてばかりの恋愛のことも含めて……。
なんて迷惑な話だ、と客観的に思いつつ、自分でもどうすることもできなかった。
やがて、涙はひっこみ、頭がすっきりした。
なにごともなかったかのように、支払いを済ませ、外にでる。
生ぬるい風が頬を濡らしてひんやりとした。
採用試験まであと1ヶ月。
泣いてなんかいられない!
わたしはぎゅっと拳《こぶし》を握りしめた。
4
「合格」の二文字をみて、ふふんと笑う。
目的があれば、なんだってできる。
そんな自分はけっこう好きだ。
経理部に入ることに成功したわたしは、やっと宮口《みやぐち》さんのそばで働くことができた。
手の届きそうな距離、ななめ向かいの席にいる。
ところが、3ヶ月が経《た》つ頃には、以前ほどの熱量がわいてこなくなった。
またか……。わたしはがっかりした。
いつも、追いついてしまうと、とたんに興味がなくなってしまう。
その繰り返し。
いっそのこと、告白して、付き合ってしまえばいいんじゃないだろうか。
恋人になれば、なにかが変わるかもしれない。
そんなことを考えると、今すぐにでも行動を起こしたくなった。
たしか会議室が空いているはずだ。ちょっと呼び出して、気持ちを伝えてしまおう。
わたしは勢いよく立ち上がり、すたすたと宮口《みやぐち》さんのところまで足を進めた。
「あの! みや……」
名前を呼ぼうとしたとたん、後ろから誰かにぎゅっと腕を掴まれた。
ふりむくと、そこには見知らぬスーツの男が立っている。
5
「え?」
わけもわからず、喉《のど》の奥からまぬけな音が落ちてくる。
「少し、いいですか?」
その声は、どこかで聞いたことがあるような気がした。
「えっと……。は、はい」
謎の男は、わたしの腕を掴んだまま、非常階段の踊《おど》り場へと連れて行った。
靴の音があたりに響く。
「すみませんね。ただ……このままでは、あなたがどんどん深いところに落ちて行ってしまうような気がして」
この声のリズムは……。
「マスター?」
わたしが尋ねると、彼は七三分けのウィッグをとり、マスクをとり、メガネを外し笑ってみせた。
あっけにとられていると、今度は革の靴《くつ》を脱ぎだす。
靴下《くつした》だけになったマスターは、さきほどよりも身長が低い。
「シークレットブーツというやつです」
マスターはこちらの心境を読んだように、そう言って満足げにうなずいた。
わたしもつられて、なるほど、と大きく首を振る。
……いや、そうじゃない。
「どうしてここに?」
「それは、企業秘密です」
人差し指をまっすぐ立てて、マスターは言った。
「あなたは、バーのマスターでは、ないのですか?」
「あれは表の顔です。私の本業は、いわば探偵業のようなもの。もっといえば、情報屋です」
「情報屋?」
だから、たまに怪しいお客さんがきていたのか!
わたしは妙に納得した。
「そうです。それでですね、率直《そっちょく》に申し上げると、あなたをスカウトしたいのです」
「え?」
「おや? 驚きましたか?」
「驚いたもなにも、どうして? わたし、そんな難しそうなこと、できません。学歴だってないし、美人じゃないし、人と仲を深めることだって得意じゃない。情報をとってくるだなんて、とてもとても……」
「ふむ。スカウトの理由、ですか。そうですね、ひとつは、あなたの人を追いかける熱意。ふたつめは、ある程度のことをなんでもこなせる器用さ。この能力に魅せられた、といえば納得してもらえるでしょうか」
マスターの言うことは、決して的外れではないと思った。
どちらも、自覚している。
「それは、そうかもしれませんけど、いきなり情報屋だなんて言われても……」
「もちろん、報酬は保証します。おそらく、今よりもずっといい暮らしができるでしょう。なにより、あなたは自分を最大限に活かせる場所に身をおける。悪い話ではないはずです」
たしかに、幸せを追いかけて職を変え続けるより、ずっといい。
「あの……。わたし、けっこう突っ走りますよ?」
「ええ。知っていますとも」
「もうすぐ、五十歳になります」
「年は関係ありません」
「ぜんぜん愛嬌《あいきょう》もないです」
「ポーカーフェイスくらいがちょうどいい」
わたしの言葉に、マスターはポンポンと答えていった。
どれも、なんてことない質問だとでもいうかのように。
「……お願いします」
そう口にしたとたん、わたしは肩の力が抜けるのを感じた。
それは、ずっと、抱えていた大きな荷物を下ろせたような感覚だった。
ほっとして、その場に座り込む。
非常階段の踊り場は、薄暗くて、ひんやりとしていて、そこにシークレットブーツが並んでいるのが、なんだかおかしかった。
「さて、では行きましょうか。いろいろと手続きを済ませなくては」
マスターは、ふたたびシークレットブーツに足を突っ込むと
座り込んだままのわたしへと右手を差し出してくれた。
手をとり、立ち上がると、さきほどよりうんと体が軽い。
生まれ変わったみたいだ。
「このまま、会社、抜けるんですか?」
「ええ。あとのことはお任せください。そういうのは得意ですから」
マスターは、さらっと言った。
「へえ」
わたしはマスターのあとを追いながら、声を漏らした。
「ああ、そうだ。 かえったら乾杯《かんぱい》しましょう。新たな|天職《てんしょく》との出会いにね」
「天職?」
「そうですよ。私はずっと、そうじゃないかと思って、あなたの様子をうかがっていました。ときにはスーパーで、そしてときにはビルのなかで」
「ずっと、追いかけてたんですか?」
「ええ、まあ」
「まったく気づかなかったです」
「そりゃ、私もプロですから」
マスターは悪びれもなく言った。
「ふふ。わたしも頑張らなきゃ」
「コツをお伝えしますよ。きっと、すぐ習得できます」
わたしは次の職に思いを馳《は》せた。
今までの、男性という名の幸せを追いかける仕事とは違う。
「ふふふ」
思わず笑みがこぼれるくらい、心の底から楽しさがこみあげてくるような気がした。
思っていた形とは異なるけれど、
そこには、今よりもずっと充実した毎日があるような気がした。
完