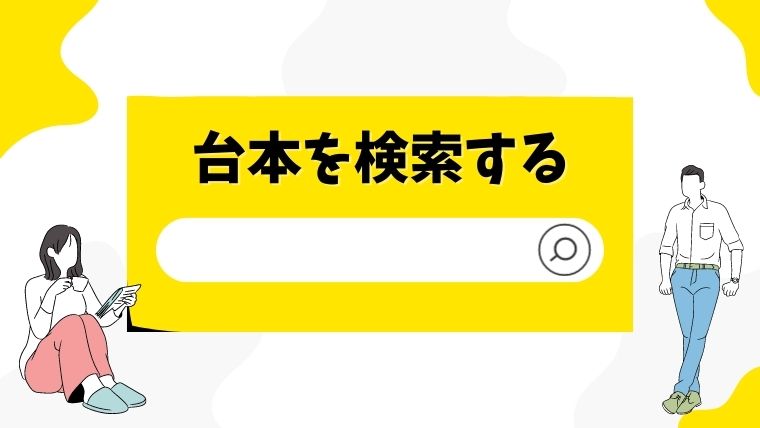【朗読台本】ちっぽけな町の道端で【30分~40分】

●使用料:無料
●利用報告:商用のみ要(非商用は任意)
●クレジット表記:必須
ー表記内容ー
| 台本名 | 当ページのタイトル |
| 作者名 | 紺乃未色(こんのみいろ) |
| サイト名 | フリー台本サイト「キャラコエ」 |
| 台本URL | 当ページのURL
※リンク付け(URLをクリックすると、当ページに飛ぶように設定すること)必須 |
上記4点を必ず表記していただきますよう、お願いいたします。
利用のルールについては、利用規約をご覧くださいませ。
概要
| カテゴリ | 朗読(一人) |
|---|---|
| ジャンル | 現実世界 |
| 時間(目安) | 30分~40分 |
| あらすじ | ユキは六年ぶりに姉に電話をかける。 暮らしぶりが悪くなり、しかたなく実家に帰るためだ。 |
| 注意 | このストーリーはフィクションです。実在する人物や団体、出来事などとは一切関係がありません。 |
その他、朗読におすすめの台本は、以下のページにまとめています。

フリー台本『ちっぽけな町の道端で』
九月の上旬、わたしはスマートフォンを握りしめていた。
呼び出し音が鳴る。
一回、二回、三回……。
ええい! やっぱり切ってしまおうか。
そう思ったときだった。
「あら、珍しいわね」
わたしよりも二つ年上、今年三十歳になるお姉ちゃんの声がした。
「あー、うん。久しぶり」
「なにか、あったの?」
実家を出てから、六年間も顔を見せずにいた妹が突然連絡をよこしたら、誰だってそう思うだろう。
「ちょっとさ、そっちに帰ろうかと思ってて」
「……そう」
お姉ちゃんは短く相槌を打った。
「それで、しばらくはそっちにいると思う」
「わかったわ」
なんにも聞いてこないのが、彼女らしいと思った。
「よろしく、お願いします」
なぜか敬語になる。
「ふふ。ユキったら、どうせお母さんたちには、まだ伝えてないんでしょう」
「うん」
なにもかも、お見通しらしい。
「じゃあ、私から言っておくわよ」
子どもの頃、お姉ちゃんは、いつもこんな風にフォローしてくれたっけ。
ふいに蘇ってくる記憶を、どこかへ振り払うように首を振った。
「ねえ、お姉ちゃん。お母さんたち、怒るかな?」
二十八歳とは思えないくらいの幼い口調だった。
「え? どうして? むしろ、喜ぶと思うけど」
「そうかな。ほら、けっこう、一方的に出て行ったから」
「ふふふ。ええっと、なんだったかしら。「わたしはこんなちっぽけな町なんかにいたくないの。小さな世界しかしらないお母さんたちみたいになりたくない」だったかしら?」
その通りの言葉だ。
「あと……。ああ! そうだわ。「もっと広いところに行って、いろんなものを見て、成長したい。家にいてばかりのお姉ちゃんとは違うの!」とも言ってたかしら」
「……根に持ってる?」
「私? とくに気にしてないわ」
「嘘」
「どうしてそう思うの?」
「だって、わたしが言ったこと、そのままそっくり覚えてるから」
「……そりゃ、最初の一年くらいは、イラつきもしたわよ」
「そうだよね」
「ふふ。なあに? ユキ、反省してるの?」
お姉ちゃんが楽しそうに尋ねてくる。
「ちょっと、言い過ぎたかもって」
「まあ、あのときはみんな、ユキを引き留めたくて、必死だったのよ。そりゃ、あなただって、反発したくもなるわよ」
「だって、もう二十二歳だったのにさ、危ないから都会での一人暮らしはダメだとか、|過保護すぎるでしょ」
「たぶんだけど、あのときは寂しかったのよ。ほら、あなたって、うちのムードメーカーみたいな存在だったから」
「そうなのかなあ?」
あんまりピンとこなかった。
「まあ、もう過ぎた話よ。ユキは何も心配せずに、帰ってくればいいの」
「そう、思いたいけどさ。あー、うん。わかった」
わたしは、引っ越しの日程を伝え、電話を切った。
勢いよく家を出た日のことは、つい最近のことのようにも思えるし、ずいぶんと昔のことのようにも感じられる。
べつに、家族のことが嫌いだったわけではない。
「小さな町の片隅(かたすみ)で人生を終えたくない」だなんて、映画の主人公みたいな心境になっただけだ。
恋人と歩いていれば、翌日には両親の耳に入る。
町のショッピングモールに行けば、三組は知り合いに会う。
そんな、狭い世界から出たいと思ったのだ。
小説やドラマによると、世界はもっと広いらしい。
わたしはそこに行きたかった。さまざまなものを見て、いろんな人と知り合い、自身を成長させて、刺激的な生活を満喫するはずだったのだ。
「あー、もう!」
結果、このありさまだ。
六年前、入社したIT系の会社は、ぐいぐい波に乗っている最中だった。
ところが、ここ一年で一気に坂を転げ落ち、社員はほぼクビになってしまった。
正直なところ、当初、わたしは例外だと思っていた。
「風野(かざの)さん、申し訳ないけれど、来月いっぱいまでで」
上司からそう告げられたときは、驚いたし、頭で考えるより先に言葉が飛び出していた。
「え! どうしてです?」
「……どうしてって、今の会社の現状をわかっているだろう? なにも、君だけじゃない。みんな一緒だ」
その言葉を聞いたとたん、頭にカッと血が上った。
「みんなって、そのなかに、わたしも入るんですか?」
「ああ、そうだよ」
「そんな! わたし、いつも、一番早くに出社してました。誰とは言いませんけど、他の人がサボってるときも、その分カバーしていたつもりです。……ミスだって少なかったはず。ご存じですよね?」
「会社がこの状態じゃ、残すわけにはいかないんだ」
上司の顔は疲れ果てているようで、わたしは、小さく頷くしかできなかった。
数日後、あえて名を伏せた、サボりがちな同僚がクビにならずに済んだと聞いたときの腹立たしさは一生忘れないだろうと思っている。
そんなことがあり、あっけなく職を失ったのだ。
それでも、少し気持ちに余裕があったのは、彼氏と呼べる存在がいたから。
しばらく、彼に甘えよう。
そんな期待を裏切るように、その一言は告げられた。
「ごめん。別れてほしい。君より好きな子ができたんだ」
「は? なんなら、二股でもいいんだけど。どうせ本命の奥さんはべつにいるんだし!」
「そういうわけにはいかない。僕の中にもルールがある」
「なによそれ! 都合のいいこと言っちゃって」
頭で考えるより先に、言葉はつらつらと飛び出してくる。
彼は感情的になって、罵声を浴びせてくるだろうか、それとも殴るだろうか。
「すまない。べつに、ケンカをしたいわけじゃない。ただ伝えに来ただけなんだ」
わたしの予想を裏切り、彼は淡々とそう言った。
それがすべての答えだと思った。
いまだに、スマホを何度も手にしてしまうのは、彼からの電話やメッセージを待っているから。
ところが連絡は来ない。
彼どころか、誰からもなにも届かない。
乾いた笑いが漏れる。
今の自分がみじめで悲しい。
もう、いいんだ。このあたりで実家に帰って、もう一度、スタートを切ろう。まだ、二十八歳。できることはたくさんある。
わたしは自身を励まそうとした。
未来のことを考えると、ちょっぴり気持ちが晴れることを知っている。
次は、どんなところへ引っ越そう。
海の近くがいいかもしれない。
ドラマティックな景色を思い浮かべると、うっとりする。
ふいに、自身が家族へ告げた台詞を思い出した。
「わたしはこんなちっぽけな町なんかにいたくないの」
たしかに言葉をストレートにぶつけ過ぎたとは思っている。
でも、わたしの考えそのものは変わっていない。
あの町でずっと変わらず、のんきに暮らしているお姉ちゃんたちみたいになりたくないんだ。
手に馴染まないカギを差し込み、おそるおそる玄関の扉を開けた。
「おかえりなさい」
パタパタという足音とともに出迎えてくれたのは、お姉ちゃんだ。
その姿があまりにも不自然なものだから、わたしは「えっ?」と声を上げ、三十五万円のハンドバッグを落としそうになった。
「ユキ?」
「なに、そのダサい感じ!」
彼女が身につけているのは、高校のときに使っていた体操服だ。
胸元には、「風野(かざの)」という名字が、くっきりと刺繍(ししゅう)されている。
「ああ。これ、動きやすいのよ。残っててよかったわ」
昔から、お姉ちゃんはよれよれのスウェットや、スポーティなジャージとは、無縁の人だったはずだ。
「え、どうして、そんな恰好(かっこう)してるわけ?」
「ここ数日、ずっと掃除してるのよ。物置になっていたあなたの部屋を綺麗にするためにもね。もう少しで、終わるわよ」
「え? それ、お姉ちゃんがしてくれてるの?」
「ええ。なあに? 私がしちゃ、ダメなの」
「そういうわけじゃないけど」
わたしの記憶のなかのお姉ちゃんは、わがままなお貴族様だ。
宅急便が届いても、ダンボールなんて持とうともしないし、そもそも一人で留守番しているとき以外は、インターフォンにも対応しない。
実家で暮らしているくせに、掃除やら、洗濯やら、家のことにはノータッチだ。
仕事のない日は、マイペースに本を読み、紅茶を飲み、音楽を聴いている。
わたしはそんな彼女をひそかに馬鹿にし、こうはならないでおこうと心に決めていた。
それなのに……。
なぜ、似合わない服を体に装着して、作業に精を出しているのだろう。
「まあ、いいわ。とりあえず、入ったら?」
わたしはお姉ちゃんにお土産を手渡し、ゆっくりと足を進めつつ、人の気配を感じようとする。
「あ、お母さんたち、出かけてるわよ」
「そうなんだ」
肩の力が抜けて、呼吸が楽になる。
「今は、私だけよ」
「え、待って。……お母さんたち、二人で一緒にいるの?」
「そうよ」
ぶったまげた。
「そんなに、仲良かったっけ? いや、むしろ悪くなかった? ケンカすると、家の中、ピリピリしてたでしょ。あの空気、なんとかするの大変だったもん。……どうして?」
「さあ。あらためて聞かれるとよくわからないけど、年を重ねて丸くなったんじゃない? それにお母さん、ここ数年、膝の調子が良くないのよ」
「え、それ、大丈夫なの?」
「歩けてはいるけど、ちょっと辛そうなの。それでいて、お父さんは腰をやられてるわ。今じゃ、重いもの持つのも、玄関の電球変えるのも、私の担当よ。危なっかしくて見ていられないんだもの」
あのお姉ちゃんがそこまでしているということが、すべてを物語っている。
「……二人ともぼろぼろなんだ」
「そりゃ、年齢的にねえ。それで、お父さんったら、ちょっと人の痛みがわかるようになったみたいでね、お母さんにずいぶんと優しくなったのよ」
「へえ。あんまり想像つかないけど」
お父さんは、とにかく頑固(がんこ)な男だ。
自分の言ったことが、たとえ誤りだったとしても、意見を曲げようとしない。
いつも、タヌキの置物みたいに茶の間に座り、料理やお茶が目の前に運ばれてくるのを待っていた。
「そうでしょうね。今、お父さん、料理までするんだから」
「ええ?!」
「本当よ。もともと、凝り性な人ではあるでしょう? それが上手くマッチしたみたいでね。もしかしたら、私よりも包丁さばきが上手かも」
信じられない、と口にしようとしたとたん、玄関の方で物音がした。
わたしは、おろおろしながら、お父さんとお母さんのいるであろう場所へと向かった。
「えっ」
ただただびっくりした。
わたしの記憶のなかの二人とは、姿かたちがすっかり違っていた。
たったの六年しか経(た)っていないはずなのに、体は小さくなっているし、髪は白くなっている。
顔には彫刻刀で掘ったようなシワがあるし、お母さんの片手には杖が握られていた。
目の奥が脈打つ。
わたしは、子どものように大声で泣き喚きたくなるのをぐっと堪えた。
「あら? おかえりなさい」
お母さんが笑った。
懐かしさを噛みしめるような表情は、いまにも歪みそうで、とっさに視線を逸らしてしまう。
わたしは「うん」と一言だけ返して、慌しく部屋へと籠った。
一人になって泣いていると、お姉ちゃんがティッシュの箱を片手にあらわれた。
ノックくらいしてよ、という言葉よりも先に、手が箱へと伸びる。
「落ち着いたら、でてきてね」
わたしはティッシュで水っぽいハナを噛みながら、大きく頷いた。
いつまでも、涙は止まらなかった。呼吸が浅くなり、ときどき、しゃくりあげずにはいられない。
六年という年月の重みを感じながら、わたしはどんどん苦しくなった。
一時間ほどして、茶の間へいくと、三人の視線が一気にこちらを向いた。
一瞬、シンとした空気が流れる。
とても気まずい。
「ユキ。よく、帰ってきたな」
お父さんの声は、とても穏やかだった。
「……うん。ただいま」
「ふふふ。今日は、カラアゲとシチュー、両方作るわよ。……お父さんが」
お母さんは大袈裟に、両手をお父さんの方へと向けた。
「さすがに、一人では時間がかかる」
彼はぶっちょう面で言った。
「冗談よ。手伝うわ。あたしも」
お父さんは、納得したのか「ならいい」と口にしてお茶を啜った。
もうずいぶんと、食べていない大好物たちを思い浮かべると、自然と頬が緩くなる。
そこでわたしは、ここ数年、食生活がひどく乱れていたことを思い出した。
ひとまず、帰ってきて良かったのかもしれない。
いまだにぐちゃぐちゃの心境のなかで、ぼんやりとそう感じた。
「ユキ、こないだより、雰囲気が柔らかくなったわね」
お姉ちゃんからそんなことを言われたのは、お母さんから頼まれて、郵便局へと向かっている最中だった。
畑のあいだをぐねぐねと続く一本道を進みながら、彼女はちらりとこちらを見てくる。
「そうかな?」
「帰ってきたばかりのときは、どうしたのかしらって思うほど、尖ってたわよ。といっても、ほんの一週間前だけれど」
「そりゃ、さんざんな……」
状況になったばかりだったから、と伝えようとして声が出なくなった。
わたしがピリピリしていたのは、もっと前からじゃないだろうか。
とにかく、イライラすることばかりだったから。サボりがちな同僚、増える残業、なかなか連絡をよこさない彼……。
どれも、我慢していたのに、最終的にはすべてなくなってしまった。
「どうしたの?」
「ううん」
「……あ! ほら、あそこ新しく、タイ焼き屋さんができたのよ」
お姉ちゃんは、畑の先、何十メートルも先に見える黄色の光を指差した。
「へえ」
「けっこうおいしいのよ」
変わったんだなあ、と思った。
そのお店だけじゃない。
この町には、六年前とは異なる場所がたくさんあった。
田んぼの隣には、見知らぬケアセンターが立っているし、昔通っていた学習塾はなくなり、代わりにコンビニが、昔からそうしていたかのように客を迎え入れている。
「なんか、いろいろ前と違うね」
街の風景だけじゃなく、風野(かざの)家も……という言葉はぐっと飲み込む。
変わっていないのはむしろ……。
「そりゃ、六年もあったらね」
「……そうだね」
わたしのテンションを悟ったのか、お姉ちゃんはだんまりを決め込み、足を進めた。
空はオレンジ色に染まり、どこからか童謡のピアノ音楽が流れてくる。
昔、この曲が流れると、こうやってお姉ちゃんと並んで歩き、公園から家へと帰ったっけ。
しみじみと過去に浸ってしまうのは、懐かしいメロディのせいだ。
お姉ちゃんも覚えているのだろうか。視線を隣へ向けると、ばっちりと目が合った。
「さすがに、ユキが何を考えているのかまでは、はっきりわからないけれど……」
彼女は、ぽつりとなにかを伝えようとした。
「なに?」
「……また、家を出て、どこかに行きたいんでしょう?」
たしかに、そのつもりだった。
わたしは煮え切らない返事をした。
ふいに、道のはしっこ、草むらの陰にあるセミの死骸が目に入る。
こんなの、ありふれた光景で、昔から見慣れているはずのものだ。
それなのに、どうしてか気になった。
「その様子じゃ、いくら元気とはいえ、前よりも弱ったお母さんたちを見たせいで、家を出るのためらってるんじゃないの?」
お姉ちゃんは静かに言った。
図星(ずぼし)だった。
「そりゃ、気にならないって言ったら嘘になるけど……」
「ほら、私もいるでしょう? 家のことだって任せて」
お姉ちゃんにしては珍しく、早口だった。
わたしは、ジャージ姿のお姉ちゃんを思い出した。
「あはは。前と違って、ちゃんと動いてるもんね」
「なあに? ユキったら、人をミノムシかなにかとでも思ってたの?」
「うん。前はそんな感じだったもん」
「ふふふ。たしかにね。それで、なんの話だったかしら。あー、そうそう。ユキは自分が思うようにやればいいのよ。あなたのことだから、なにかあるんでしょう?」
新幹線のなかで、描いていた未来を思い浮かべる。
あのときは、くっきりと映っていたはずのキラキラした映像が、今は、|仄暗《ほのぐら》いベールに包まれている。
「あるにはあるけどさ」
「なら、すればいいのよ。いいわね? はい、返事は?」
「……」
「昨日、お母さんたちも話してたわよ。ユキは自分の人生、思いっきり楽しんで欲しいって。ほんとよ」
お姉ちゃんはなんでもないことのように、そう言ってのけた。
「……そんな風に、簡単に言うなんて」
「なあに? 年齢を重ねて、家を飛び出したときほどの、勇気はもうなくなったのかしら?」
「そうじゃない!」
大きな声に驚いたのか、近くにいたスズメたちが一斉に空へと飛びあがった。
「ユキ?」
わたしはその場で動けなくなった。
全身が熱くなり、体内の水分が逆流してくる。
「ど、う、して。なんで……そこまでしてくれるの?」
わたしは、震える唇で、必死に言葉を紡ごうとした。
「ええっ?」
お姉ちゃんが素っ頓狂(すっとんきょう)な声を上げる。
「ねえ、どうして? わたし、勝手に家出て行って、自分の都合(つごう)のいいときに帰ってきたんだけど! 理由だって説明してないし!」
「だから?」
「そんな風に扱ってもらえる価値なんてない!」
わたしは仕事を頑張った。
彼のためにつくした。
それでも、悲しい結末だけが残ったのだ。
お父さんには、お母さんには、お姉ちゃんには、なんにもしていない。
それなのに、どうしてわたしのことなんかを考えてくれるんだろう。
「……べつに、理由なんてないわよ」
「そんなんじゃ、納得できない!」
「さっきから、泣いたり、怒ったり、忙しいわね」
いろんな感情が忙しなく巡るものだから、頭のなかはパニック状態だ。
「うるさい!」
わたしは、八つ当たりするように言葉を吐き出した。
そのまま、しゃがみこんで泣いた。
近くで犬が吠えても、虫がリンリン鳴いても、気にせず、地面をぽたぽた濡らし続けた。
「ちょっとそこにいて」
彼女は、小走りで郵便局へと入って行く。
いつの間にか、目的地のすぐそばまでたどり着いていたようだ。
秋の風が頬を撫でる。
冷たい、と感じた。
熱くなった頭が一気に冴えていく。
わたしは立ち上がり、歩いて来た道を振り返った。
なくなった仕事のこと、去っていった彼のこと、もどかしい日常……。
次々と、浮かんでくる。
どのくらいの時間が経(た)っただろうか。
「お待たせ!」
後ろから声を掛けられ、意識がはっとする。
「早いね」
思ったよりも、声がかすれている。
「そう? あ、ミナちゃんのお母さんいたわよ。郵便局で働いてるのよね」
「あ、ミナちゃんか。そういえば、毎年、あけおめの連絡くれるなあ」
「……ユキ、それ、ちゃんと返してるんでしょうね?」
「うん。さすがにね」
といいつつ、今、名前を出されるまで、すっかり存在を忘れていた。
昔はよく、遊んでいたし、勉強のよくできる彼女に、数学を教えてもらうこともあったのに。
「なら、いいけど。ユキちゃん元気? って聞かれたから、はいって言っといたわよ。さすがに、今、泣いてますなんて言えないもの」
お姉ちゃんが笑った。
「ありがと」
「いいのよ。……それで、さっきの返事は?」
「……うん」
「うんではありません。わかったら、元気よく「はい」と言うように」
お姉ちゃんは、小学校のときにお世話になった、独特なトーンで話す先生の声を真似た。
身内ネタだが、わたしたちのなかでは、鉄板の話題だった。
「あはは! 今は反則!」
「ふふっ。返事は?」
「はい! でも、もう少しは家にいようかな」
お姉ちゃんは想定外だとでもいうように、首をかしげる。
「あ、べつに遠慮してるわけじゃないから。ただ、ちょっと、いろいろ疲れたからさ。もう少し家で過ごすのも悪くないなって」
心を休ませたい。それは、本心だった。
わたしは、あたりをぐるりと見渡した。
そこにはただ、静かな空気と畑が広がっている。
遠くに並んでいる家々は点々と光り、ありふれた生活感を醸し出していた。
住宅街のはるか後方には、太陽が沈んだばかりの山がそびえ立っていて、あれを越えると、違うエリアになる。
「どうしたの?」
「ううん。この町ってさ、小さいよね」
「まあ、そうね」
「……もうちょっとよく、見てみようかな」
新しく、スタートを切るのはそれからでも遅くない。
わたしはちっぽけな町の道端でそんなことを思った。
「え? 町を? どういうこと?」
お姉ちゃんがあたふたする。
「あはは! なんでもない」
「ちょっと、ユキ。どういうことよ?」
わたしは笑ってごまかしながら、家へと続く道へと、大きく一歩踏みだした。