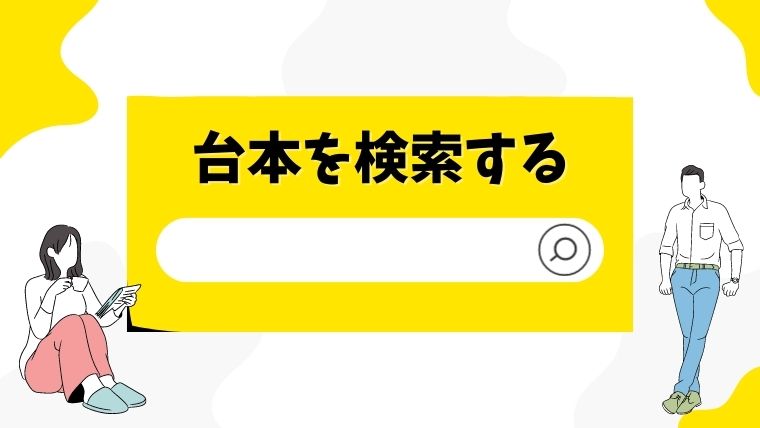●使用料:無料
●利用報告:商用のみ要(非商用は任意)
●クレジット表記:必須
ー表記内容ー
| 台本名 | 当ページのタイトル |
| 作者名 | 紺乃未色(こんのみいろ) |
| サイト名 | フリー台本サイト「キャラコエ」 |
| 台本URL | 当ページのURL
※リンク付け(URLをクリックすると、当ページに飛ぶように設定すること)必須 |
上記4点を必ず表記していただきますよう、お願いいたします。
利用のルールについては、利用規約をご覧くださいませ。
概要
| カテゴリ | 朗読(一人) |
|---|---|
| ジャンル | 現実世界 |
| 時間(目安) | 15~20分 |
| あらすじ | 「わたしは、たまごから生まれました」坂見ユリナのその発言は、美術室をどよめかせた。 |
| 注意 | このストーリーはフィクションです。実在する人物や団体、出来事などとは一切関係がありません。 |
その他、朗読におすすめの台本は、以下のページにまとめています。

フリー台本『たまご宣言』
1
「わたしは、たまごから生まれました」
坂見(さかみ)ユリナがそう言ったのは、中学校での美術の時間のことだった。
そのときのテーマは「誕生」で、生徒たちは思いつくままに筆を走らせていた。
授業は二週にわたっておこなわれ、トータル4時間。そのうちの1時間は、一人ひとりが黒板の前に立ち、自分が描いた絵について、クラスメイトに発表する。
みんなの絵は、家の花壇で見つけた青々しい芽だとか、生まれたばかりのイルカの赤ちゃんだとか、地球のはじまりだとか、そんな感じ。
ぼくはというと、イチゴのバースデーケーキ。
どうしてって、一週間前に、誕生日を迎えたばかりだったから。珍しく、デパ地下のケーキショップで、お母さんが買ってきてくれたんだ。
あまりにおいしかったからか、「誕生」と聞いても、これしか思い浮かばなかった。
それで、坂見ユリナがたまごから生まれたと宣言したとき、あたりまえだけど、美術室はざわついた。
午後の気だるさに身を任せ、机に伏せていた生徒たちは、面白いくらいおんなじタイミングに顔を上げた。
とっさに下を向いて、笑いをこらえているのか、肩を震わせている子もいた。
一番うしろの席って、そういう教室の雰囲気がぜんぶ見えるんだ。
「あ、あの、ええっと、坂見さん?」
美術の先生は、画用紙のまんなかに描かれたたまごの絵を見ながら声をかける。
それは、絵の具で書かれたとは思えないくらいに、ちゃんと質感があった。
カラの堅さと冷たさがありありと感じられる。
そのたまごは、心を閉ざし、あたりを警戒しているようにも思えた。
「本当です。それで、たまごを描きました。テーマが誕生だから」
坂見ユリナは、画用紙を体の横で広げ、美術室のすみからすみまでぐるっと見渡した。
彼女のまなざしとたまごの鈍いテカり加減には、ゆるぎない主張がこめられているようだった。
ぼくは「この人、いったい何を言ってるんだ?」と呆れながらも、そのたまごの絵から目が離せなかった。
「そう。た、たしかにたまごは誕生っていうテーマにもぴったりね。うん、そうね、いいと思うわ」
美術の先生は、歯切れが悪そうに感想を言うと、すぐに次の生徒の名前を呼んだ。
坂見ユリナはひとつうなずき、画用紙を抱きかかえるようにして、静かに席に戻った。
正直、そのあとの発表者のことは、あんまり覚えていない。
坂見ユリナの言葉は、その日のうちに、ほかのクラスにも広がっていったらしい。
「なあ。坂見ユリナ、なんでそんなこと言ったんだ?」
テニス部の更衣室で、部活仲間が尋ねてくる。
「そんなの、ぼくに聞かれてもわかんない」
「お前、同じ、クラスだろ? なんか、まわりが言ってねえの?」
「さあ。坂見さんと仲の良い子たちが、教室戻るときに聞いてたけど、彼女、首を横に振るだけだった。誰も理由なんて知らないんじゃないの?」
「ふうん。べつにあいつ、不思議ちゃんって感じでもないのにな」
「そうだね」
坂見ユリナは、とくに目立つタイプでもなければ、とくべつ大人しいタイプでもない。
表情はわかりにくいけど、笑うことだってあるし、友達と会話もする。
どこにでもいそうな女子中学生だ。
それがかえって、たまご宣言のおかしさを際立たせていた。
2
たまご宣言から一ヶ月か二ヶ月ほどが経った頃、ぼくはショッピングモールで坂見ユリナの姿を見かけた。
まさにばったり!
坂見家と鉢合わせたのだ。
「あら、坂見さん。ご無沙汰しております」
母さんは、相手の父親と知り合いらしく、よそゆきの声でそう言った。
「ああ、佐藤さん」
日に焼けていて健康そうな人だった。
その隣にいるのは、高いヒールを履いた女の人で、すらりとした両手を坂見ユリナの父親にからませている。
その二人の後ろを、坂見ユリナは捨てられた子犬のように歩いていた。
「おはよ」
ぼくは、なにも話さないのもどうかと思い、声をかけることにした。
「……おはよ」
少しの間のあと、たしかに坂見ユリナはそう言った。
彼女の黒々とした瞳がこっちを見ている。
ところが、たまご宣言をしたときのような強さはそこにはなかった。
あのあと、美術室に置き忘れてしまったのだろうか。
そう思うほどに、力も光も宿っていないように思えた。
ぼくたちは軽くあいさつを交わしたものの、すぐに沈黙がやってくる。
これは気まずい。
そういえば、坂見ユリナと一対一で話をするのは初めてかもしれない。
そうこうしているうちに、母さんは立ち話を終えたらしい。
ぼくたちは、坂見家から遠ざかっていく。
「坂見さん、再婚されたのね。まあ、あの人、まだ彼女かもしれないけれど」
母さんが言った。
「もともと、父親だけしかいなかったの?」
「そうそう。お母さんは、小さい頃に家を出て行ったって……。小学校も一緒だったでしょ? なにかの集まりのときに、坂見さん本人から聞いたのよ。まあ、べつに、いまどき離婚っていうのも、珍しくはないわよね」
「へえ」
初耳だ。
「ただねえ……」
母さんは何かを言おうとして、口を開き、すぐに閉じた。
言葉にださなくても、ぼくにはなんとなくわかる。
そこまで馬鹿じゃない。
その日、ぼくの頭の片隅には、女の人がまとっていた甘ったるい香りがいつまでもへばりついて離れなかった。
あんまり考えたくないのに、嗅覚が勝手に反応してしまうのだ。
もどかしくって、もやもやする。
坂見ユリナは、ひょっとして、毎日がこんな感じなのだろうか。
3
そんなことがあってから、何日かが過ぎた頃、知らない人たちが、昼休みの教室にやってきた。
「坂見さんだっけ? たまごから生まれたの。どの子?」
にたにたと笑っているのは、丸坊主の男子生徒。
たぶん、上級生だ。
「なになに? ひよこですってか? それとも爬虫類? どれどれ実物は?」
その隣で、金髪の学生がひゅるっと口笛を吹いた。
あたりがシンとする。
教室が息を止めたかのように思えた。
「わたしです」
坂見ユリナは、小さな声で言った。
「へえ。なんだ、普通の子じゃんか。あんた、たまごから生まれたってマジ?」
丸坊主の生徒がじろじろと坂見ユリナを見る。
「はい」
彼女はうなずく。
「んなわけねえだろう。お前、なんでそんなウソつくわけ?」
金髪がけらけら笑うと、坂見ユリナは両手をぎゅっと握り締めた。
「本当です! わたしは、たまごから生まれたんです!」
静かな教室に、坂見ユリナの大きな声が響き渡る。
二人の男は顔を見合わせると、面白いものを見つけたとでもいうように、坂見ユリナに近づいた。
彼女は後ずさることもなく、まっすぐに前を見ている。
その瞳に、なにが映っているのか、ぼくからは確認することはできない。
「ふうん。じゃあさ、そのたまごはどっからきたわけ? 誰かが生んだんだろ?」
丸坊主が言った。
坂見ユリナは黙った。
「答えられないってか? そりゃあ、そうだろうな。ウソだもんなあ」
金髪がほらみろとでもいうように、肩をすくめた。
「たまごは……」
坂見ユリナがなにかを言いかける。
「ん? なんだ? 言ってみろよ」
丸坊主が挑発する。
「たまごは、わたしそのものなの! 最初から! だから、誰かが生んだわけでもないんです!」
「は? なにいってんだ?」
「頭、大丈夫か? 話通じてないと思うんだけど」
二人の男子生徒の言葉には、ぴりぴりとした感じがあった。
すでに面白いを通りこして、怒りになっているんじゃないかって気がした。
「ほ、本当です!!!」
そう言ったのは、坂見ユリナじゃない。
ぼくだ。
教室にいたみんなが、一斉にこちらを向いた。
もちろん、坂見ユリナと二人の上級生も。
「なんだ、お前?」
「こいつの彼氏か?」
「違います! でも、坂見さんはたまごから生まれたんです!」
どうして、そんなことが言えたのか、さっぱりわからなかった。
声も指先もふるふると揺れている。
二人の上級生がぼくの方に近づいてくる。こ、怖い……。
そのとき、教室のあちこちから声がとんできた。
「彼女、たまごから生まれたんです!」
「本当です。あたし、聞いたことがあるから」
「先輩、実際に、たまごらしいっす!」
「おかしな話かもですけど、そういうこともあるんです」
「人間がたまごから生まれるってこともあるでしょう。21世紀ですから」
坂見ユリナとよく一緒にいる女子生徒だけでなく、普段まったく接点のない子、勉強にしか興味がないって感じの田村までもが、彼女の意見をさも当たり前かのように肯定した。
みんな、彼女のことを助けようとしたのか、それとも自分たちの平穏な昼休みを取り戻したかったのかはわからない。
それでも、そのとき1年2組は、まるっとひとつになっていた。
「こ、このクラス、おかしいんじゃねえの?」
「おい。もういこうぜ、こっちまで気が狂いそうになる」
二人組の上級生は、漫画にでてきそうなセリフをはいて、そそくさと去って行った。ここにやってきたときのような威勢はなくなっていて、けっこう、まぬけに見えた。
教室は、やっともとの動きや音をとりもどす。
坂見ユリナは小さく「ありがとう」と呟いて、自分の机に戻って行った。
ぼくがたまご宣言について、ちゃんと覚えているのはここまでだ。
4
中学校を卒業した後、坂見ユリナは祖父母の家に行ったと、母さんが言っていた。
そこから高校に通うことになったらしい。
人の家の事情はよくわからないけど、それでよかったような気もする。
それから、ぼくたちは社会人になり、なんと再会を果たすことになる。
彼女は取引先のWEB(ウェブ)クリエイト部に所属していて、ぼくの勤めていた会社は、デザインの依頼をする側だった。
会議室に入り、彼女の顔を見たとたん、ぼくの頭のなかでは「たまご宣言」という名のムービーが、ものすごいスピードで再生された。
「あ!」
坂見ユリナは、目を軽くひらいて、イスから立ち上がった。
ぼくのことを覚えているらしい。
でも、たまご宣言のことを記憶しているかどうかまではわからなかった。
5
オムライスの香りに意識がふっと我に返った。
キッチンの流し台で、泡の落ちたスポンジをもったままの自分に気づく。
「もう、できるわよ。大丈夫? なんだか、ぼうっとしてるわよ?」
「あ、ごめん。お皿、すぐ出すよ。あとスプーンとケチャップも」
ぼくは水をとめると、タオルで手を拭き、食器棚のところへと移動した。
ちらっと振り返り、ユリナの姿を盗み見る。
会議室での再会を果たした後、ぼくたちは食事を重ね、わりと早い段階で交際をスタートさせた。
そのニ年後に結婚をして、今は2LDKのマンションで一緒に暮らしている。
それぞれ、べつべつに部屋がほしいといったのは、彼女の申し出だった。
二人で時を過ごすなかで、ユリナが自分の両親について話そうとすることはなかった。
祖父母のことは、何度か話にあがったし、結婚報告をするために家を訪れたこともある。
ぼくは、あえてなにも聞かなかった。
その代わり、少しでも彼女の過去が癒されるようにと、なるべく小さなひとときを丁寧に過ごすように心がけた。
桜の木に近づいて、一枚の花びらを二人並んで眺めたり、イチゴのバースデーケーキを切り分けたり、カフェオレを飲みながら、ふわふわの毛布に一緒に包まったりもした。
それでも、ユリナの本心が見えることはなかった。
それがちょっと寂しくもある。
少しでも、穏やかな気持ちになってくれているといいんだけど。
「さあ、冷めないうちに食べましょう」
ユリナが笑う。
「そうだね」
二人向き合い、テーブルで食事を終えた後、彼女は思い出したように口をひらいた。
「そういえば、先週もオムライスだったわね」
「え? ああ、あのときのはオムレツだったよ。タマネギとツナを入れたと思う」
タマネギが、やけに目にしみたから覚えている。
ぼく、ユリナの隣でぽろぽろと静かに泣いてたんだ。
「そうだったかしら? なんだか、最近、たまご料理が多いわね。飽きない?」
「ぜんぜん、ぼく、たまご好きだから」
「それならいいんだけど」
「君は?」
「わたし? そういえば、最近、なんだか好きなのよね。前はそこまで、たまごって好まなかったんだけど」
「……そうなんだ」
「なんでかしら? 急になのよね、たまごのおいしさに気づいたの。ほら、どんな料理にも使いやすいし、栄養もあるし、すばらしいわよね」
ユリナは、たまごの価値について、つらつらと楽しそうに話した。
ぼくの胸は、じんわりと温かくなった。
「それにね、たまごを使った料理って簡単だけど、おいしいの。そうだわ! あなたも料理を勉強中なら、まずはたまごからマスターするといいわよ」
「たしかに、それならなんとかできるかも」
ぼくはうなずく。
それから心のなかで決意した。
最初に食べてもらうのは、たまごをたっぷり使ったオムライスにしよう、と。