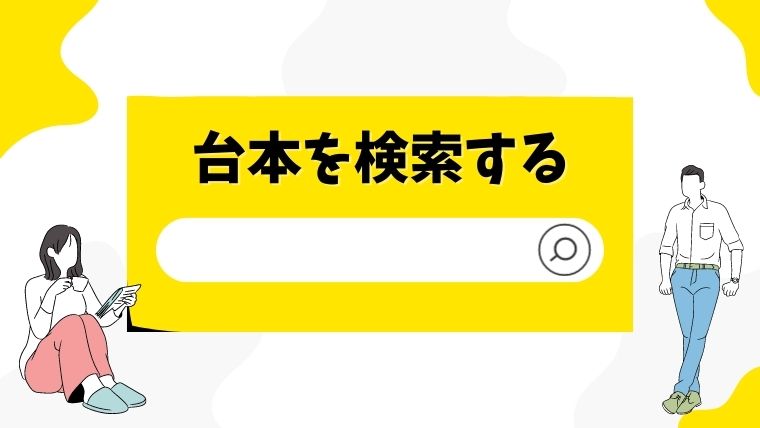【朗読台本】彼の名はソラ【10分~15分】

●使用料:無料
●利用報告:商用のみ要(非商用は任意)
●クレジット表記:必須
ー表記内容ー
| 台本名 | 当ページのタイトル |
| 作者名 | 紺乃未色(こんのみいろ) |
| サイト名 | フリー台本サイト「キャラコエ」 |
| 台本URL | 当ページのURL
※リンク付け(URLをクリックすると、当ページに飛ぶように設定すること)必須 |
上記4点を必ず表記していただきますよう、お願いいたします。
利用のルールについては、利用規約をご覧くださいませ。
概要
| カテゴリ | 朗読(一人) |
|---|---|
| ジャンル | 現実世界・奇妙 |
| 時間(目安) | 10分~15分 |
| あらすじ | 主人公はよくわからない空間にいた。目の前では謎の生命体が話している。いったい彼は何者なのだろう。 |
| 注意 | このストーリーはフィクションです。実在する人物や団体、出来事などとは一切関係がありません。 |
その他、朗読におすすめの台本は、以下のページにまとめています。

フリー台本『彼の名はソラ』
焼けつくような熱気とともに、地球最後の夏はやってきた。
ぼくの目の前では、謎の生命体がゆらゆらと動いている。
あたり一面には畳が敷き詰められていて、壁もしょうじも見当たらない。
いったい、ここはどこで、自分は何をしているのだろうか。
そんな疑問は、謎の生命体の声によってかき消された。
「ゆるさない」
「えっ?」
思わず、声を上げる。
「ここはもともと我のモノだ」
十三年間の人生のなかで、一度も遭遇したことのない出来事であることは間違いない。
SFやファンタジーの世界にいるみたいだ。
ほっぺたをつねってみると、じんとした痛みがあった。
「夢じゃない」
背中をイヤな汗が流れ落ちた。
なんだ、こいつは……。
怪し過ぎる。
そいつは、頭にヘルメットのようなものをかぶっていて、全身が黒い宇宙服のようなもので覆われていた。
いかにも悪役といった雰囲気だ。
「あの……、あなた、誰ですか?」
「答える義理はない」
そいつは低い声で言った後、こう続けた。
「ここを返してもらうぞ」
ヘルメットの中から睨みつけられているのを感じ取り、膝がふるふると揺れた。
今にもへたりこみそうになるのを必死でこらえる。
喉はカラカラだし、頭の中は白くぼんやりとした霧がかかっている。
倒れるかもしれない。
本能的にそう思った。
「まったく……。色々と破壊してくれたものだな。せっかく我が整備していたと言うのに」
謎の生命体が言った。
ぼくが何も言わないことに痺れを切らしたのか、やつはあたりをぐるりと眺めながら一人で話を進めていく。
「まあ、いい。また元に戻すだけだ」
「は、か、い? ぼくが?」
ようやく喉から絞り出した声はたどたどしく、目の前の生命体よりもよっぽど宇宙人のように思えた。
「ふん。わざわざ話すほどのことじゃない。とっくにわかっているだろう」
これまでよりも低い声だった。
ぼくは何も言えなかった。
この場を立ち去りたくて心の中で叫ぶ。
動け、動け。
呪文のように唱えてみても、相変わらず体はちっとも言うことを聞いてくれなかった。
「ほう。都合が悪くなったらだんまりか?」
やつはこちらのペースなどおかまいなしに脅迫するような口調で追いつめてくる。
じりじりと近づいてきたものだから、ぼくは思わず後ずさる。
ふいに、ちりん、というこの場に似つかわしくない音が鳴った。
「なんだ?」
「ほう」
やつは感心したような声を出した。
「何?」
「これは、我が一番好きな音だ。さて、何の音だと思う?」
突然、なぞかけをされた。
答えを導きだそうとするがまったくもって思い浮かばない。
「わかりません」
「まあ、そうだろうな。お前にとってはどうでもいい音だろう。でも我にとっては違う。この音によって癒され、幸せを得られるのだ」
さらに謎は深まった。
うんうんとうなってみても、やっぱり答えは出なかった。
いや、まて!
そもそも今はそんなことを考えている場合ではない!
ぼくは、左右にちらちらと視線をやった。
どこを見ても畳の世界が続いているだけで、自分以外の人はどこにもいないようだ。
……もしかしたらすでに地球はやつらに支配されてしまったのかもしれない。
「おい。聞いているのか?」
低い声が言った。
「はい」という返事は喉の奥につっかかり、意味のないくぐもった音となって空気中に零れる。
やけに冷静沈着な頭と、パニック状態の体。
ふたつが別々のいきものみたいだった。
どこからともなくお線香の匂いが漂ってくる。
それが、記憶の引き出しを刺激し、とある光景が浮かび上がった。
お墓参りだ!
花の添えられた墓石と、お線香。
ひょっとしたら、ぼくはもう死んでしまったのかもしれない。
いや、まだわからない。
だってちゃんと意識がある。
「あの!! ぼ、ぼ、ぼ、ぼくは、死んでる?」
舌がもつれて上手く言葉を発することができない。
「いや、まだだ」
やつは吐き捨てるように言った。
それなら、とぼくは思った。
「じゃあ! ぼ、ぼ、ぼ、ぼくたちは、その……どうなるん、ですか?」
一番の不安要素だった。
「どうだろうなあ。ただ消してしまうのでは面白くない。身勝手なおこないを反省するために、永遠に我の下で働いてもらおうか?」
やつはゆったりとした口調で言った。
その余裕にあふれたただずまいが、より恐れを感じさせる。
やつがさっき口にした「ここは元々我のモノ」という言葉が、頭の中でこだました。
本当かどうかもわからないのに、この謎の生命体と対峙していると真実であるかのように思えてくる。
洗脳されてはダメだ。
でも、こいつはウソをついているのだろうか。
わからない。
ただ……、ぼくはやつの話を聞いている時、身が小さくなる思いでいっぱいだった。
お弁当に入っていたニンジンをこっそりゴミ箱に捨てた時の気持ちに似ている。
これは、罪悪感だろうか。
「お前に選ばせてやろう。消滅するか、我のもとで働くか」
やつはそう言いながら、ぼくの方へと手を伸ばしてきた。
すぐに、ほっぺたがふにふにとした感触を感じ取る。
やつの手は意外にも柔らかく、そして温かかった。
いや、こんなことに感心している場合ではない。
「どっちもイヤです!」
精一杯の声を振り絞ったつもりだ。
ぼくとやつの間に少しの間、沈黙が流れた。
風すらも吹いてくれなくて、とても気まずい時間だった。
「ふむ。……それなら、ここから消えてもらおう」
もうダメだ。
ぼくはぎゅっと目をつむった。
死、という言葉の次に流れてきた映像は、なにげない日常の様子ばかり。
今さらながらに過去の幸せが身に染みた。
みんなはどこにいるのだろうか?
まあ、いいか。
どうせもう会えないのだから。
まさかこんな、意味のわからない最期を迎えるだなんて思ってもみなかった。
もっと遊びたかった。
そんな純粋な心残りが胸をくすぶってむしょうに泣きたくなった。
地球最後の夏はとても短かく、そして一瞬だった。
……みんな、さようなら。
それからどのくらいの時間が経っただろうか。
ぼくは違和感を覚えていた。
いつまでたっても意識が落ちてくれないのだ。
冷や汗が、全身をくまなく濡らして気持ちが悪い。
やるなら早くして欲しい。
じわじわといたぶるような趣味の悪い真似は止めてくれ!
ついに、こらえきれなくなって、薄らと目を開けてみることにした。
「うわああ!!!」
大きな声が出た。
やつの顔はヘルメットではなく、クロネコになっていた。
「ニャア」
「ニャア? あ、あれ? ここは……」
今度はまぬけな音が零れる。
クロネコの向こう側には、古びた天井があった。
ぼくは荒い息を繰り返す。
Tシャツのなかは、びっしょり濡れていた。
とにもかくにも助かった。
ここは、知らない場所じゃない。
いつのまにか止まっていた呼吸をゆっくりと再開する。
ようやく全身の力が抜けて、筋肉が緩むのが心地良かった。
「あら? やっと起きたのね」
くすくすと笑いながらそう言ったのは、よしこおばあちゃんだった。
ぼくのところからおおよそ1メートル先の縁側に座り、燃え尽きた蚊取り線香を取り除く作業をしている。
そこでやっと、夢を見ていたのだと、理解した。
「ニャア」
「ふふ。そこはね、ソラの縄張りよ」
よしこおばあちゃんが笑いながら言った。
どうやらぼくは、ネコ用のクッションが敷き詰められた場所を占領していたらしい。
「あっ! そうだ。ぼく、朝からスイカ食べてて……」
眠気に襲われて横になったのだった。
「ニャアッ!!!」
ソラは毛を逆立てている。
「さっきから凄く威嚇していたのよ。何度か声を掛けたのだけどまったく起きなくて困ったわ。あなた昔から寝相も悪いでしょ? 蹴られるのもイヤだし放っておいたの。ごめんなさいね」
よしこおばあちゃんは悪びれる様子もなく淡々と言葉を紡いだ。
「う、うん」
ぼくは「ごめんな」とソラに言ってその場から離れた。
ソラのお気に入りのタオルケットはぐちゃぐちゃに丸まっているし、おもちゃのボールやぬいぐるみは、あたりに散らばっている。
「ニャア」
ソラはぼくと入れ替わるようにしてクッションに座った。
「ごめんな」
もう一度謝ると、ソラはボールのおもちゃを前足でつついた。
ちりん、と音が鳴り、ぼくの心臓はとくりと跳ねた。
頭にさっきまでの光景が浮かびそうになる。
頭の中のやつを追い払うように首を振り、時計を見る。
時刻は十一時ちょうどだった。
時計の横には、カレンダーが貼ってある。
八月一日のところは、赤い丸で囲われていた。
「ふふ。あなたが来るの、楽しみでねえ。ほら、今年から中学生になったから、もう顔見せてくれないかもしれないってずっと心配だったのよ」
ぼくの視線に気が付いたのか、よしこおばあちゃんが言った。
「来るよ。川遊びもしたいし。おばあちゃんの育てたすいか食べたいし。ここ、自然いっぱいで楽しいもん」
「ふふ。あなたが来ると、夏が来たって感じだわ、ほんと。あ、そろそろ閉めるわね。空気、入れ替えてたのだけど、すっかりクーラーの冷気が逃げちゃったわね」
どうりでこんなにも、暑いはずだ。
よしこおばあちゃんは、にっこりほほ笑むと台所の方へと歩いて去って行った。
「ニャア」
振り返ると、ソラの黒い目がじっとこちらを見詰めていた。
息が止まる。
前足を丁寧に揃えて座り、背筋を凛々しく伸ばしたソラの姿は、夢で会ったやつの風貌を思い起こさせた。
蚊取り線香の残り香がツンと鼻腔を刺激する。
「……お前、ソラだよな?」
なんでこんな当たり前のことを口にしてしまったのか自分でもわからない。
ただ、確認したかったのだ。
いつも、ぼくが話しかけると、ソラは何かしらの反応を返してくる。
それを期待していた。
自分でも単純で呆れるけれど、そうやって安心感を得て、さっきの夢のことは忘れようと思ったのだ。
「な?」
念を押してそう口にする。
ソラは珍しく無言を貫いた。
目だけはじっとこちらを見ている。
心臓の音が早くなった。
ぼくは、とうとうにらめっこに負けて視線を逸らした。
しばらくすると、ソラは何事もなかったかのように、またボールをつついて遊び始めた。
「チリン」と、音が鳴った。
ぼくにはもう、この音が無関係には思えない。
いつかどこかで同じ音を耳にする。
そんな、気がする。
そこは、雑居ビルが立ち並ぶ街の中かもしれないし、山奥や浜辺の可能性だってある。
よくわからないけれど、きっと季節は夏じゃないだろうか、と思った。
焼けつくような殺気の中で聞こえる「チリン」は、今度こそ、謎の生命体がぼくたちに警告する音かもしれない。
完