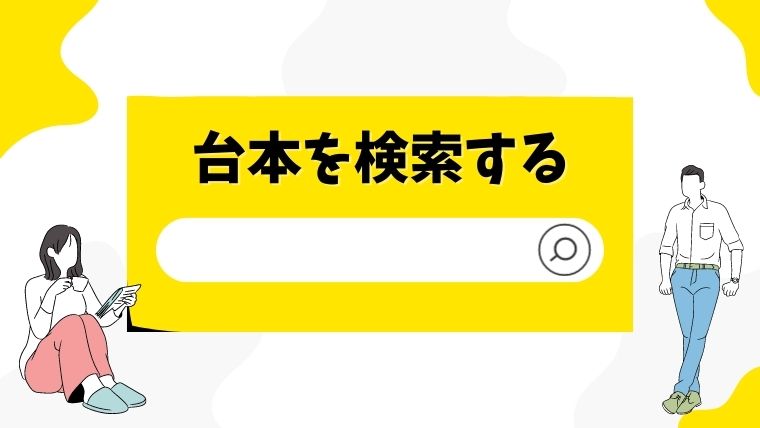【朗読台本】変わらないスイカ【30分~40分】

●使用料:無料
●利用報告:商用のみ要(非商用は任意)
●クレジット表記:必須
ー表記内容ー
| 台本名 | 当ページのタイトル |
| 作者名 | 紺乃未色(こんのみいろ) |
| サイト名 | フリー台本サイト「キャラコエ」 |
| 台本URL | 当ページのURL
※リンク付け(URLをクリックすると、当ページに飛ぶように設定すること)必須 |
上記4点を必ず表記していただきますよう、お願いいたします。
利用のルールについては、利用規約をご覧くださいませ。
概要
| カテゴリ | 朗読(一人) |
|---|---|
| ジャンル | 現実世界 |
| 時間(目安) | 30分~40分 |
| あらすじ | 七十歳の祖母は「娘に会いたい」と言った。 私は意味がわからなかった。だって、隣にいるじゃないか。 |
| 注意 | このストーリーはフィクションです。実在する人物や団体、出来事などとは一切関係がありません。 |
その他、朗読におすすめの台本は、以下のページにまとめています。

フリー台本『変わらないスイカ』
「娘に会いたいわ」
久しぶりに会った祖母の言葉にぎょっとした。
意味がわからない。だって、その娘は、今、すぐ隣にいるんだから。
「ちょっと、おばあちゃんってば、なにいってるの。お母さん、ええっとあなたの娘、ここにいるでしょ!」
わたしが言うと、祖母はニコニコと笑う。
「ええ、ええ。この方ね、娘にそっくりなのよ。お名前までおんなじなんですって。すごい偶然よねえ」
嘘だ……。一瞬、酸素が吸えなくなって苦くなる。昔、プールの授業で息継ぎが上手にできなくなったときのことが蘇ってくる。
鼻から水が入ってきて、目の奥がツンと痛んで泣きたくなるあの感じ。
なんとか必死に酸素を吸い込むと、どこか懐かしい畳の匂いが体いっぱいに広がった。そのせいで、小さな頃にここに来たときの記憶が次々と脳裏に広がっていく。
「お、おばあちゃん。ちょっと待ってよ」
「月子(つきこ)、いいの。大丈夫だから」
すぐそこで母の声がする。
その声は、なんでもないことだと伝えるときのトーンだった。わたしが幼い頃からよく聞いた、母からの大丈夫。
いいや、平気なわけがあるもんか。実の親に忘れられるだなんて考えたこともないし、考えたくもない。
「ねえ、お母さん。どういうこと? おばあちゃん……」
おかしくなっちゃったの? そう声に出したくなるのをぐっと押さえる。
「こないだ話したでしょう? もうねえ、色んなことを忘れてしまっているみたいなの。あたしたちのことも認識ができてないみたいでね……。困っちゃうわよね。実の娘と孫だっていうのに」
「そりゃ、少し忘れっぽいとは聞いてたけど、それってもっとささいなことじゃなかったんだ……」
蚊の鳴くような声。わたしは喉から絞り出すように言葉を吐いた。
「そうなの。もう、困っちゃうわよね。まあ、七十を過ぎると、こうなるのも珍しい話じゃないけれど……。ごめんね。先に説明しようかとも思ったんだけど、実際に会った方が早いかなって思ったの。あ、お父さんには伝えてあるわ」
母がいうお父さん、というのは、わたしの父という意味だ。
「だからって、そんな……」
大切な家族のことを忘れるなんて酷い話、本当にあるんだろうか。いや、たしかに、おかしいって思ったんだ。
ついさっき、わたしたちが祖父母の家にやってきたときだって祖母はこう言った。
「あらあら、こんにちは。お客さんですか。どうぞ、上がってくださいな」
あれ? お客さん? そう思ったけれど、母はなにごともなかったかのように「こんにちは」と声をかけて、古びた実家の土間で靴を脱いだ。
その一連の流れがあまりに自然だったものだから、わたしは違和感を気のせいとして流してしまったんだ。
だけど、その後の会話もへんだった。
「昨日ねえ、お隣の家のゆきこさんとお話したのよ。楽しかったわ」
「吉田さんには三人の子どもがいるの。こないだ、帰ってきていたみたいよ」
「今朝、久しぶりに町内放送を聞いたのよ。内容はなんだったかしら」
祖父によると、ゆきこさんは五年前に亡くなっている。吉田さんの子どもは一人らしいし、各家に備え付けられたスピーカーから聞くことのできた町内放送なんて、十年前から一度も流れていないとのことだ。
過去と今の記憶がごちゃごちゃに混ざっているとか、そういう次元の話ではない。これじゃあ、実の娘に対して「娘に似ている」と言ってしまうのも、無理はないのかも。
現実を受け入れようとしたとたん、祖母と過ごしたさまざまなシーンが頭の中の引き出しから飛び出してきた。
夏休みに手を繋いで近所の豆腐屋さんに行ったこと、海水浴場で砂まみれになった手のひらを手ぬぐいで丁寧に拭いてくれたこと、蚊に噛まれて赤く腫れた腕にアロエを塗ってくれたこと。
どの祖母もニコニコと笑っている。そりゃあもう幸せそうに。
次々と蘇ってくる思い出の欠片たち。それにつられるように体中の水分が溢れそうになって、ぐっと堪える。
そういえば、祖母はよく畑でとれたスイカを食べさせてくれたっけ。つやつやしていて、みずみずしくておいしいやつ。近頃は山から下りてきたタヌキが野菜にいたずらするのだとぷんぷん怒っていたのを思い出す。
あんなに、心も体も、それから頭も健康だったのに……。
もう、目の前にいる人は、わたしのよく知る祖母じゃなくなっているんだ。
わたしは座布団の上にぺたんと座ったまま、何食わぬ顔で首を振る扇風機の風を感じることしかできなかった。足が痺れているような気がするけれど、今はどうでもいい。
「あのねえ、お母さんね、十八歳で実家を出てから、あんまり帰ることもなかったから。ここに娘がいることが、信じられないのかも」
母が淡々と言った。どうして、そんなに平然としていられるの? 辛くないの?
そう聞ききたかったけど、やめておくことにした。
半年前、母は肩こりからの頭痛に悩まされてジュエリー製造のパートを辞めた。それから一週間に一度、片道二時間の祖父母の家を訪れている。
わたしは、たまたま仕事が休みだったから、今日は久しぶりに顔を出しただけ。
きっと、母はもう悲しみに浸り終えたのか、感覚が麻痺してしまっているんだ。
「だからって……」
「月子」
納得がいかないわたしの肩に母がそっと手をおいた。じんわりと温かい。そのことに安堵する自分に縁起でもないと釘を刺す。
ちらりと祖父の方を見てみると、為す術がないのだというように、首を横に振っていた。その振り子のような動きは少しも芝居じみていなくて、すっかり彼の体に馴染んでしまっているみたいだった。
「ねえ。おばちゃんは、おじいちゃんのことは覚えてるの?」
わたしは祖父に尋ねた。
「俺のことはなあ、思い出したり忘れたりを繰り返してる。まったく、こっちが混乱してくるさ」
祖父はため息を吐くと、ごつごつとした手で新聞紙をばさりと広げる。なにげなく紙面に視線をやると、下の方、書籍の広告欄では、脳について書かれた健康本が紹介されている。
わたしはそこから目を逸らして口を開く。
「そっか。……おじいちゃんも大変だね」
「まあ、そうだな。だが、今のところ、記憶の抜けと認識のずれはあるが、身の回りのことは自分でできるようだからな。会話が成り立たなくともなんとかなってる」
「そうなんだ」
祖母と同い年の祖父は歯がすべて揃っていて、低い声でハキハキ話す。昔の人にしては珍しく、もともと家事全般もしていたらしい。手先が器用で、裁縫は祖母よりも得意だったなんて話も聞いたことがあった。
わたしはちらりと祖母の方を見た。白い割烹着を身につけたまま、ちょこんと座布団の上に座っている。
彼女はこちらを見ると、なにかしら? とでもいうように首を傾げる。
わたしたちの会話の意味はわかっていないようで、ただニコニコと笑っているだけ。不思議なことに、昔から変わらない朗らかな笑顔を見ていると「どうして認識できないの?!」という怒りは湧いてこない。「ああ、忘れちゃったのか……」という悲しさばかりがじわじわと込み上げてくる。
祖父も母もおんなじ気持ちなのかもしれない。
「あなたを見ていると、娘に会いたくなるわ」
祖母がまたぽつりと呟く。
「だからおばあちゃん! 娘なら隣に……」
わたしは言いかけて止めた。このやりとりはさっきもやった。でも、なんにも効果がなかった。
それなら……。
「ねえ、ミチさん」
わたしはあえて、祖母の名前を呼んだ。
「はあい?」
祖母は感じよく返事をしてくれる。
「わたしが娘さん……桐子(きりこ)さんのこと、呼んできますよ」
少し前に見た、介護業界をテーマにしたドラマを思い出しながら、ゆっくりと大きな声を出す。
母と祖父は、なにごとだろうかと思ったのか揃って首を傾げた。親子だからか、動きが見事にシンクロしている。
自分でもなにを言っているんだと思ったけれど、今の状況をこのまま放ってはおきたくなかった。なんとかしたい、その一心で思いつきの行動に出る。
「あらあら、本当に? 娘に会えるの?」
祖母の声が大きくなる。
「はい! 少しだけ、待っていてくださいね」
「ええ、ええ」
祖母は、そう言いながら、何度もこくこくとうなずく。
「ちょっと月子。なにを考えてるのよ」
戸惑ったように呼びかけてくる母の腕を引っ張り、居間と隣接している台所へと連れて行く。
「ねえ。この家にお母さんの昔の服とか残ってないの? 一枚くらいあるでしょ?」
「服? ああ、二階のタンスに残ってはいると思うけど……。まさか、それ着て、ここに登場するってこと?」
「そう! 名案じゃない? まあ、どうなるかはわからないけれど」
わたしは首を痛めそうなくらいに、大きく首を振る。
「あー、まあ。やってみてもいいかもしれないわね」
「でしょ」
「……待ってて。着替えてくる」
母はそう言って、居間の端にある一歩踏むごとにミシミシと鳴く古い階段を上っていった。
わたしはその背中を見送ると、急いで祖母の元へと駆け寄る。
「ミチさん。桐子さんに連絡つきましたよ! 今から、来てくれるみたいです」
オーバーリアクションぎみに、両手を叩く。
「まあ! まあ! なんて素敵なことなの。……あ、でも」
祖母の表情は、一瞬だけ華やいだものの、すぐに眉を垂らしてしまう。咲いたと思ったらすぐに萎んでしまったお花みたい。
わたしは小学生のときに枯らしてしまったアサガオを思い出して、無性に切なくなった。
「ミチさん? ど、どうしたんです?」
焦りからか、声がひっくり返る。いったいなにが、気がかりなのだろう。
「あの子ったら、ずっと忙しいみたいなの。仕事とか、学校のこととか、あとなんだったかしら。とにかくいろいろあるらしいの。無理してまで帰って来なくていいって言ってあるのに……。本当に、大丈夫なのかしら? ねえ、あなた、伝えてくださる? またの機会でもいいからって」
さっきまでの、のんびりとした口調とは違っていたから驚いた。祖母の舌は、言い慣れたフレーズを紡ぐときのように、すらすらと動く。
まるで、これまでもずっと繰り返してきたかのように。
わたしはそのとき、ふと感じ取ってしまった。祖母と母、二人が後悔していることを。本人たちが自覚しているかどうかはわからないけれど。
「桐子さん、お仕事や家のことも頑張ってるみたいですね。でも、忙しくても、久しぶりにミチさんに会いたいって言ってましたよ。だから、大丈夫です!」
「まあ、そうなの? 嬉しいわ」
祖母は両手を頬に当てて、恋する乙女のように、うふふと笑う。まるで、初恋の人にでも会うときのようなしぐさ。
祖父の方を見ると、彼は行く末を見守ってくれているのか、新聞紙を広げながらもちらちらとこちらに視線を送っていた。ニュースにちっとも集中できていないことが見てとれる。
そのうち、ミシ、ミシ、ミシとリズミカルに階段が鳴った。
母が下りてきた! わたしの心臓は小刻みに騒ぎ出した。呼吸が止まっていることに気づき、慌てて酸素を取り込んだ。
どうか、どうか! おばあちゃんが、お母さんを認識できますように!
神様、お願いします! 子どもの頃に戻ったかのように、心の中で叫ぶ。
「お、お母さん」
祖母を呼ぶ母の声は、緊張のせいか震えているように聞こえた。
「桐子?」
祖母が囁くように呟く。まだ、信じられていないといった様子だ。
「そう! 桐子よ」
「まあ、まあ、まあ! 桐子、元気なの?!」
祖父は静かに新聞紙を閉じ、軽く畳むとテーブルの上に置いた。わたしは、座布団の上で膝立ちになった。そのまま膝歩きをして二人の傍を離れ、祖父の隣に腰を下ろす。
畳に擦れる膝の痛みも、扇風機の風によって乱される髪も、今は気にならない。
「元気、元気よ。お母さんは? ちゃんと食べてるの?」
「ええ、ええ。月子ちゃんはどうしてるの? そろそろ高校を卒業する頃でしょう?」
祖母の中での時系列はぐちゃぐちゃになっているみたいだったけど、そんなことはどうでもよかった。
「月子も楽しくやってるわ」
母はそう言って、ちらりとこちらを見てほほ笑んだ。
「そう、みんな元気ならいいの。よかったわ。本当に」
「お母さん、ごめんね。ずっと来れなくて」
「いいのよ。あなた、忙しいでしょう? こっちは大丈夫だから。でも、こうやって会えたのはすごく嬉しいわ。ありがとうねえ、来てくれて」
「ううん。これからはあたしも、ひと月に一度は来るから!」
母は、わたしが知っているよりも、子どもっぽくなっているような気がした。ちょっぴり、自分の姿と重なりそうになる。
わたしも二十五歳で一人暮らしを始めてから、実家の存在が遠くなりつつあったから。実は母に会ったのも、三ヶ月ぶりだった。でも、親元から離れるっていうのは、誰もが経験する可能性があることで、自然なことだとも思う。
本人たちの人生があるんだから。
ずずっと音を立てて鼻をすすっていると、祖父が黙ってティッシュぺーパーの箱を近くに置いてくれた。
一枚とろうと手を伸ばすと、大きな腕とぶつかった。
「あ、おじいちゃんも、泣いてる」
小声で呟くと、祖父はさっと顔をそむけてしまう。
「いや、違う」
「あはは。二人、よかったね」
わたしが言うと、祖父は無言で大きくうなずいた。
それから祖母と母、二人はいくつか言葉を交わしていた。ときどき、噛み合っていないような気もしたけど、それは重要なことじゃない。
話の内容はなんだっていいんだ。
「じゃあ、お母さん。また来週来るね」
母が祖母へ言った。
「わたしも! おじいちゃん、おばあちゃん、また来るね」
彼らは笑顔で見送ってくれた。
祖母は、おばあちゃんと呼ばれることは否定しないけど、やっぱりわたしのことを孫だとは認識していなさそうだった。
「月子、ありがとうね」
母がそう言ったのは、祖父母の家から少し離れたところにある駐車場まで向かう途中のこと。二人並んで、昼間の太陽の熱に温められた砂利道を歩いていたところだった。
「どういたしまして。再会大作戦、成功だね」
わたしは得意げに笑った。
「最初は何を言い出すのってびっくりしたけど、やってみるものね」
「うん。あ、そういえばあの服さ、どう見ても寝巻だったよね?」
母が着替えてきたのは、小花柄のセパレートパジャマだった。アイボリーと桜色のミックスが可愛らしいデザイン。
サイズは少し小さめだったけど、それは仕方がないだろう。
「他にも服はあったんだけど、それしか入らなかったのよ! ほかのスカートもブラウスも、今の私にはキツかったの。けっこうショックだったんだから、言わせないでちょうだい」
「ああ、ごめん。ごめん。たしかにパジャマって、少し大きめ買うもんね」
「ああ、あれね、買ったんじゃなくて高校生のときにお母さんに作ってもらったやつなの」
母は駐車場の向こう側、キラキラ光る水平線を見ながら笑った。
「おばあちゃんの手作りってこと? 凄いね!」
びっくりした。売り物に近かったから。
「そう。でもねえ、当時は、柄が好みじゃないっていって、嫌がったのよねえ。結局、あんまり着てなかったかも。そのことも、すっかり忘れてたんだけどね。タンスの中で見つけるまで。でも、よかったわ。あのパジャマのおかげであたしのこと、認識してくれたのかもしれないし」
母の顔は、どこか晴れやかだった。
「どうだろ。なんとなく、パジャマがなくても、うまくいってたような気もするけどね」
それは、わたしの希望だったのかもしれない。
「そう? なにはともあれよかったわ」
母が言った。
「だね」
夕方だというのにまだ日は高く、どこからかやってみた潮風が肌を撫でていく。元気いっぱいに鳴いているセミの声を聞きながら、わたしは大きくうなずいた。
一週間後、わたしはドキドキしながら、母と一緒に祖父母の家を訪れた。
祖母は母のことをちゃんと覚えているだろうか。
「こんにちは。入るわよー」
母はいつものように声をかける。
「おじいちゃん、おばあちゃん、お邪魔しまーす」
わたしは不安を打ち消すように、わざと明るい声を出した。
すぐに二人は、出迎えてくれた。
さあ、どうなる?
「……あらまあ、お客さんねえ。いらっしゃい。上がってくださいな」
祖父と母、それからわたしは同時にぽかんとした。
沈黙が流れ、生ぬるい風がひゅるっと、何食わぬ顔で吹き抜けていく。……でも、不思議なことに、先週のように悲壮感に包まれることはなかった。むしろ、ずっこけて「なんでよ!」って突っ込みを入れたくなるようなその状況に、三人で顔を見合わせて笑った。満面の笑みっていうよりも、かなり引き攣った苦笑いだったけど。
祖母はというと、相変わらずご機嫌なのかニコニコしていた。
母は、そんな祖母を眺めると「まあ、いっか」と言った。
強がりでも、やけくそでもなく、気持ちに折り合いをつけたのかな、と感じさせるようなニュアンス。
わたしはそこでようやく、肩の力を抜いて、祖父母の家に上がったのだった。
「これねえ、食べてちょうだい」
居間のテーブルで祖父と母が会話していると、丸いお盆を持った祖母があらわれた。その光景に息を飲む。
「あ、懐かしい」
思わずぽつりと言葉が零れた。
「朝、この人に切ってもらって冷やしておいたのよ。今年のは自信作なの」
祖母はそう言ってちらりと祖父の方を見ると、スイカをのせたお皿をテーブルに置いた。光を反射してキラキラと光るキューブ型のそれは、見るからに甘そうだ。
「おばあちゃん、まだスイカ作ってたんだ!」
驚いた。
てっきり、もう畑仕事はしていないと思い込んでいたから。そこで、自分の考えが恥ずかしくてたまらなくなった。過去と今がこんがらがっている祖母は、体まで弱ってしまったのだと、勝手に想像していたんだから。
なんて、失礼なんだ。さっきから視界に入る祖母は、茶托の上にのっている湯呑みのように、姿勢がしゃんとしているのに。
「ええ、ええ。もちろんよ。でもねえ、タヌキに食べられちゃったの。ほんと、なんとかしたいわ」
祖母は困ったように、手のひらを頬に沿えた。
「そうなのね。いつも困っちゃうわよねえ」
母が言った。記憶の中と違わない声、話し方、それから表情。ああ、おんなじなんだ、とぼんやり思う。
わたしは、いただきますと手を合わせて、爪楊枝でキューブ型のスイカを刺した。ジュワッと水気が滲み出てくる。
そのまま口の中に入れて、咀嚼する。心地良い冷たさとシャクシャクという音。爽やかな香りとほんのりとした甘さ、こちらを見つめる祖父母と母の優しい視線……。
どれも変わっていない。ただ、みんなが少しだけ年を重ねただけだ。
そのことを実感したとき、わたしのなかには、フルーツの果汁のように甘く酸っぱい感情が溢れかえった。
「ふふ。おばあちゃんのスイカ、やっぱりおいしいね」
わたしが笑うと、みんなも笑った。あの頃みたいに。
そのことが、ただただ嬉しかった。
その後、母は変わらず、二、三週間に一度は顔を見せに行っていたし、わたしは二、三ヶ月に一度は同行していた。
最後の方は、実家帰りというよりは、病院へのお見舞いになっていたけれど。
祖母が亡くなったのは、再会作戦から三年が経った頃だ。
すい臓に悪性の腫瘍が見つかってからは、本当にあっという間だった。祖母はみるみるうちにやせ細っていったし、言葉もほとんど発さなくなった。たぶん、わたしたちのことをお客さんとすら認識していなかったと思う。
だんだんと弱っていく姿から目をそむけたくならなかったといったら嘘になる。でも、ここで見たくないからと、会いにいかないという選択肢を選ぼうとは思わなかった。
結局、祖母はあれ以降、母のことを娘だと理解できることはなかった。
でも……。
最期のとき、
「桐子、ありがとう」
清潔な白いシーツの上で、祖母はたしかにそう言った。
掠れていて、耳を澄まさないと聞こえないくらいに小さな声。でも、わたしにはわかった。それから母にも。その証拠に、母は嗚咽を漏らしたから。
わたしもつられるように体が熱くなり、鼻の奥が痛くなる。祖母がいなくなって悲しいから?
それもあるけど、他にも理由はある。
「また、会えたんだ」
心の中でそっと呟く。
実際には、定期的に顔を合わせてはいた。けれど、この瞬間になって、二人はやっと母と娘として三年ぶりの再会を果たせたんだ。
その事実に、心の底からよかったって思う。
ぼやける視界の中で、目を閉じた祖母を見る。
彼女はいつもみたいに、朗らかに、それでいて優しく微笑んでいた。
完