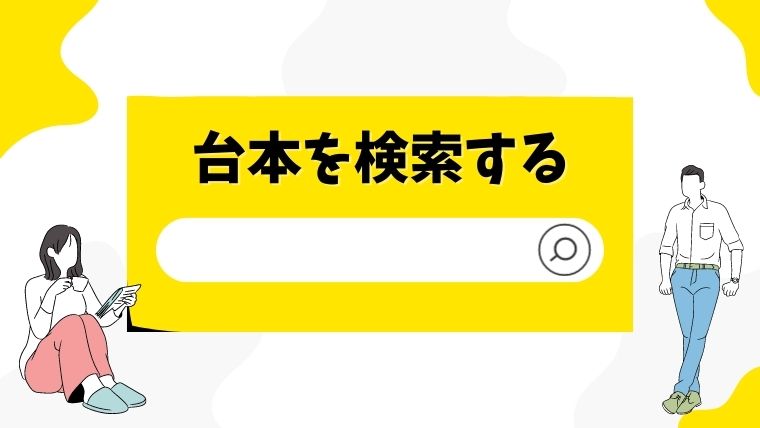●使用料:無料
●利用報告:商用のみ要(非商用は任意)
●クレジット表記:必須
ー表記内容ー
| 台本名 | 当ページのタイトル |
| 作者名 | 紺乃未色(こんのみいろ) |
| サイト名 | フリー台本サイト「キャラコエ」 |
| 台本URL | 当ページのURL
※リンク付け(URLをクリックすると、当ページに飛ぶように設定すること)必須 |
上記4点を必ず表記していただきますよう、お願いいたします。
利用のルールについては、利用規約をご覧くださいませ。
概要
| カテゴリ | 朗読(一人) |
|---|---|
| ジャンル | 現実世界 |
| 時間(目安) | 30分~40分 |
| あらすじ | いつのまにか、私はブルームーンの妖精になっていたらしい。 |
| 注意 | このストーリーはフィクションです。実在する人物や団体、出来事などとは一切関係がありません。 |
その他、朗読におすすめの台本は、以下のページにまとめています。

フリー台本『ブルームーンの妖精たち』
1
テーブルの上には、ミステリアスな青い満月がぽっかりと浮かんでいる。
「お姉ちゃんには、特別。そのカクテル、ここで出すのは初めてなの」
バーカウンター越しに妹、エリは言った。
私は、おしゃれなグラスのフチにすっぽりと包み込まれている青い月を眺める。
「ふうん、幻想的《げんそうてき》ね。ブルーサファイアみたい。あの宝石がとろとろに溶けたら、こんな感じになりそうよ」
見たまんまの感想を伝えると、エリは「もう」と呆《あき》れた。
「へんな例えね。それ、ブルームーンっていうの」
満月に似ていると思ったのは、あながち、間違ってはいないみたいだ。
そんなことを思いながら、グラスを軽く持ち上げる。
「ブルームーン」
小さく名を呼んでみる。たしかにしっくりとくる。
「本当、お姉ちゃんって、反応薄いわよね。こんなの飲むのもったいなーい! とか、ないの?」
エリは甲高《かんだか》い声を作りながら、そう言った。
「これでも、感心してるんだけど」
「伝わらないわよ」
エリがため息交じりにそう言うと、カランと音がして、店の扉が開いた。
夏の終わりを感じさせる生ぬるい風とともに、白いシャツの似合う青年が姿をあらわす。
「いらっしゃいませ。あ、ユキくん。珍《めずら》しいね、金曜日に来るの。しかも、久しぶりじゃない?」
「あー、最近、顔出せてなくて」
「へえ。忙しかったの?」
「ちょっといろいろあって」
「そっか。あ、何飲む? いつものビール?」
「そうします」
ユキくんは、三つ離れた席に座った。
私は一番端の席で、ちまちまとブルームーンを飲み、気配《けはい》を消しつつ耳をそばだてる。
二つ年下の妹、エリは二十六歳のときから、このバー『コスモス』のオーナーから運営を任されている。もう一年くらいが経つ。
私はというと、たまに顔を見せる客といったポジション。
だって、不安にもなる。
いきなり、妹が「バーで働くから」だなんて言い出したら……。
それが、いつしか『コスモス』に来ることが、金曜日のルーティンと化している。
「あ、それ、ブルームーンですよね?」
突然、話しかけられ、肩をびくりと震わせた。
「すみません。急に声掛けて。あんまり見ないお酒だけど、綺麗だなって思って」
「あ、そうです。ブルームーン」
「ですよね。なんか、昔、よく遊んでた色付きのスライム、思い出します」
「えー? もう、そんな例えばっかり!」
エリはぷりぷり怒りながら、ユキくんの前にビールジョッキを置いた。
「だって、そっくりなんですよ。あのスライムがどろっどろに溶けたら、たぶん、こんな感じになります」
さっきまでの自分の考えに似ていたものだから、思わず笑ってしまう。
「あ、ごめんなさい」
私はすぐに我に返り、きょとんとした表情をしているユキくんに謝った。
「なあに? お姉ちゃん、どうせ、味方ができたとか思ってるんでしょう」
エリが言った。
「あ、お姉さんなんですか?」
「あ、うん。そうなんです」
ユキくんは「たしかに、言われてみれば似てるかも」と感想を述べると、ジョッキを手に取り「乾杯《かんぱい》」と言った。
私はつられてカクテルグラスをそっと持ち上げる。
そういう流れだった。
お酒の席では、こういうことがたびたび起こる。
なんとなく、近くに座っている人との距離が近くなるのだ。
とくに、『コスモス』は、誰もが知らずのうちに、店の空気と一体化する、不思議な場所だった。
たとえ、一人で座っていても、空間を彩るひとつの欠片として、そこに自然と馴染《なじ》める空間。そんな感じ。
2
「そういえば、なにかあったの?」
エリがユキくんへと尋ねる。
「あー、大学やめようか迷ってるんですよ」
「えー。どうして?」
「もともと俺、高校卒業したらすぐ働くつもりだったんすよ。うち、お金もあんまりないし」
ユキくんはそこまで言うと、ビールを飲んだ。
そこへ、べつの二人組がやってくる。
エリは必然的にそちらに時間をとられることになった。
「でも、親が反対したんです。大学は出ておいた方がいいって。言ってることはわかりますけど、奨学金《しょうがくきん》払い続けることとか考えると、やっぱりもやもやしましたよ」
驚いたことに、ユキくんはエリがその場にいなくても会話を続けようとした。
「そう」
とりあえず、相槌《あいづち》を打つ。
エリ! 早く戻ってきて!
そんな心の叫びをあざ笑うかのように、カランという音が、次の来客を知らせる。
「それで、ひとまず入学して二年はいたんですけど、あんまり楽しくなくて……。まわりの奴らは、今のうちに遊んでおこうって感じなんです。それも、たまに度を越すようなこともしそうになるし……。俺からしたら、そんな時間あるなら、働きたいんですよね。でも、それを伝えると、変な目で見られるんです」
「変な目?」
「こう、意識が高いって言われるんですけど、たぶん、良い意味ではなくて、からかわれてるんです」
「あー。なるほど」
「俺、悲しかったんです。あと、腹立たしかったです。正直、遊んでばかりいる相手を馬鹿にしました。「お前らとは違うんだ」と。もちろん、口には出しませんでしたけど」
彼が感じているであろう、感覚には見覚えがあった。
「悔しい」だとか、「むかつく」だとか、激しい感情で表現する人たちもいるけれど、私にとっては、もっとシンプルで「わかってもらえない」というもどかしさだ。
私は、一言「そっか」と口にする。
相変わらず気の利いた言葉のひとつも出てこない。
「髪、切ったんですね」
エリは、こちらのお通夜っぽい雰囲気を気にも留めず、二人組と世間話を繰り広げている。
「あ、すみません。こんな話」
私がエリを見ていることに気が付いたのか、ユキくんが謝った。
「え、いいの、いいの。それで? その子たちとはどうなったの?」
「さすがに縁は切ってないんですけど、前ほど仲良くはないですね」
「そうなのね。あ! 大学の勉強は? とくに、興味ない?」
「ええ。お恥ずかしながら。こんなこと言ってたら、怒られそうですけど」
ユキくんの肩は、一回り小さくなってしまった。
その体に貼り付く悲壮感を、びりびりと剥がしてあげたくなる。
「大丈夫! それって自然なことよ。ええっと……。世の中、勉強好きばかりじゃないもの。うん。ユキくんは、勉強より仕事に力を入れたいんでしょう? 私は凄いって思った。ほんとに」
なんとか、元気になって欲しいと思い、言葉を綴るも、当たり障りのないことしか出てこない。
こういう、自分の不器用さがときどき嫌になる。
「……ありがとうございます」
ユキくんは、ぐびぐびとビールを飲み切り、タンっと音を立てて、ジョッキをカウンターに置いた。
「あ、次もビール?」
エリがすかさずやってきて尋ねる。
「はい」
ユキくんはそう言うと、「お手洗い」と呟き、そそくさと席を立った。
「あれ? なんか、ユキくん、目が赤くなってた?」
エリが尋ねる。
「え? 隣にいるとわかんないよ」
私が答えると、エリは少し首を捻ってから、すぐに新しいジョッキを手にとった。何の気なしに、手元のブルームーンへと視線を落とす。
青い月は二回りほど小さくなっていた。
それを手に取り、残りを飲み干す。
「あ、もう帰られますか?」
ユキくんは、戻ってくるなり、空っぽになったグラスを見てそう言った。
「うん」
ユキくんは、「そうっすか」と言って、静かに座った。
3
それから、二ヶ月の間、ユキくんと会うことはなかった。
その日、私はいつもの場所、一番端のカウンター席に座っていた。
エリが意味深《いみしん》に笑いながら、青い満月の浮かんだグラスを差し出してくる。
「なによ? にやにやして」
エリは「なんでもない」と短く言った。
「そういえば、最近こればっかり出すわね」
私は、お酒のことはよくわからない。
いつもエリにお任せして、適当にカクテルを出してもらっている。
でも、最近は、ブルームーンばかりだ。
「いいじゃない。それ、美味しいでしょ?」
「まあ、たしかに」
「ね!」
エリはウインクをして見せると、少し離れたところにいるべつのお客さんの前へと行ってしまった。
「あの、それ、ブルームーンですよね?」
ふいに、カウンターの真ん中にいた二十代前半くらいの女性に声を掛けられる。
「あ、はい」
これで、何度目だろうか。
私は、もともと『コスモス』にやってくるお客さんと、そこまで多くの言葉を交わすタイプではない。
思い返してみると、ユキくんと話をしてからだ。
一人で飲んでいると、必ずといっていいほど、誰かに話かけられ、身の上話が始まってしまう。
家族のこと、恋人のこと、仕事のこと……。
だいたいカテゴリは決まっているけれど、内容はみんな違う。
まさに十人十色《じゅうにんといろ》。
そして、「ブルームーンですよね?」はもはや、合言葉《あいことば》みたいになっている。ん? 合言葉……。私は、ちらりとエリの方を見た。
エリはこちらへ背を向けて、冷蔵庫から炭酸水を取り出している。
「あの……。ひょっとして、このカクテルのことで、なにか噂《うわさ》になってたりしますか?」
私はエリに聞こえないように、小声で尋ねた。
「えっと、『コスモス』のカウンター席の一番端に、ブルームーンの妖精がいると……。たぶん、あなたのことですよね?」
「妖精?」
私が単語を復唱すると、女性は困ったように目尻を下げた。
「はい。それで、悩みを聞いてくれるのだと、うかがって……。すみません、てっきり、あなたもこの話をご存じだとばかり思っていました。まさか、ご本人が知らないとは……。迷惑でしたよね」
女性が申し訳なさそうに言うものだから、私は大きく首を左右に振った。
「いえ、大丈夫です。ただ、びっくりして。私は、人の悩みなんて解決したこともないし、ただ、聞いているだけなんです。本当に」
女性は、その言葉を聞くと「やっぱり、あなたですね」と言って笑った。
私は不思議に思い、小さく首を捻ることしかできない。
きっと、まぬけな顔をしていたと思う。
「お姉ちゃん、凄いね。今日の人も、すっきりって感じの顔してた」
女性が店を後にしてすぐ、エリが言った。
「ちょっと、エリ! 噂《うわさ》になってるなら、教えてよ」
私が文句《もんく》を言うと、エリは、はっとした表情を見せた後「だって……」と口にする。
「お姉ちゃん、私が伝えてたら、ここ来なくなっちゃいそうだもの」
「まあ……。そうかも」
「ねえ! お願い。来週も来てね。その後も!」
エリはいつになく真剣な表情で言った。
「うーん」
私はどうしたものか、と考えた。
べつに、今まで通り、ここに来て、お酒を楽しめばいいだけだ。
声を掛けられたら、少し話を聞けばいい。
ただ……。噂《うわさ》のせいで、見知らぬ人から聞き手としてのスキルを求められていると思うと、どうにも気がのらない。
「本当はね、あたしだって、ちゃんと話を聞いてあげたいのよ。でも、一人にばかり時間をかけてはあげられないの」
「それはわかるけど」
「お姉ちゃんに話をした後のお客さんの顔を見ると、こっちまで良かったって思うのよ。目には見えないけれど、なにかが軽くなっている感じ」
「うん」
私は相槌《あいづち》を打ちながら「私も、あんたも、カウンセラーじゃない!」と心中で叫んだ。
人の話を聞くのって体力がいる。
嫌いではないけれど、好んでしたいとは、まったくもって思わない。
でも、口には出さない。
エリの言いたいことは、わからなくもないから。
「……いいお店ね。また来るわ」
私は、そう言って外へと出た。
4
翌週も、その次の週も、「ブルームーンですよね?」から始まる交流はあった。
私は、ただ話を聞くだけだ。
相槌《あいづち》をうち、青いカクテルをちまちまと飲む。
グラスのなかに浮かんでいる月が小さくなり、やがて消えると、席を立ち、店を去る。
そんな金曜日を繰り返している。
彼らが語るのは、後悔、未練、罪悪感《ざいあくかん》、喪失感《そうしつかん》……。
お互いが素性《すじょう》を知らないからこそ、ありのままの状況を、丸裸《まるはだか》の心境を、ストレートな言葉で語れるのだろう、と思う。
彼らから零《こぼ》れ落ちる一つひとつの単語は、真っ白なマシュマロみたいで、剣《けん》も楯《たて》も知らない子どものように無防備だった。
それなのに、表面上は大人を演じて言葉を紡《つむ》ぐ。
そんな人がびっくりするくらいたくさんいる。
だから、たまに、私の方が泣きたくなってしまう。
赤ん坊みたいに泣き叫び、助けを求められたら、どんなに楽になれるだろう。
そんなことを考えながら『コスモス』のドアへと手を伸ばした。
「あ、いらっしゃい」
普段通りの調子で、エリが言った。
「あ、うん」
私は面食《めんく》らった。
いつもの席が埋まっていたからだ。
「そこ、座ったら?」
「うん」
私の場所にいるのは誰だろうかと思い、視線を向けて驚いた。
その人の手元には、ブルームーンがあった。
「あ」
小さく声が漏れるものの、それは、店内に流れる洋楽にかき消される。
「はい。今日は、これ」
エリはショートサイズのグラスをカウンターテーブルへと置いた。
「カルーアミルク」
「正解。名前、覚えてきたんじゃない?」
「そうかも」
「なんだかんだ、けっこう通ってくれてるものね」
エリが嬉しそうに言った。
そうだ、今の私にとって『コスモス』は、ただの妹の勤め先ではない。
ちらりと、いつもの席を見ると、エリと同じくらいの年齢の女性が、静かに青い満月へとキスをしていた。
ウェーブがかった亜麻色《あまいろ》のロングヘアが美しく、ブルームーンのミステリアスな魅力を引き立てている。
私では、あんな風に絵にはならない。
「あたしの、恋人の先輩の友達の彼女」
エリが囁《ささや》くように言った。
「え、なんて?」
関係性が遠すぎるだとか、エリには恋人がいたのかだとか、突っ込みどころはたくさんあった。
しかし、一番聞きたいのは、なぜ、彼女がそこでブルームーンを飲んでいるのかってことだ。
私の席なのに、という本音が零れそうになるのをぐっと堪える。
「あのね、向いてるって思ったの」
エリはこちらの心を読んだように言った。
「え?」
「つい先日、ここに飲みにきてくれてね、そのとき、ブルームーンの妖精になれる人だってピンときたの。それで、お願いしたら引き受けてくれたのよ。ほら、一人より二人っていうじゃない」
エリの言葉が聞こえたのか、その人はこちらを見てほほ笑んだ。
「……ねえ、エリ。ビールが飲みたい」
エリは一瞬、何かを言おうとして、口を閉ざした。
5
次の金曜日は、ブルームーンを思い起こさせるような、綺麗な満月の夜だった。
でも、私の足は『コスモス』の方へとは向いていない。
なんだか自分の居場所をとられたような気がして、小石でも蹴飛《けと》ばしたい感じがするからだ。
どうやら私は『コスモス』で過ごす時間を気に入っていたらしい。
「……違うか」
あのお店が好きなら、いつもみたいに飲みに行けばいいだけだ。
「はあ」
ため息が零れる。
あんまり認めたくないけれど、私は『ブルームーンの妖精』である自分に酔いしれていたらしい。
耳が、頬が、首が、じわりと熱くなる。
なんだか飲みたい気分になり、近くの居酒屋に入ることにした。
ここは、カウンター席が充実していて、一人客も多い。
枝豆を齧《かじ》りながら、あたりを見渡すと、サラリーマンらしき人たちがいた。
笑い声に交じって、上司の愚痴《ぐち》やら、自慢話やらが聞こえてくる。
「はあ」
ありありと視界に入る光景が嫌になる。
アルコールの匂いを纏《まと》い、目をギラつかせ、大きな声で主張している彼らも『コスモス』では、ただの子どもになるのだろうか。
「しっくりこない」
あまりに想像がつかなかった。
結局、居酒屋に漂うリアルな生活感から逃れたくて、三十分程で店を後にした。
どことなく、非現実的な雰囲気の漂う『コスモス』が恋しくなる。
少し、顔を出してみようかどうしようか、迷っていると、どこかで見たことのある人物が、前方から歩いてきた。
あれはたしか……。
お酒で鈍くなった脳みそを懸命に動かしていると、突然、肩に衝撃を受けた。
「きゃっ」
短い悲鳴を上げるとともに、ハンドバッグがなくなっていることに気が付く。
「ひったくり」
思いっきり叫んだつもりが、喉《のど》から出るのは、高音の掠《かす》れた音だけだ。
「待て!」
代わりに大声を上げながら、ひったくり犯を追いかけてくれたのは……。
「ユキくん!」
そうだ、彼だ。
私は、すぐに二人の後を追って走った。
路地裏《ろじうら》へと入って息を飲む。
ユキくんはひったくりの男に馬乗りになり、バッグを取り返そうと手を伸ばしていた。
相手も身を引く気はないようで、こぶしでユキくんを何度も殴りつける。
私は荒々しい取っ組み合いに、背を向けたくなるのをぐっと堪えた。
「やめて!」
なんとか声を出すものの、二人はこちらのことなんて、気にも留めてくれない。
「け、警察! 警察呼ぶから。けいさつ!」
その言葉を聞いた男は小さく悲鳴を上げた。
そのすきに、ユキくんは、がっしりとバッグの持ち手を掴み、そいつから引き剥がす。
私は、素早くスマホのカメラアプリを起動して、ひったくり犯の方へと向けた。
状況を察したのか、男は顔を隠すようにして、走り去って行く。
私はというと、ひざの力が抜け、その場にへなへなと座り込む。
6
「あの、これ」
ユキくんが、ハンドバッグを差し出してくる。
あ、お礼言わなきゃ。
そう思い顔を上げて絶句した。
「血が……」
暗くてもわかる。
ユキくんの顔は血まみれになっていた。
「大丈夫です。ただの鼻血ですから」
ユキくんは片手で顔を拭いた。
赤い血が顔面に広がり、痛々しさを物語る。
ぽたぽたと落ちる真っ赤なそれは、まだ止まりそうにない。
私は急いでハンカチを取り出した。
「これで押さえて」
「あ、ありがとうございます」
「病院に……」
「それはちょっと……。俺もけっこう本気で殴ってるんで。できれば、このまま去りたいかな。警察には、たまたま近くにいた人がなんとかしてくれたとか、適当に言っておいてください」
「でも……」
「すみません。ほんとにダメなんです」
ユキくんは、有無を言わさないような低い声で言った。
きっと、事情があるのだ。そう悟った。
あのとき、『コスモス』で話してくれたことのほかにも、彼は何かを抱えているのかもしれない。
「……なんで、ここまでしてくれるの?」
べつに、私自身が攫《さら》われたわけじゃない。
ハンドバッグだって、どうみても高級ブランドのものではない。
ユキくんがケガをするだけの価値があるとは思えない。
「え?」
「私がユキくんの知らない人でも、同じことした?」
彼は首を振った。
「さっきも言った通り、俺自身が警察のお世話になることは避けたいですから」
「じゃあ、どうして」
「……だって、前に話を聞いてくれたじゃないですか」
ユキくんの口調は、小さな子どものように幼くなった。
「話って……」
そんなこと? というのが本音だった。
「俺、嬉しかったんです」
ユキくんは、まっすぐにこちらの目を見てそう言った。
「……そう」
誰かが通報してくれたのか、パトカーのけたたましいサイレン音が近づいてくる。
「もう行かないと。このハンカチ、クリーニングして返します」
「いいよ、そんなの」
「俺の気が済まないですから。また、来ますよね?」
どこに、とは言われずとも理解できる。
「うん。行くよ」
「よかった。あの、お願いしますね。俺のことは、絶対に伝えないでください」
私が頷くと、ユキくんは血まみれの顔で少し笑って、その場を去った。
小さくなる背中を見送りながら、彼が助けてくれた理由を思い出す。
私はちっとも嬉しくなかった。
空を見上げると、まるい月が浮かんでいる。
「……足りないんだ」
秋の冷たい風に肌を撫《な》でられ身体が冷える。
なぜだか、むしょうに泣きたくなった。
「あの人です!」
知らない声がした。
一人の女性と二人組の警察官がいた。
私はユキくんとの約束通り、警察には知らない青年が、バッグを取り返してくれたのだと伝えた。
何食わぬ顔をしてウソを吐く。
大丈夫、誰にも疑われない。不思議と罪悪感はなかった。
警察がメモをしている隙に、もう一度、月を見つめる。
私は祈りを捧げるように両手を組んだ。
それから『コスモス』のはじっこの席だけじゃなくて、この世界のいたるところに、ブルームーンの妖精たちが増えますようにと、小さく願った。
完