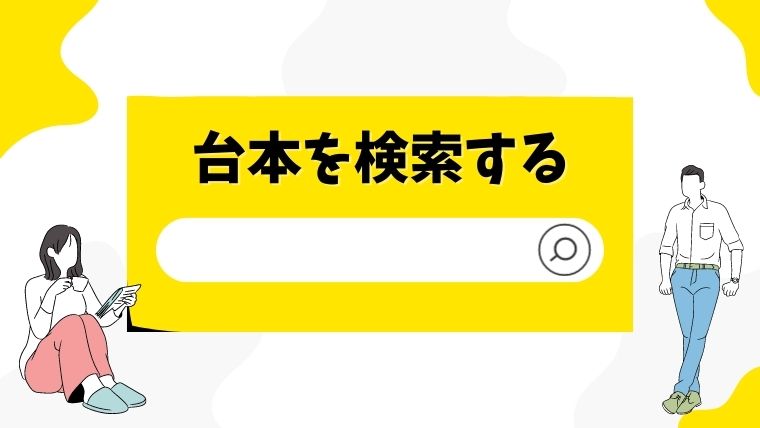【朗読台本】かえりみち【6分~10分】

●使用料:無料
●利用報告:商用のみ要(非商用は任意)
●クレジット表記:必須
ー表記内容ー
| 台本名 | 当ページのタイトル |
| 作者名 | 紺乃未色(こんのみいろ) |
| サイト名 | フリー台本サイト「キャラコエ」 |
| 台本URL | 当ページのURL
※リンク付け(URLをクリックすると、当ページに飛ぶように設定すること)必須 |
上記4点を必ず表記していただきますよう、お願いいたします。
利用のルールについては、利用規約をご覧くださいませ。
概要
| カテゴリ | 朗読(一人) |
|---|---|
| ジャンル | 現実世界 |
| 時間(目安) | 6~10分 |
| あらすじ | 祖父母の家からのかえりみち、母が声を押さえて泣いていたことを覚えている……。 ひとりの女性の、昔と今の夏のおわり。 |
| 注意 | このストーリーはフィクションです。実在する人物や団体、出来事などとは一切関係がありません。 |
その他、朗読におすすめの台本は、以下のページにまとめています。

フリー台本『かえりみち』
1
小学生の頃、夏休みは、母と一緒に祖父母《そふぼ》の家で過ごすことが多かった。
車で三時間くらいのところにある田舎《いなか》町だ。
山のふもとにある金魚の池でスイカをキンキンに冷やしたり、一日中、海にぷかぷかと浮いてみたり、浴衣《ゆかた》を着せてもらって近所のお祭りに参加したり、学校生活とは違う、非日常的な日々にワクワクとしていた。
そりゃあもう、夏休みの宿題の絵日記のネタに困らないくらい。
でも、わたしには、ひとつだけ苦手なことがあった。
2
「じゃあ、お母さんまたね。父さんも」
母が、祖母《そぼ》のことをお母さんと呼んでいるのは、へんな感じだった。
おばあちゃんは、お母さんのお母さん。
そんな、当たり前のことが、なんだか、おもしろい。
「はいはい。マキコもツムギちゃんも気を付けてね。家、ついたらメールしなさいよ」
「元気でな」
「うん。ありがと。ほら、もう家入っていいから。お母さん、足、痛いんでしょ」
母はそう言うけれど、祖父も祖母も、わたしたちが駐車場のところに歩いていって見えなくなるまで、ずっと見送ってくれていた。
わたしはそれが嬉しくて、なんども、なんども、振り返りながら、キャッキャと声を上げたっけ。
ほのかな雨の匂い、少しべたつくぬるい潮風、橙色《だいだいいろ》に染まる空、日焼けのひりひりが残る背中……。
また、来年も楽しみだなあ。
早く夏がこればいいのに。
ひと夏の名残《なごり》を感じながら、わたしはそんなことを思っていたんだ。
でも、母の様子はわたしとはぜんぜん違っていて、祖父母に背を向けたまま、一度も振り返らずに、静かにまっすぐ車のところに歩いていく。
「あっ」
わたしは小さく声を上げる。
祖父母の家から、駐車場までの道を辿《たど》って行くと、たまに見かけるのがセミの死骸《しがい》だ。
ちょっと前まで、あんなに元気はつらつと鳴いていたのに……。
石ころみたいに転がっている生き物の最期《さいご》の姿。
わたしはなんとなくそれを直視できなくて、無理やり目を背けた。
母はというと、セミのことなんて視界にも入っていないよう。
運転席に座った後も、なかなか車を出発させず、目の前に広がる海をぼうっと眺めるんだ。
「ママ?」
わたしが顔を見ようとすると、ふいっとそむけられてしまう。
「ごめん、ごめん。ちょっと、潮風が目に染みたみたい」
母はハンドタオルをとりだすと、ぐっと顔を押さえる。
わたし、知ってたよ。
そんなのウソだって。
だって、毎年、毎年、駐車場でおんなじことを繰り返すから。
母は声をおさえて泣いてたんだ。
だけど、その理由がよくわからなかった。
寂しいの? また、来年の夏も会えるのに。
電話だって、いつでもできるのに。
どうして、悲しくなるんだろうって。
自宅につく頃には、わたしは半分寝ぼけているから、意識はぼんやり。
車の外に出ると、近くの畑や田んぼから、秋の虫たちの鳴き声が聞こえてくる。
その音がやけにひかえめで切なくて、思わず耳をふさぎたくなる。
夏の終わりのかえりみち。
それはいつだって、わたしの胸をぎゅっと締め付けるんだ。
3
「さあ、着いたよ。長旅《ながたび》お疲れさん。あれ? ツムギ、起きてる?」
どこからか、旦那のナギトの声がした。
「あ、なに? ああ、もう家なの?」
わたしは体をもぞもぞと動かしながら、重いまぶたを持ち上げる。
「うん。なに? 寝ぼけてるわけ?」
「失礼ね!」
子供たちの夏休みも残り三日。
母の家から帰ってきたのだ。
なんだか、妙に懐かしい夢を見ていたような気がする。
「そう。ははっ。泣きつかれたんじゃない?」
ふざけるように彼が言った。
「……バレてたの?」
「そりゃあね。帰り、悲しそうだったから」
「あー。そっか、うん」
今ならわかる気がする。
祖父母の家からの帰りみち、母が泣いていた理由。
ひょっとしたらもう会えないかもしれない。
最後かもしれない。
そんな不確かでありながら巨大な感覚を、夏のおわりの風とともに肌でひしひしと感じていたんだ。
今のわたしみたいに。
「俺だけじゃなくって、うしろのトキとルナもね。二人とも、なんにも言わなかったけど、心配そうにしてたよ」
後部座席《こうぶざせき》を見ると、ふたりは心地よさそうにすやすやと眠っている。
愛しさがこみあげてきて、表情が柔らかくなったのもつかの間。
わたしはトキの隣、後部座席のドアのところにある物置スペースを見たとたん、悲鳴を上げそうになった。
4
「ナギト、ナギト、ナギトってば!!!」
「なに? 聞こえてるって」
「あれ、あれ! なに、なんなのよ」
わたしが指差したものを見て、彼は笑った。
「ああ。車に乗る前にさ、トキが見つけて、持って帰るって」
「ええ! セミの死骸《しがい》よ。どうして?」
息子の行動が理解できず、声を荒げそうになる。
「お墓《はか》、作ってあげたいんだってさ。ほら、向こうでセミ獲りもしただろ。さすがにあのときのセミとは違うだろうけど、トキにとっては愛着あるみたいだったからさ」
ナギトはさらりと言った。
「セミにお墓って……。そんな発想、なかったわ」
「そうかな。俺はいいと思うけど」
ふいに、祖母の家の近くに転がっていたセミの死骸《しがい》を思い出す。
小さい頃、わたしが思わず目を背けた喪失《そうしつ》の気配。
「でも……そうね。そういうの、大切かもしれない。トキったら、優しいのね。それに、とっても強い子なんだわ、きっと」
「うん。明日にでも、みんなで庭に埋めてやろう」
ナギトの言葉にこくりと頷く。
車の外に出ると、少しひんやりとした風とともに、虫たちの声が流れてくる。
リン、リン、リン。
「あー。秋って感じだな。きれいな音。俺、秋の虫ってけっこう好きなんだよな」
ナギトはなんてことないようにそう言った。
「ええ? そうなの?!」
わたしは思わず声を漏らす。
「へん?」
「いや、おかしいわけじゃないけれど、ほら、この音ってなんだか、聞いてると切なくならない?」
「ああ、そういう感覚になるのもわかるよ。でも、俺はけっこう好き。ほら、夏はおわるけど、もうすぐそこでは、秋がスタンバイしてますって感じがするからさ」
「ふふ。なによ、スタンバイって」
なんだか表現がおもしろくって笑える。
「夏のおわりの余韻《よいん》に浸る間もなく、秋を感じられるだろ。季節のつなぎ目が曖昧《あいまい》になる。俺は、そういうところが気に入ってるんだよ」
ナギトは一瞬《いっしゅん》、真剣な表情になった、ような気がした。
「あー、なるほどね。それはちょっとわかる気がするわ」
「だろ」
二人でトキとルナをリビングのソファに下ろし、セミの死骸をティッシュペーパーの上に下ろし、リュックサックを玄関《げんかん》に下ろす。
リンリンリン。
心なしか、さっきよりも力強い音に聞こえた。
「ふふふ」
「え? なに?」
急に笑い出したわたしを見て、ナギトが後ずさった。
「ううん。なんでもない」
わたしは、秋の気配に耳を澄ませながら、母になんて電話をかけようか、と考えた。
家についたよ。体、大事にしてね。
それから……。
今はささやかで楽しい話をしよう。そう思った。
完