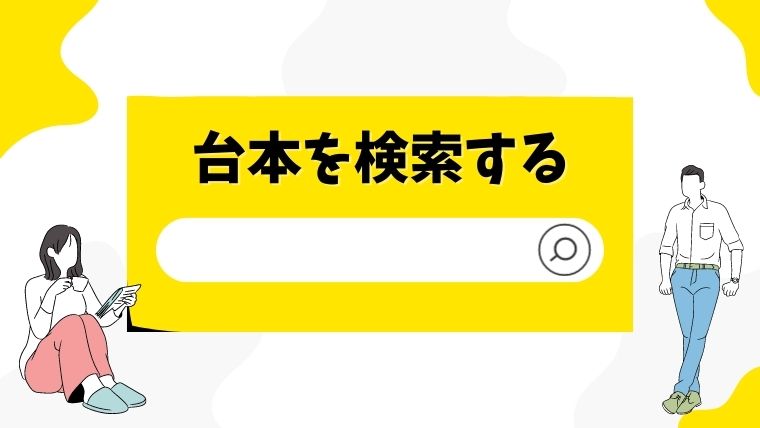●使用料:無料
●利用報告:商用のみ要(非商用は任意)
●クレジット表記:必須
ー表記内容ー
| 台本名 | 当ページのタイトル |
| 作者名 | 紺乃未色(こんのみいろ) |
| サイト名 | フリー台本サイト「キャラコエ」 |
| 台本URL | 当ページのURL
※リンク付け(URLをクリックすると、当ページに飛ぶように設定すること)必須 |
上記4点を必ず表記していただきますよう、お願いいたします。
利用のルールについては、利用規約をご覧くださいませ。
概要
| カテゴリ | 朗読(一人) |
|---|---|
| ジャンル | 現実世界 |
| 時間(目安) | 30分~40分 |
| あらすじ | 小さい頃から仲がよかったはずのみーちゃん。 なんとなく、気づいてる。 二人のあいだに距離ができているんだってことに。 |
| 注意 | このストーリーはフィクションです。実在する人物や団体、出来事などとは一切関係がありません。 |
その他、朗読におすすめの台本は、以下のページにまとめています。

フリー台本『カブトエビのみーちゃん』
1
「ねえ、まなみ。弱肉強食って知ってる?」
六年二組の教室で、スプーンを手にしたみーちゃんはそう言った。
「じゃくにくきょうしょく?」
わたしは牛乳のパックを持ったまま、おんなじ言葉を口にした。
そこで、やっと意味がわかった。
ついさっき、授業で使っていた図鑑の表紙が頭のなかに浮かんでくる。
タカがねずみをくわえて、飛んでいるやつだ。
「うん」
「弱いものは、強いもののエジキになるんだって。人間も一緒だよね」
みーちゃんは、コッペパンを指でちぎりながら、なんでもないことのように言った。
「え?」
みーちゃんは、どこか大人びていて、わたしにはよくわからないことを話すんだ。
「なんでもない」
みーちゃんは、わたしの目を見て、早口で言った。
黒目がちなくりくりとした目と長いまつげ。
お人形さんみたい。
そんな彼女は、あたり前のように、男の子からも人気だ。
胸がちくりとする。
わたしが、いいな、と思っていた学級委員長の山下くんは、どうやらみーちゃんのことが好きらしい。
そのウワサを聞いたときのことを思い出してしまった。
もう、半年も前のこと。
ふっきれたつもりでいたのに。
わかってる。
わたしじゃ、みーちゃんにはかなわない。
どこにでもいそうな顔立ちのわたしと、ぜんぶのパーツが整っているみーちゃん。
体操服や赤白帽子が似合うわたしと似合わないみーちゃん。
ぜんぜん、違うのだ。
それでも、昔はよく一緒に過ごした。
バッタやチョウチョを追いかけたり、フナやカエルを捕まえたり、どろんこになって砂場で遊んだり……。
今のみーちゃんは、とてもそんなことをするようには見えない。
彼女は、毎日、どんなことを考えているんだろう。
みーちゃんは、さっきからずっと下を向いている。
わたしもなんとなく、視線を落としてぼうっとした。
まだ、給食は残っているけど、そういう気分だったから。
視界のなかには、うっすらと湯気《ゆげ》を立てている、春雨《はるさめ》スープがあった。
つるんとしたうずらタマゴ、光る春雨。
それから、そのとなりに浮かんでいるはシイタケたちだ……。
わたしは、ぼんやりとお椀《わん》のなかを眺めていた。
だんだんと目の前がぼやけてきて、シイタケの形が変わっていく。
「あっ!」
小さく声を上げる。
カブトエビが四匹、スープのなかを泳いでいた。
2
田んぼの土のなかから、ぴょんぴょん飛び出るイネの葉っぱたち。
その間を、カブトエビが泳いでいる。
今よりも幼かったわたしは、その小さな生き物を宇宙人みたいだと思っていた。
ひっくりかえると、足がうようよとうごめいていて、背中がぞわぞわとする。ちょっぴりイヤな光景だ。
だからわたしは、背泳ぎしているカブトエビを見つけては、指先でもとの体勢に戻していたっけ。
「これ、なんだろう。魚?」
「虫みたいでもあるよね」
みーちゃんと、そんな会話をしたことも覚えている。
昔、といったって三年前のこと。
もっともっと、遠い過去のことのようにも思える。
ある日のことだった。
わたしとみーちゃんは、その日、おままごとで使うスープ皿を水槽《すいそう》代わりに選んだんだ。
直径が約十五センチくらい、深さが五センチくらいのそれは、手のひらですくったカブトエビを入れておくのにぴったりだったから。
「たくさんとれたね」
わたしが言うと、みーちゃんも「そうだね」と口にして笑った。
二人で四匹のカブトエビを観察していると、遠くの方から声がした。
「まなみー! みーちゃん! ちょっと来てちょうだい」
お母さんだ。
わたしたちは、その場にスープ皿を置きっぱなしにして、声のする方へと走っていった。
しばらくして、元のところへ戻ると、みーちゃんが声を上げた。
「まなみ! みんないなくなってる!」
「本当だ!」
わたしたちはびっくりした。
スープ皿のなかにいたはずの、カブトエビが消えていたからだ。
最初から、そこには、なんにもいなかったかのように。
「カブトエビ、四匹とったよねえ?」
みーちゃんが首をかしげた。
「うん。とったよ。ぜったいに……。あっ!」
わたしは小さく息をのんだ。
すぐにみーちゃんが短い悲鳴を上げた。
スープ皿のまわりで軽やかに弾んでいたスズメの一匹が、口からカブトエビを吐き出したのだ。
「吐いた……」
みーちゃんがつぶやく。
スズメはすぐに、もう一度カブトエビをくちばしで突いて、あっというまに食べてしまった。
「食べた」
わたしは、目の前で起こったことを、そのまんま言葉にすることしかできなかった。
からっぽになったスープ皿の表面を風が撫《な》でていく。
わたしたちは、そんな光景をぽかんと眺めることしかできなかった。
ぽっかりと心に小さな穴が空いたような気分になった。
後になって「喪失感《そうしつかん》」「虚無感《きょむかん》」そういう言葉を知った。これに近いんじゃないかな、と思った。
でも、よくわからない。
わたしはあのときの感覚を、いまだに上手く言い表せなかった。
みーちゃんも、おんなじように感じていたんだろうか。
……そもそも、覚えているのかな。
そんなことを考えているうちに、春雨《はるさめ》スープのなかを泳いでいたカブトエビは、細切りのシイタケへと戻っていった。
「ねえ! みーちゃん、カブトエビのこと、覚えてる?」
わたしが聞くと、みーちゃんは言った。
「カブトエビ? なにそれ」
「ごめん、なんでもない」
けっこう、ショックだった。
「うん」
みーちゃんは、カブトエビについて深く聞いてくることすらなかった。
その悲しさを追いやるようにして、わたしは明るい声を作って尋ねる。
「ねえ、今日の放課後、遊べる?」
みーちゃんは、ちょうど牛乳パックのストローをくわえているところだった。ぽこっと音を立てて、パックがへこむ。
「あ、忙しかったら、いいんだけど」
「……ごめん」
みーちゃんは、それだけ言った。
ふと、寂しくなった。
「あ、いいの、いいの」
「中学受験に向けて、勉強しなきゃ。まなみは? B中学、受けるんでしょう? レベル高いって聞いてるけど」
「え、わたし? ああ、うん。大丈夫だと思う」
もうみーちゃんとカブトエビの話をすることはないんだろうな。
わたしはそう思いながら、彼女の質問にぼんやりと答えた。
3
中学三年生になると、一年が過ぎていくのが、けっこう早くなった。
わたしは変わらず、騒がしい田んぼの近くに住んでいる。
六月にはカエルが大合唱をはじめるし、梅雨《つゆ》が明けると、今度はセミのコーラス。
年中、なにかしらのコンテストでも開催されているんじゃないかって思う。
「水族館、俺、久しぶりだわ」
わたしのすぐ横で、ナオトくんが言った。
彼は、図書委員会の元先輩で、よくわたしの面倒をみてくれていた。
生まれて初めてできた恋人でもある。
「うん! わたしも子どものとき以来かも」
ナオトくんは、わたしがぼんやりと考え事に耽《ふけ》っていても、そっと見守ってくれている。
でも、ウワサによると、もっと、お姫様みたいな子がタイプらしい。
「どうしてあの子と?」という言葉はできるだけ、聞かないようにしていたけど、やっぱり気にはなる。
「わ! あそこにいるの、サメだぞ? 近くで見よ?」
「うん。その前にクラゲのところ行きたい」
ナオトくんは、手を引いてくれる。
わたしはうんと背伸びをしているから、少しヒールのあるサンダルで歩くのが精いっぱい。
友人に髪をアップにした方がいいといわれて、ポニーテールにしてみたものの、強く括《くく》りすぎたのか、結び目も痛くてちょっぴりつらい。
ちなみに、この友人というのは、みーちゃんじゃない。
彼女とはべつべつの中学校に入ってから一度も会っていない。
ケンカをしたわけじゃないけど、お互い、志望校に受かって、毎日忙しいのだと思うことにしている。
「うわあ。きれい」
わたしはうっとりとクラゲを眺めた。
ゆらゆら動くその子を見ていると、いろんなことが頭に浮かんでは消えていく。
日々、あれこれ考えている脳が癒《いや》されて、かってに情報が整理されていくみたいだ。
「ねえ、まなみちゃん。大丈夫?」
声をかけられ、はっとする。
「あ、うん」
「まなみちゃんは、ときどき自分の世界に入っちゃうよね」
「ごめん」
「いや、悪い意味はなくていいと思う、うん。可愛いし」
「もう! からかわないでよ」
ふいっと顔をそむける。
そういう言葉は、わたしには似合わない。
もっと、べつの子を表現するときに使う形容詞だ。
例えば……。
そこまで考えて首を振る。
今は、よけいなことは考えたくない。
わたしは早足で、サメのいる大きな水槽《すいそう》のところへと歩いていった。
「待てってば!」
後ろから、ナオトくんが追いかけてくる。
慌てた雰囲気が伝わってきて、思わず頬《ほお》が緩んだ。
4
「ひゃあ!」
「近くで見ると、迫力あるよな」
わたしたちは、巨大な水槽を前にして、興奮したように声を上げた。
大きな魚や小さな魚、白黒のしましまに、派手な色をした魚。
さまざまな生き物がそこには存在していた。
まるで、海の一部をきりとって、透明のガラス箱に飾りつけたみたい。
わたしたちの視覚は、岩のマネをしていた生き物にびっくりしたり、同じ方向に進む魚のグループに感心したりと、目の前の光景に反応し続けた。
「なんか、不思議だよな」
ナオトくんがぽつりと言った。
「え?」
彼に視線を向けて息をのんだ。
思っていたよりもずっと、真剣な表情をしていたからだ。
「だってさ、こんなにいろんな魚がいるんだよ」
「うん」
ナオトくんの言葉の先がわからず、ただあいづちを打つ。
「ほかの魚、食べないんだろうか」
浮かんできたのは、いつの日かみーちゃんが口にした言葉だった。
「弱肉強食……。たしかに、気になるかも」
わたしがそう言ったときだった。
「気になるかい?」
五十代半ばくらいの男性が、声をかけてきた。
「え? 答え、わかるんですか?」
思わず、大きな声が出た。
「いやあ、僕も水族館の人間じゃないから、正しいかどうかはわからないけどねえ」
男性がふにゃりと眉を下げて笑った。
よく見ると、黒と白のシマシマ模様のTシャツを着ている。
さっき見た、小さな魚みたいだと思った。
「なにか、知ってるんですか?」
ナオトが聞いた。
「そうだねえ。この水槽の世界では、エサも十分に与えられている。つまり、みんなそれなりに満足していて、バランスがとれているんじゃないかな。わざわざそれを崩す必要もない」
「バランス?」
わたしが言うと、シマシマの男性は大きくうなずいた。
「そう。さっき、君は弱肉強食って言ったでしょう?」
なんだか少し恥ずかしくなって、わたしは小声で返事をした。
「彼らはね、無駄な捕食《ほしょく》はしないんだ。ほら、みてごらん」
シマシマの男性は、巨大な水槽の一部を指差した。
そこでは、大きなサメが悠々と尻尾《しっぽ》を揺らしながら泳いでいる。
その左下の方では、小魚たちがお互いの体を突き合っていた。
「無駄な捕食《ほしょく》……」
聞きなれない言葉だった。
「ほしょく」はわたしにとって、少し難しい。
「お腹が空いてないときに、わざわざ食べないってことですか?」
となりから、ナオトくんが尋ねる。
「そうそう。狩りが必要のない環境では、むやみやたらに、他の魚を襲うことはないんだと思うよ」
「へえ」
ナオトくんが感心したように言った。
「たとえ、弱い者であっても、必ずしも強い者に食べられてしまうわけではないってことですね」
わたしがそう口にすると、シマシマの男性は目をまんまるくさせた。
「君、なかなかおもしろいまとめ方をするね」
「俺も思った」
ナオトくんが同意する。
それから彼らは顔を見合わせて、笑った。
「まあ、そのあたりは、人間の方が大変かもしれないねえ」
シマシマの男性は、巨大な水槽に視線をやり、つぶやいた。
「どういうことですか?」
わたしは尋ねずにはいられなかった。
「人間社会という水槽のなかでは、弱い者はとことん生きづらい」
シマシマの男性は、しぼんだフグみたいに大人しくなってしまった。
「弱い者……」
わたしが小さな声でそう言うと、彼はぱっと明るい表情を作った。
「いやいや。若い子にこんなこといっちゃダメだね。……でもね、ここにくると、希望が湧くんだよ。強いも弱いも関係なく、うまくやっていけるんじゃないかってね。ごめんね、いきなり。じゃあね」
後半の言葉は、彼自身に言い聞かせているようにも思えた。
わたしとナオトは、突っ立ったまま、シマシマの男性の背中を見送った。
やがて、彼は人の群れに隠れて見えなくなった。
ふいに切なさのようなものがこみあげてきて「元気でね」と、心の中でひっそり願った。
その後は、イルカショーの会場でひとやすみ。
冷たいお水を飲んでいると、シマシマの男性の声が蘇ってきた。
「弱い者はとことん生きづらい」
わたしは、みーちゃんのことを思い出していた。
どうしてか、まったくわからないけど。
「教えてあげなきゃ。弱肉強食、そんなに気にしなくても大丈夫なんだって」
わたしの声は、水族館のスタッフさんが吹いた笛の音にかき消された。
5
どこからともなく流れてくるピアノ音に、はっとした。
ずいぶんと長い間、考え事をしていたような気もするけれど、まだ、ここにきて十分しか経っていない。
ナオトと水族館に行ってから一ヶ月が過ぎていた。
わたしはスマホを握りしめ、七月の夕暮れ、田んぼのはしっこで彼女を待つ。
なんとなく、あたりをぐるりと見渡すと、建設途中の建物が目に入った。
あそこには、老人ホームができるらしい、とお母さんが言っていたっけ。
三十メートル先には、もうひとつ、できたばかりの施設がある。
変わっていく町と、止まったままのわたしとみーちゃん。
それも、今日までだといいな、だなんて考える。
なんだか、心臓のあたりが、ドクドクうるさい。
「まなみ」
懐かしい声に名を呼ばれて振り返る。
「みーちゃん!」
黄色のワンピースを身にまとったみーちゃんは、少しだけ大人っぽくなっていた。
きっと、今でも、男の子にモテるんだろう。
なぜか、ナオトくんの顔がよぎる。
思わず顔が引きつりそうになって、視線を落とした。
アスファルトに映る自分の影が、いびつなくらいに伸びている。
言いたいことは決まっていたはずなのに、どうしてかうまく言葉がでない。
「あのね……」
先に、沈黙を破ったのは、みーちゃんだった。
生ぬるい風が、向かい合わせになったわたしたちの間を吹き抜けていく。
「ずっとまなみに謝りたくて」
「どうして?」
わたしの声はまぬけなくらいに裏返ってしまった。
「小六の頃から、変な距離ができていたでしょ。それ、私のせいだから」
「でも、みーちゃんは、受験勉強とかで忙しかったから……」
「違うの!」
みーちゃんは大きな声でわたしの言葉を遮った。
「違うのよ」
彼女は、もう一度、今度は静かな声で言った。
「まなみのことが羨《うらや》ましかったの」
「わたしが?」
さっぱり意味がわからない。
みーちゃんが、わたしを羨《うらや》む理由があるものか。
「うん。だって、まなみは昔から、頭がよかったでしょう?」
「え? そうかな? まわりから褒められた記憶もないし、普通だと思うけど」
「ううん。国語も算数も社会だって、いつも八十点以上だったもの。私のお母さんがね、よく聞いてきたの。まなみちゃんは何点だったのって」
そこでやっと、わたしはみーちゃんの気持ちがわかったような気がした。
なんと声をかければいいのかわからず、黙り込む。
「それでね、受験が近くなってた六年の頃から、まなみに冷たくなってたんだ。……ごめん。本当に」
「うん。こっちこそ、ぜんぜんみーちゃんのこと、理解できてなかった。わたし、悪気なく、テストの点数とか聞いてたし……。あれ、いやだったでしょ?」
「まあ、それなりにね」
「……ごめん」
「あ、違うの。べつにまなみは悪くないから。……あのね、最近、仲の良いグループで、テストの点数を競《きそ》ってたんだ。最初は、みんなゲーム感覚だったんだけど、だんだん本気になってきたのか、ケンカしたり、カンニングしたりする子まででてきてね、笑っちゃうでしょ?」
「カンニング?」
思わず声が大きくなった。
「そう。びっくりでしょ? それで、私、バカらしくなってきたんだ。点数とるために、そこまでする? って。でも、よく考えたら。私もまなみとテストが原因で疎遠《そえん》になったからなって思って、反省して……」
「……うん」
「そんなときに、まなみから連絡来て、嬉しかった」
みーちゃんは、ごめんねの次に、ありがとう、と言った。
「こっちこそ、ありがと。会ってくれないんじゃないかって、ヒヤヒヤしたたんだ。ついさっきまで」
そこまで口にすると、全身の力が抜けるような感覚がした。
よかった、本当に。
6
それから、みーちゃんと並んで、田んぼの近くにあるベンチに座った。
視界いっぱいに、田んぼの緑色が映り込む。
スズメが五、六羽飛んできて、わたしたちのそばで飛び跳ねた。
「スズメ……」
みーちゃんがつぶやく。
「うん。スズメだね」
「……食べてないね」
みーちゃんの言葉に、どくりと胸が鳴った。
穏やかな夕暮れの空気が、ぴんと張りつめる。
なにを? だなんて聞かなくてもわかる。
わたしはただうなずいた。
「あのときのこと、本当は覚えてたんだ」
「あのとき……」
「ほら、目の前でスズメがカブトエビ、食べちゃったときのこと。衝撃だったなあ」
「うん。わたしも、なぜか忘れられない」
「あ、給食のときのことも謝らなきゃ」
みーちゃんは、体の向きをわたしの方へと向けた。
「給食って?」
「ほら、給食のとき、私が弱肉強食の話をしたでしょ? そしたら、まなみが、聞いてきたじゃない。「カブトエビのこと覚えてる?」って」
「あ、うん」
「そのときね、私、忘れてるふりしたの」
本当は覚えてたんだ!
そう感心するとともに、ひとつの疑問が浮かんでくる。
「どうして?」
「……あのときね、スズメがまなみで、カブトエビが私のような気がしたんだ」
さっきまでの、みーちゃんの事情を聞いたあとだと、なんと言うのが正解か、ちっともいいアイデアが浮かばない。
「あ、もう大丈夫だから、気にしないでよ。べつに私たちが競い合う必要ないもの」
みーちゃんが笑った。
「あ! あのね! みーちゃん」
わたしは、彼女と会おうと思った目的を思いだした。
「うん?」
「共存できるんだよ」
「共存?」
「弱肉強食の世界でもちゃんと共存できるの。わたし、水族館で教えてもらったの!」
わたしは強い口調で言った。
みーちゃんにではなく、自分に言い聞かせているようでもあった。
これから先、むやみに誰かと比べてしまわないように。
大きな力に怯《ひる》むことがないように。
一文字ずつ、はっきりと口にする。
「常に何かと闘う必要はないんだって。魚も、人間も。うまく、言えないんだけど」
なんとかして説明しようと言葉を紡ぐけれど、人に伝えるのって難しい。
「うん。わかる気がするよ」
みーちゃんは優しい表情でうなずいてくれた。
それが、とても嬉しかった。
その後、二人でいろんな話をした。
学校のこと、家のこと、そして恋のことも。
やがて、風がどこかの家の夕食の香りを運んでくる。
今も昔も変わらない匂いだ。
「ねえ、まなみ」
ふいにみーちゃんが声をかけてくる。
「うん?」
「これからもよろしくね」
みーちゃんが笑った。
これからは、じゃないのが嬉しかった。
「こちらこそ!」
わたしが元気よく言うと、近くにいたスズメたちがバサバサッと飛び上がり、電線の上に移動した。
思わずびくりと肩が揺れる。
「ふふ。まなみの声が大きいからびっくりしたんじゃない?」
みーちゃんがからかうように言った。
「えー。もう、一斉に飛ぶんだもん。こっちの方が驚きよ」
わたしは赤く染まった空の方を見上げた。
いつのまにか、十羽以上に増えていたスズメたちが、じっと、こちらの様子をうかがっているように見える。
「ねえ、みーちゃん。今度、一緒に水族館行こうよ」
わたしは、スズメたちから視線を逸らすようにして、あえて、明るい口調で言った。
「うん! 来月の土日なら、いつでもいいよ」
「やったー」
わたしとみーちゃんは、なんでもないことを話しながら、二人並んで田んぼの脇を歩き出す。
遠い昔、一緒に遊んでいた頃のように。
完